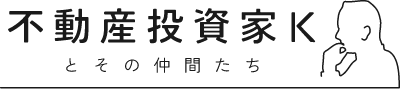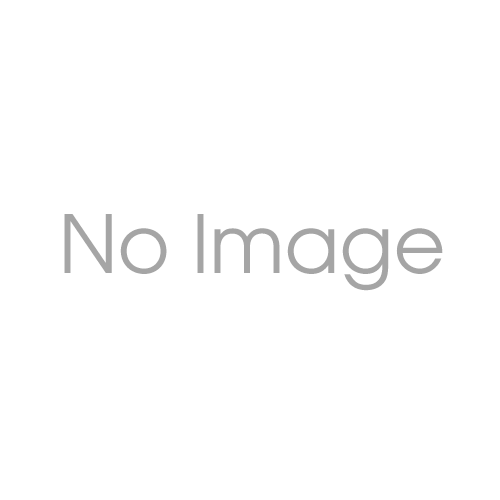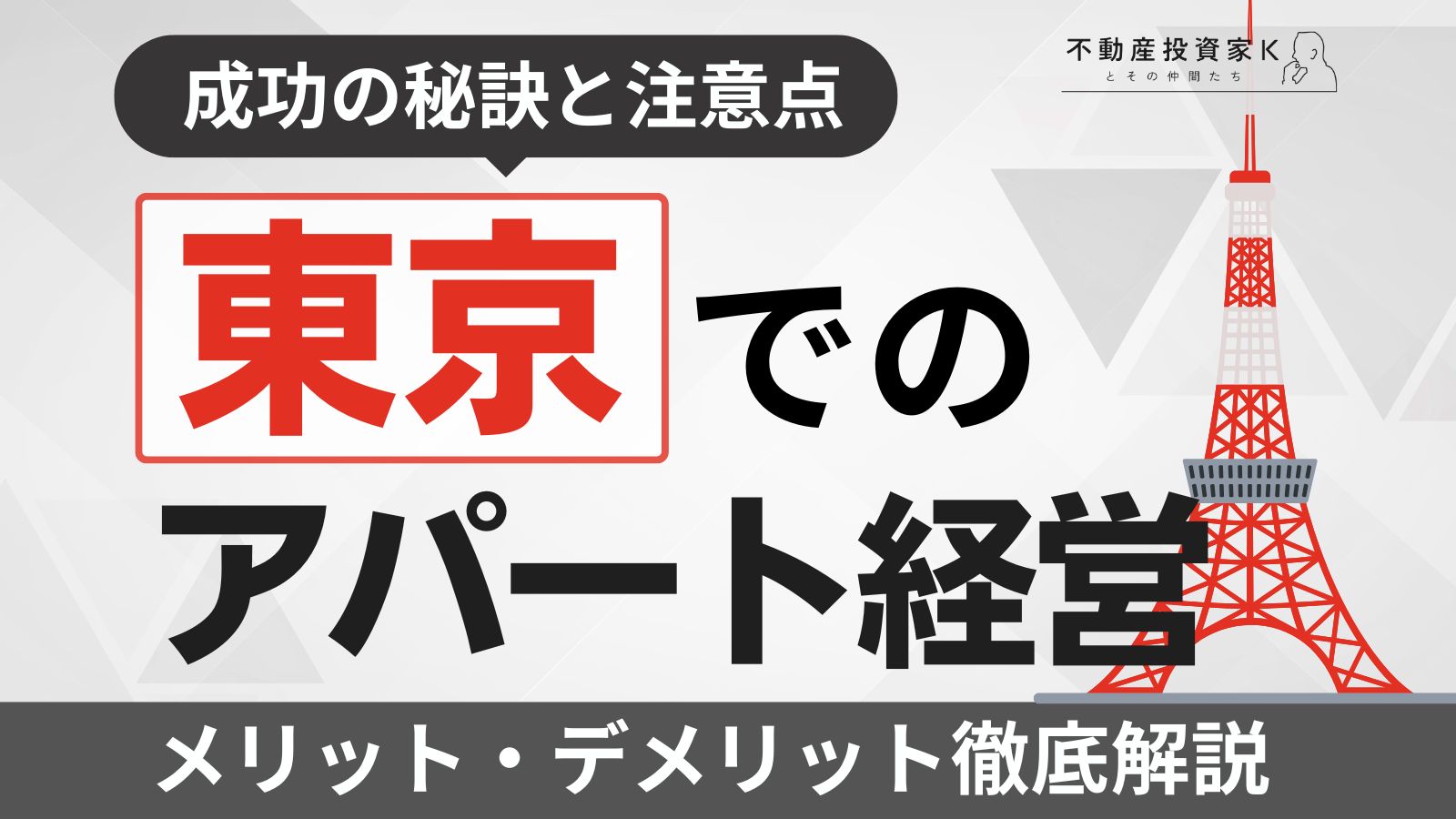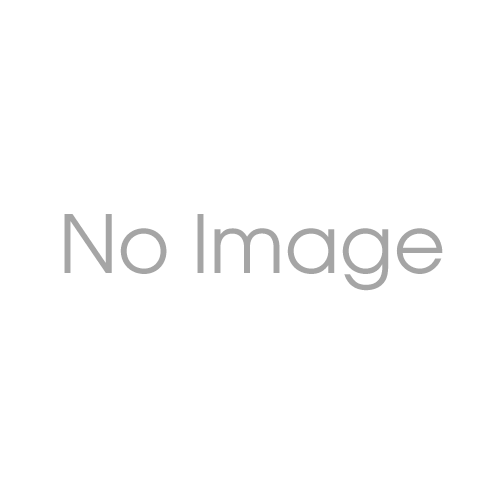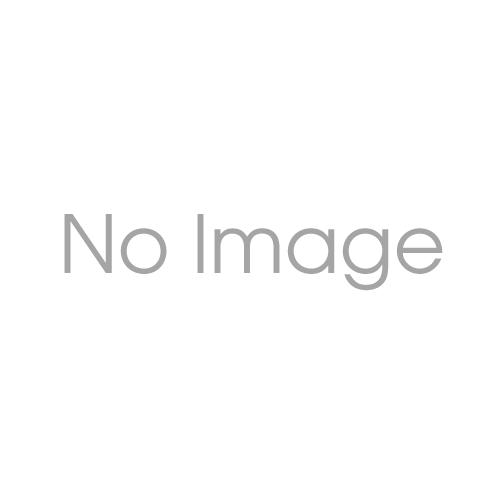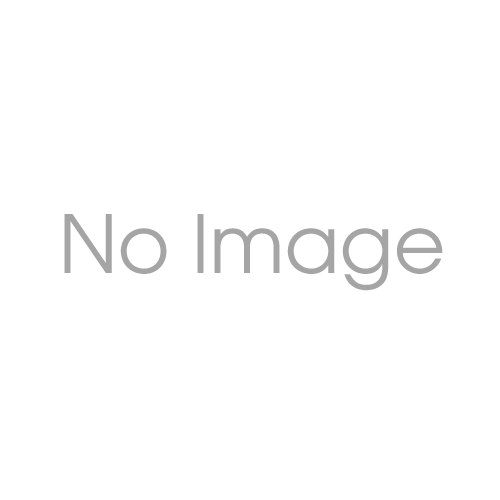
借地権が設定された土地を示す用語に「底地(そこち)」があります。「借地」との違いが分かりづらいと感じている人もいるかもしれません。
この記事では底地の基礎知識やメリット・デメリット、借地との意味の違いなどについて詳しく解説します。とくに大きな資金が関係する不動産取引では誤解されないよう、正しく用いることが重要です。
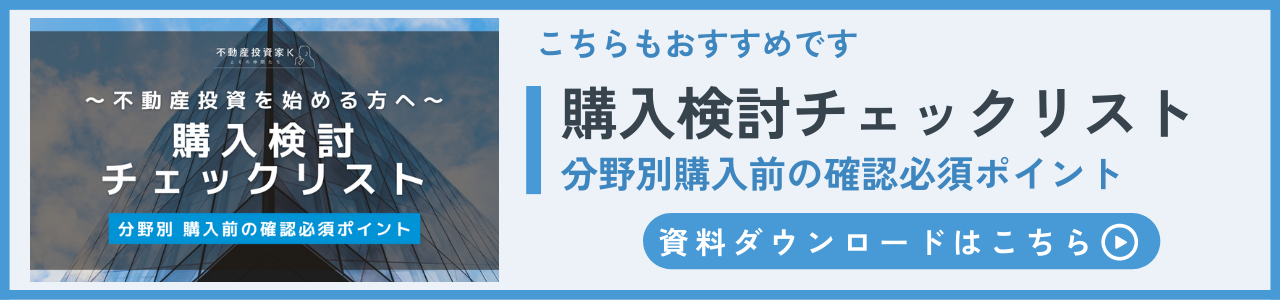
ポイント
- 底地とは上に建物を建てることを前提に貸し出している土地の、土地所有者から見た名称である
- 底地には所有権だけでなく借地権が設定されることから、評価額は低く設定される
- 底地にかかる税金は低く抑えられるが、そのまま売却するのは難しく、売却金額を低く設定せざるを得ないことが多い
底地とは
底地とは、借地権が設定された土地のことをいい、貸地とも呼ばれます。借地権とは「他人の所有する土地を利用する権利」です。借地権があれば借りた土地に建物を建てられます。底地とは建物の建てられた貸地であり、土地所有者が貸している土地そのものです。
借地権は賃借権と地上権に分けられ、どちらを設定するかによって建物の建っている土地の取り扱いは異なります。
| 賃借権 | 原則として建物の建て替えや売却には土地所有者の許諾が必要 |
| 地上権 | 土地所有者の許諾なしでも原則として土地の賃貸や建物の売却などができる |
土地所有者と借り手(借地人)の合意があればどちらの権利でも設定できますが、とくに住宅を建てる場合は、土地所有者に有利な「賃借権」を設定するのが一般的です。これは借地人は借地借家法により権利が保護される影響ともいわれています。
借地とは
借地とは借地権の設定された土地を指し、借地人が土地所有者から「借りている土地」を意味します。「借地」と呼ぶのは、借地人が土地の上に建物を建てており、建物ではなく土地のみを借り受けているためです。建物のない駐車場や資材置き場などのために借りた土地は借地借家法の適用外となるため、借地権は設定されません。
たとえば住宅を建てるとき、土地と建物の両方を購入する方法もありますが、借地権を利用すれば土地を一定期間まとめて借りられます。契約期間満了で改めて手続きする必要はありますが、土地の固定資産税が課せられず、住宅ローンも建物分のみの返済に抑えられるのはメリットといえるでしょう。
底地と借地の違い
ある土地の賃貸借契約において、その土地は土地所有者にとって貸地であり「底地」です。借地人にとっては建物を建てるために借りた「借地」です。つまり借地と底地は「同じ土地」を指しており、土地所有者と借地人という立場によって「異なる呼び名」を表す用語です。
しかし、これが権利を表す「底地権」「借地権」となると事情は変わります。底地権とは土地所有者の権利、借地権は借地人の権利であり、両者はまったく異なります。底地・借地という用語の示す土地がたとえ同じ土地であっても、底地権・借地権という権利は違うと覚えておきましょう。
底地権と借地権の違い
底地権・借地権は借地借家法によりそれぞれ次のように定められています。
- 底地権:底地を所有する権利だが、借地人が借りていて建物が建っている場合土地所有者は土地を自分のために利用できない
- 借地権:借地人が土地所有者から借りている土地に建物を建てて利用できる権利で、契約によっては建物の建て替えや売却に土地所有者の許諾が必要になる
借地権はさらに普通借地権と定期借地権に分けられ、いずれも借地人のメリットが大きいといわれています。
| 普通借地権 | 定期借地権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 | ||
| 存続期間 | 30年以上 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満(契約内容による) |
| 更新後の存続期間 | 1回目20年 2回目以降10年 |
なし | なし | なし |
| 利用目的 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 事業用に限定 |
| 借地関係の終了 | 正当な事由が必要 | 期間満了 | 建物の譲渡 | 期間満了 |
底地権は、底地である限り土地所有者が土地を自分のために利用できないと定めているのは、土地所有者にとって不利です。また、借地権では存続期間を10年〜50年以上の長期と定めていることや多くの場合借地人の利用目的に制限がないことによって、借地人が契約を長期間維持しやすい定めであるといえます。
そのため土地所有者は、借地借家法による制限を十分に理解し、契約内容を定めることが重要です。長期間の取引となる場合が多く、将来の土地の取り扱いなどについてもしっかり検討する必要があるでしょう。
底地の所有者はだれか?
底地の所有者は、土地の「地主」や「地権者」です。底地の場合、とくに「底地権者」と呼ばれることもあります。
ただ通常の土地所有者が原則として土地をさまざまな用途に自由に利用できることに対して、底地の所有者は借地権が設定されているため、売却や土地の一部利用なども所有者の一存ではできません。土地の所有者ではあってもできることはかなり限定的です。
底地の所有者は土地を貸し出すことで借地人から賃料や契約更新料といった収益を得ます。借地権は10年から50年といったスパンで設定されるため、長期にわたって安定した収益が期待できるともいえるでしょう。
底地の評価額の決め方は?
土地所有者が底地を売却したいと考えた場合、その売却価格はどのように算出するものなのでしょうか。目安としては、その土地が更地だった場合の評価額から借地権割合を引いた額が、底地の評価額となります。
更地の場合の土地評価額 = 路線価×奥行価格補正率×地積
底地の土地評価額 = 更地の場合の土地評価額×(100%-借地権割合)
参考:国税庁 奥行価格補正率表
底地の売却には、第三者となる借地人が関係するため、購入希望者は少ない傾向があります。そのため、底地の状態で高く売れることはまずないでしょう。
底地に固定資産税はかかる?
底地には「固定資産税」が課せられます。ただ底地は通常、建物が建っている土地であるため、固定資産税が優遇され低く抑えられるのはメリットといえるでしょう。建っている建物が住宅の場合の固定資産税は、以下のように軽減されます。
| 小規模住宅用地の特例 (面積200平方メートルまで) |
固定資産税は6分の1に軽減 |
| 一般住宅用地の特例 (面積200平方メートル以上) |
固定資産税は3分の1に軽減 |
計算式で表すと次の通りです。
固定資産税の軽減額 =
(固定資産税額)×(200平方メートルまでの面積/土地全体の面積)×6分の1
+ (固定資産税額) × (200平方メートルを超える面積/土地全体の面積) × 3分の1
たとえば250平方メートルの更地の固定資産税が50万円だった場合、建物が建っていることで次のとおり金額が軽減されます。
面積200平方メートルまで(小規模住宅用地分)
50万円 × (200平方メートル/250平方メートル) × 6分の1 = 66,600円
※固定資産税を計算するときは、計算結果の10円単位未満を切り捨てるため、上記は計算結果の「66.6666……円」を切り捨てて示しています。
面積200平方メートル超(一般住宅用地分)
50万円 × (50平方メートル/250平方メートル) × 3分の1 = 33,300円
※固定資産税を計算するときは、計算結果の10円単位未満を切り捨てるため、上記は計算結果の「33.3333……円」を切り捨てて示しています。
合計
66,600円+33,300円=99,900円
また住宅以外の建物が建っている場合の固定資産税は70%に抑えられるため、どちらにしても固定資産税は、更地より底地である方が支出は低く済ませられるといえるでしょう。
底地を担保にできる?
底地は、不動産としての価値を利用する「担保」にして融資を受けることも可能です。ただし担保となると、債務者が返済不能に陥ったときの補填として底地を売却することになります。
底地は前述の通り、借地人が存在するため売却の難しい土地です。その分、更地としての評価額よりかなり低い価値として評価されるため、あまり高額な融資は受けられないのが一般的です。
底地のメリット・デメリット

所有している土地を底地として貸し出せば、賃貸収入などのメリットを得られますが、同時に注意すべきデメリットもあります。どちらも正しく把握しておく必要があるでしょう。
ここでは底地から土地所有者が得られるメリットと、踏まえておくべきデメリットについてみていきましょう。
所有者視点のメリット
土地所有者から見た底地のメリットは、およそ次の3つです。
- 固定資産税額を低く抑えられる
- 賃貸による収入が得られる
- 管理の手間が不要
固定資産税は、土地をただ更地として所有しているより、住宅をはじめとした建物が建っていることで軽減されます。先にも説明したとおり、土地の面積にもよりますが、税額は更地の3分の1または6分の1です。また、そもそも底地は更地より価値を低く評価されるため、固定資産税額も低く設定されます。これらの固定資産税の軽減は、土地を底地とする大きなメリットといえるでしょう。
底地は土地を借地人に貸し出している前提であるため、賃貸借契約による賃料や契約更新料といった収入を得られるメリットもあります。得られた収入を固定資産税に充当するのも良いでしょう。
さらに、土地は借地人が管理するため、これまで必要だった管理の手間も費用もかからなくなります。
所有者視点のデメリット
一方、土地所有者から見た底地に関するデメリットは次の3つです。
- 賃貸での高い収益性が期待しにくい
- 売却が難しい
- 担保価値を認められない場合がある
これらのデメリットは、底地である状態の土地の価値が一般的に低いことに起因しています。底地の賃貸借契約は借地権の関係で長期契約となるため、周辺環境の変化などに応じた賃料の値上げが難しく、他の活用法に比べ高い収益性は期待しにくいといえます。
同様に借地権付きの土地を好んで購入したいという買い手は少なく、売りに出しても長期間買い手希望者が現れないかもしれません。そうなると希望金額どころか相場金額での売却さえ難しくなるでしょう。
また、底地は担保の価値も低く評価されがちです。融資での担保にしても価値を認められない可能性があります。
底地に関するよくあるトラブル

底地として土地を借地人に貸せば、借地人とは長期間にわたる取引となるため、なかにはトラブルが起きてしまうこともあるでしょう。底地に関するトラブルは相続、借地権者との取引、売却時の大きく3つに分けられます。
ここでは底地に関するよくあるトラブルを紹介し、事前の備えや対処法について解説します。
相続のトラブル
底地も、相続するときは相続税の課税対象とされます。しかし、底地は更地よりも評価額が低く税額も低くなるため、底地としての活用は相続税対策としても有効といえるでしょう。
ただ相続人が複数の場合、土地を分筆するのではなく共有名義とすることがあります。しかし、これは後でトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。
底地には所有者と借地人がおり、それぞれの権利を持っています。それだけでも複雑な権利関係といえますが、さらに所有者が複数になれば、土地の取り扱い変更などで同意を得なければならない権利者が増え、そのうち1人でも同意が得られなければ変更はできません。手続きをきっかけに関係が悪化してしまうこともあり得ます。
複数の相続人で土地を含めて相続する方法は共有名義だけではありません。その他の方法を慎重に検討し、後でトラブルにならないよう配慮する必要があるでしょう。
借地権者とのトラブル
底地の賃貸借契約には、所有する底地権者と借りている借地権者という異なる権利を持つ両者が関係します。賃料や契約の更新、立ち退きなどにおいて、次のようなトラブルが発生する可能性があるため注意が必要です。
- 固定資産税の増加による賃料の値上げ交渉に時間がかかる、または値上げができない
- 契約の更新時に請求した更新料の支払いを断られてしまう
- 売却や活用法の変更などで求めた立ち退きに応じてもらえない、立ち退き料を請求される
これらの支払いや対応に関するトラブルは、賃貸借契約の条項として明記することで避けられます。しかし、明記しておらずトラブルとなってしまった場合は、まずは専門家に相談するのが有効です。変更の理由が正当と認められれば、契約は解除できます。交渉の前に認められるかどうか相談しておくとよいでしょう。
売却時のトラブル
土地は底地の状態では、たとえ地権者といえども一存で売却はできません。必須ではないものの、関係する権利を持つ借地人には、事前に売却の意向を伝えておいた方がトラブルは避けられるでしょう。
突然、また一方的に借地人に知らせてしまうと不安や疑念を抱かれかねません。スムーズな売却・手続きのためには、事前に丁寧に説明し理解を求めることが大切です。
もし底地が共有名義なら、共有する地権者全員の同意がなければ売却できません。共有名義のまま相続が発生すれば、権利関係はさらに複雑化し、手続きには多くの手間や時間がかかります。
売却の可能性を考えれば、底地もできるだけ早い時点で共有名義状態の解消などの対応が必要です。解消には、他の地権者から権利を買いとるなどして単独名義にしてから売却する方法があります。
まとめ

底地とは、土地を借地人に貸すことで借地権が設定された土地の、土地所有者から見た名称です。借地権は借地借家法によって保護されているため、底地は土地所有者であっても一存で売却したり建物を取り壊したりといったことはできなくなっています。いわば「思うように取り扱いにくい」土地であるため、一般的な市場での価値は低く設定されがちです。
また、底地は権利関係が複雑なため好んで購入するケースは少なく、底地のままでの売却金額も低く設定されやすいデメリットがあります。しかし、評価額が低いため固定資産税や相続税も低く抑えられ、継続的に賃料収入が得られることはメリットといえるでしょう。貸し出していれば土地は借地人が管理するため草刈りや清掃などの手間や費用も抑えられます。
ただし底地で注意したいのは、相続による権利関係の複雑化や、底地の取り扱い変更による権利関係者との交渉などにかかる手間やトラブルです。底地の性質や権利関係を十分に理解し、手続きは慎重かつ丁寧に進める必要があるでしょう。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、不動産コンサルティングマスター
髙橋 一壽
不動産・建築業界歴20年。アパートの建築請負営業、それに係る土地仲介業務、仕入営業に携わっている。自身でも不動産経営を行っており顧客目線で業務に取り組んでいる。不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!