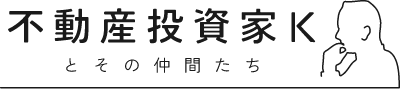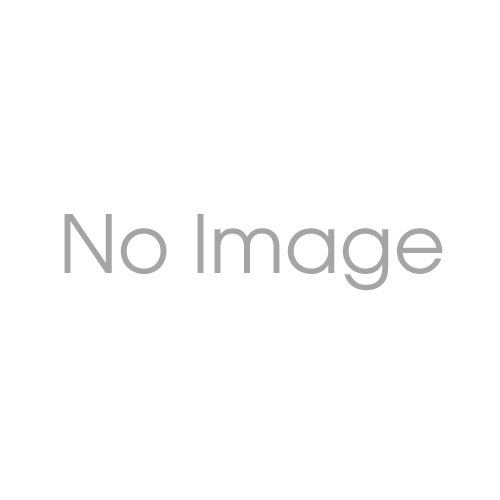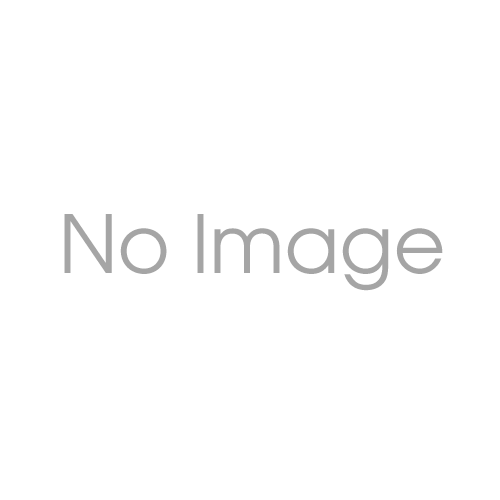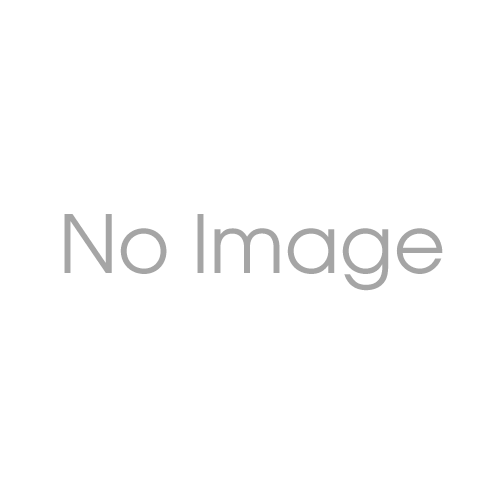
土地を相続した場合、相続税がいくら課せられるのか分からない方もいるでしょう。土地の相続税率は相続する土地の価値によって大きく異なりますが、かなり高額になるケースもあります。しかし、土地活用や特例、控除を使用して節税できることもあります。
本記事では、土地の相続税の計算方法、節税・特例の活用、申告方法をご紹介いたします。

ポイント
- 土地の相続税率は10〜55%
- 土地の相続税は土地活用や特例・控除を使用して節税するのがおすすめ
- 相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日を知ってから10カ月以内
土地相続の税率は10〜55%
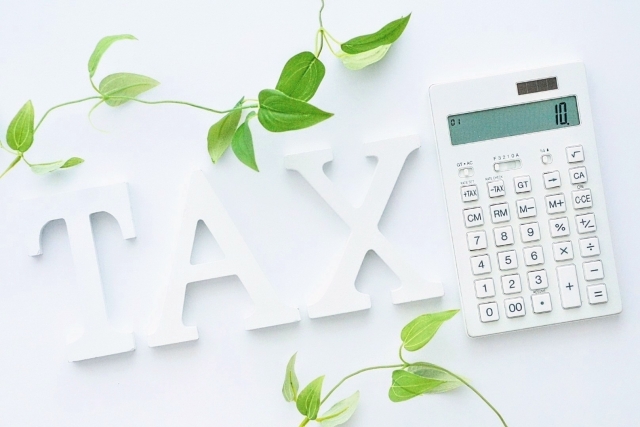
以下は、平成27年1月1日以降の相続税の税率を示しています。
| 課税対象の遺産総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記のように、土地の相続税の税率は10〜55%と決められています。
土地の相続税の税率は累進課税の方式で計算されます。つまり、土地の価値が高ければ高いほど、税率も高くなるということです。
参考:国税庁 No.4155 相続税の税率
そもそも相続税とは
相続税とは被相続人(亡くなった人)の財産を相続した際に課せられる税金です。
課税対象となるのは現金や不動産、株式などの財産総額で、一定額の基礎控除を差し引いた課税価格に応じて税率が適用されます。
税率は、課税価格が高くなるほど段階的に高くなる累進課税制度です。また、税額控除や小規模宅地等の特例を活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
相続税がかかる財産、かからない財産
相続税がかかる主な財産は、以下のとおりです。
相続税がかかる主な財産
- 現金
- 預貯金
- 宝石
- 土地
- 建物
- 有価証券
- 生命保険
- 貸付金
- 特許権
- 著作権
- 死亡退職金
金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてに相続税がかかります。
相続税がかからない主な財産は、以下のとおりです。
相続税がかからない主な財産
- 墓地、墓石、仏壇、仏具
- 相続財産の総額が3,600万円以下
- 被相続人の生命保険のうち「500万円×法定相続人数までの部分」
- 被相続人の退職手当金うち「500万円×法定相続人の数」までの部分
- 相続財産のうち申告期限までに特定の公益法人に寄附したもの
法定相続人には相続を放棄した人も含めます。また、被相続人に養子がいる場合、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含められます。
参考:国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
正味の遺産額を計算する
財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産は、主に以下のようなものがあげられます。
主なプラスの財産
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 預貯金
- 土地
- 建物
- 宝石
- 有価証券
マイナス財産は、主に以下のようなものがあげられます。
主なマイナスの財産
- 借金
- 債務
- 未払金
- 葬儀費用
- 仏具の購入代金
- 特定の公益団体に寄附した財産
マイナス財産は、相続税の計算において非課税の財産としてプラス財産から差し引くことが可能です。プラス財産からマイナス財産を差し引いた総額を正味の遺産額といいます。
基礎控除額を差し引く
まず相続人全員の課税金額の合計を計算します。続いて、基礎控除額を以下の計算式で求めます。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
たとえば、法定相続人が被相続人の配偶者と子供3人の場合の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円になります。
次に相続人全員の課税総額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
相続人全員の課税総額−基礎控除額=課税遺産総額
相続税率をかける
課税遺産総額を算出したら、まず相続人全員がそれぞれ法定相続分通りに取得したものとしてそれぞれの取得金額を計算します。
課税遺産総額×法定相続人1人当たりの法定相続分=法定相続人の1人当たりの取得金額
相続人の1人当たりの取得金額を算出したら、相続税率をかけて算出税額を計算します。
相続人の1人当たりの取得金額×相続税率=算出税額
法定相続人の1人当たりの算出税額が相続税の総額です。
法定相続人の1人当たりの算出税額の合計=相続税の総額
相続人1人当たりの相続税を算出する場合は、以下の計算式で求められます。
相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計=相続人1人当たりの相続税
ただし、相続人が被相続人の配偶者や両親、子供以外の場合と相続時精算課税分の贈与税相当額がある場合は例外です。
相続人が被相続人の親族でない場合は、以下の計算式を用います。
各相続人の税額+相続税額の2割加算−各種税額控除=相続人1人当たりの相続税
また、相続時精算課税分の贈与税相当額がある場合は、以下の計算式で算出します。
各相続人の控除後の税額−相続時精算課税分の贈与税相当額=相続人1人当たりの税額
遺産が基礎控除額を超えない場合は申告不要
遺産の総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税がかからないため、申告する必要はありません。
たとえば、法定相続人が被相続人の配偶者と子供1人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円になります。
そのため、遺産の総額が4,200万円以下であれば、相続税はかからないため申告は不要です。
土地のみにかかる相続税はない
相続税の金額は、土地を含めた財産全体の総額を基準にして算出するため、土地のみにかかる相続税はありません。
土地のみの相続税を計算したい場合は、土地の相続税評価額 ÷ 遺産総額で求められます。
たとえば、土地の相続税評価額が6,000万円、遺産総額が7,000万円の場合は、6,000万円÷7,000万円で85%が土地のみの相続税の額になります。
土地の相続税評価額の計算方法

土地は相続時の時価に対して税金が課せられるため、土地の時価を適切に評価する必要があります。
しかし、専門家以外が土地の時価を算出するのは難しいため、相続税法においては「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかの方法で算出するように決まっています。
土地の相続税評価額を算出する方法として、2つの方式について解説します。
路線価方式
国税庁により路線価が決められている地域では、「路線価方式」を使って土地の評価額を算出します。該当する地域は、主に都市部や住宅地のほとんどです。
路線価とは、路線に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格で、千円単位で表示されています。
路線価方式を使用した土地の評価額の算出方法は、以下のとおりです。
(正面路線価)×(奥行価額補正率)×(面積)=土地の評価額
相続する土地の形状に応じて補正率で補正して計算します。
参考:国税庁 財産評価基準書
あわせて読みたい
倍率方式
路線価が定められていない地域では、「倍率方式」を使って土地の評価求めます。
倍率方式を使用した土地の評価額の算出方法は、下のとおりです。
相続する土地の固定資産税評価額×決まった倍率=土地の評価額
倍率は国税庁によって定められていますが、都道府県によって異なります。
参考:国税庁 評価倍率表
土地を現金化できず、納税資金を用意できない
土地の相続で高額な相続税が発生すると、納税資金を確保できないリスクがあります。特に地価が高い都市部や商業地の土地は評価額が高くなりやすく、納税額も大幅に増えることがあるでしょう。
相続税は原則として現金での一括納付が求められるため、資金不足の場合には不動産の一部を急いで売却しなければならないこともあります。しかし、土地は現金化に時間がかかり、急ぐ場合は本来の市場価格より低く売却せざるを得ない可能性もあるでしょう。
一括納付が難しい場合は、「延納」が認められています。相続税額が10万円を超え、現金での納付が困難な事情がある場合に、申請により分割払いができる制度です。ただし、担保の提供や利息の負担が必要です。
また、土地を担保に金融機関から借入する方法もあります。延納と比較してどちらが有利か金利面を確認し、適した方法を選ぶことになるでしょう。
参考:国税庁 No.4211 相続税の延納
納税資金は相続前から準備する
土地の相続が見込まれる場合、納税資金の確保は相続前からの準備が必要です。生命保険の活用や事前の売却計画など、あらかじめ納税資金を用意する方法を検討しておきましょう。
また、金融機関では「納税準備預金」という専用口座を開設できるため、これを活用する方法もあります。普通預金より利率が高く、利息は非課税で、相続税を含む各種税金の納付に利用可能です。相続前に口座を整えておくことで、相続発生後も慌てずに対応できるでしょう。
土地の共有によってトラブルが発生する
相続人が複数いる場合、土地は簡単に分割できないため、共有状態になることが少なくありません。
不動産の共有には、以下のようなリスクを伴います。
- 売却・活用には共有者全員の同意が必要
- 管理方針や修繕費負担で対立が生じやすい
- 一部の相続人が持分を第三者に売却する可能性がある
共有不動産を売却・活用する際、1人でも反対すれば手続きが進まず、資産の有効活用が難しくなります。
また、建物の修繕や固定資産税の支払いなど、維持管理には費用が発生します。負担割合や管理方針を巡って意見が食い違い、相続人同士の対立につながることもあるでしょう。
相続人の1人が自分の持分を第三者に売却すれば、見知らぬ人が共有者となり、さらに話し合いが難航するケースもあります。
あわせて読みたい
共有状態を避けてスムーズな承継を確保する
共有状態によるトラブルを避けるためには、遺言書の作成や事前の分割協議で、できるだけ単独所有にしておくと、承継がスムーズになります。
単独所有にする方法として、「換価分割」や「代償分割」があげられます。
換価分割は土地を売却して現金化し、分ける方法で、代償分割は1人が不動産を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
これらを活用すれば資産を円滑に分配でき、トラブルの予防につながります。
節税対策の遅れにより高額の課税が発生する
土地の相続税には、特例や控除、生前贈与など税負担を軽減できる制度があります。しかし、これらの制度は相続が発生する前に対策しておかなければ利用できないものもあり、事前に計画を立てておかないと相続発生時に大きな税額の差が生じる可能性があります。
相続前の節税対策を怠れば、結果として高額な相続税を支払わざるを得ないケースもあるため、早めの準備が重要です。
相続発生前の対策を優先的に行う
生前贈与や土地の有効活用など、相続発生前にしか対応できない節税策は多く存在します。これらは制度の適用条件や手続きのタイミングを誤ると効果が得られないため、早めに税理士や不動産の専門家へ相談することが必要です。
専門家の助言を受けながら複数の選択肢を比較検討すれば、将来の相続税負担を軽減できるだけでなく、遺産分割のトラブル防止にもつながります。
地価の上昇により評価額が増加する
土地の相続では、地価の変動によって評価額が上下し、その結果として相続税の負担が重くなるリスクがあります。特に地価が上昇した場合には、想定していた以上に評価額が膨らみ、相続税額も増加する可能性もあるでしょう。
地価は景気動向や周辺地域の再開発計画、公共交通機関や道路整備などのインフラの影響を受けやすく、短期間でも大きく変動することがあります。
そのため、数年前に立てた試算と実際の相続時点での評価額に大きな差が生じ、想定外の税負担につながるケースも少なくありません。
地価動向を常にチェックする
土地を含む資産を相続する見込みがある場合は、定期的に公示地価や路線価の推移をチェックし、税負担を見据えた資金計画や節税対策を検討することが重要です。
相続時に慌てないためにも、必要に応じて税理士や不動産鑑定士などの専門家へ相談し、適切な節税対策を講じることが将来のリスク回避につながります。
土地の相続税評価額を抑える方法

相続する財産によっては、相続税が高額になります。土地の相続税評価額を抑える方法として、アパート経営や土地活用の専門家に相談する方法があります。
少しでも相続税を抑えられるように工夫しましょう。
アパート経営により評価額を抑える
土地を相続した場合、相続税を抑える方法としてアパートを経営する方法があげられます。アパート経営を行うと、財産評価額が低くなり、結果的に相続税の節税につながります。
相続した土地に賃貸物件を建て、不動産として他人に貸すことになり、自分では自由に使えないという権利の制約が生じ、土地の評価額が下がるのです。また、アパート建築でローンの借入れがあれば、マイナス財産として遺産総額から差し引くことができます。
また、直接相続税を減らすわけではありませんが、アパート経営で得た家賃収入を相続税の支払いに回せます。
生前贈与を活用して段階的に承継する
土地の相続税評価額を抑える方法として、生前贈与の活用があげられます。生前贈与とは、存命中に財産を他者に贈与することです。相続税は相続時の課税遺産総額に対して課税されるため、相続時の財産を減らすことで税負担を軽減できる可能性があります。
相続発生前に暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)を活用し、評価額の高い土地を複数回に分けて贈与しておくことで、相続時の税負担を抑えることが可能です。
ただし、被相続人が亡くなる7年以内に行った贈与は相続財産に持ち戻され課税対象となるため、早めの計画が必要です。
参考:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
あわせて読みたい
法人化して土地利用を最適化する
法人化して土地利用を最適化することで、土地の相続税評価額を抑えることも可能です。法人へ不動産を移転すると、相続時には土地そのものではなく法人株式の評価額が課税対象となり、評価方法の違いから結果的に税負担が抑えられるケースもあります。
ただし、株式評価にも法人が保有する資産や収益が反映されるため、必ずしも税負担が軽減されるとは限りません。不動産移転には登録免許税や不動産取得税などのコストも伴うため、専門家に相談し、長期的な資産管理の観点から総合的に検討することが必要です。
あわせて読みたい
土地活用の専門家に相談する
土地の相続税評価額を抑えるには、土地活用の専門家に相談するのがおすすめです。以下のような相談先があげられます。
- ファイナンシャル・プランナー
- 不動産会社
- 金融機関
- 弁護士、司法書士
- 税理士
ファイナンシャルプランナーは、お金に関するプロです。さまざまな土地活用の初期費用や予想される利益について相談に乗ってくれるでしょう。ファイナンシャルプランナーは、金融機関やハウスメーカーにも在籍している可能性はありますが、中立的な立場からのアドバイスであるかを見極めることが必要です。
不動産会社は、土地や建物の専門家です。アパート経営など自分で思いつくような土地活用だけでなく、さまざまな土地活用の方法を知っています。また、相続トラブルについてコンサルティングをしてくれる不動産会社もあります。
一般的にアパートなどの建築費はローンで賄うことが多いため、金融機関に相談する必要があります。不動産会社から提携している金融機関を紹介された場合は、有利な金利でローンを組める可能性があるため、不動産会社に相談に行った際は提携の金融機関の紹介についても確認しましょう。
相続税の節税のための土地活用の法的な手続きが難しい場合は、トラブルに備えて弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
税理士は、税金のプロです。土地活用は、毎年どれくらいの税金がかかるのかを考慮した上で行う必要があります。金融機関や不動産会社、ファイナンシャルプランナーは節税に関するアドバイスはできないので、税理士に専門的なアドバイスを依頼しましょう。
同じ内容で見積もりをしても、相談先によって提示する土地活用法や金額が異なるため、複数の相談先に見積もりを依頼するのがおすすめです。
土地の相続税を軽減する特例
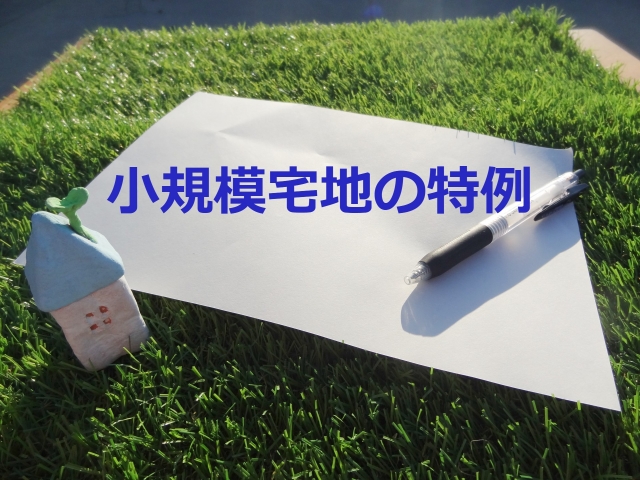
土地の相続税は、小規模宅地等の特例を利用することで、負担を軽減することができます。
一定の条件を満たしていれば、最大80%が減額される特例です。
ここでは、特例の内容について解説します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生活をともにする親族の事業用または居住用の土地に対し、区分ごとに50〜80%まで評価額を減額できる制度です。
ただし、農地や採草牧草地は対象外です。
土地は大きく分けると、以下の4種類に区分されます。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 特定同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
それぞれの特例について解説します。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等の特例とは、小規模宅地等の特例の中でもよくされている制度で、被相続人が住んでいた土地を相続する場合に利用されます。
特定居住用宅地等の特例の限度面積や減額される割合は、以下のとおりです。
| 土地の区分 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
たとえば、価額が5000万円の300㎡の土地を1人で相続する場合は、以下の計算式で減額できる金額が求められます。
5,000万円×80%=4,000万円
また、5000万円の330㎡を超える400㎡の土地を1人で相続する場合は、以下の計算式で減額できる金額が求められます。
5,000万円×330㎡/400㎡×80%=3,300万円
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等の特例とは、貸付事業以外の事業用の宅地を相続する場合に使用する制度です。
特定事業用宅地等の特例の限度面積や減額される割合は、以下のとおりです。
| 土地の区分 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定事業用宅地等の特例を使用するには、以下の条件があります。
被相続人が事業に使用していた宅地を相続する場合は、以下の要件を満たさなければなりません。
- その宅地で被相続人が営んでいた事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、申告期限までにその事業を営むこと
- その宅地を相続税の申告期限まで所持していること
被相続人と生計をともにしていた被相続人の親族が事業に使用していた宅地を相続する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続開始の超前から相続税の申告期限までその宅地で事業を営むこと
- その宅地の相続税の申告期限まで所持していること
どちらか一方の要件ではなく、それぞれに掲げる要件をどちらも満たしていなければなりません。
要件を満たしていれば、たとえば、被相続人が事業を営んでいた価額が5,000万円の300㎡の土地を1人で相続する場合は、以下の計算式で減額できる金額が求められます。
5,000万円×80%=4,000万円
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等の特例は、相続する宅地が一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業用に使われていた場合に使用します。
特定同族会社事業用宅地等の特例の限度面積や減額される割合は、以下のとおりです。
| 土地の区分 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等の特例を使用するには、以下の条件があります。
- 相続税の申告期限にその法人の役員であること
- その宅地を相続税の期限まで所持していること
たとえば、一定の法人に貸し付けされており、申告期限時点で相続人が法人となる価額が5,000万円の300㎡の土地を1人で相続する場合は、以下の計算式で減額できる金額が求められます。
5,000万円×80%=4,000万円
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等の特例とは、一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業用または貸付事業用宅地、被相続人等の貸付事業用の宅地に使用する制度です。
貸付事業用宅地等の特例の限度面積や減額される割合は、以下のとおりです。
| 土地の区分 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
貸付事業用宅地等の特例を使用するには、以下の条件があります。
被相続人の貸付事業用に使用されていた宅地は、以下の条件を満たしていなければなりません。
- その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで貸付事業を営むこと
- その宅地を相続税の期限まで所持していること
被相続人と生計をともにしていた相続人の親族の貸付事業用に使用されていた宅地は、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等に係る貸付事業を営むこと
- その宅地を相続税の期限まで所持していること
どちらか一方の要件ではなく、それぞれに掲げる要件をどちらも満たしていなければなりません。
たとえば、被相続人が貸付事業を行っていた価額が5,000万円の200㎡の土地を1人で相続する場合は、以下の計算式で減額できる金額が求められます。
5,000万円×50%=2,000万円
土地の相続税を軽減する控除
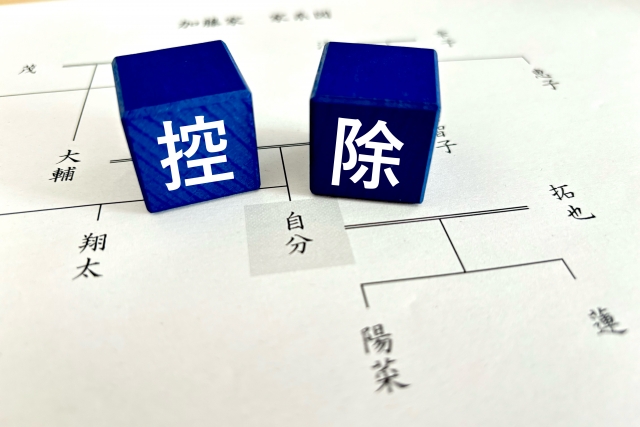
土地の相続では、税額控除により負担を減らすことも可能です。土地相続に適用できる控除として、代表的なものに以下があげられます。
- 贈与税額控除
- 障害者の税額控除
- 未成年者の税額控除
- 相次相続控除
それぞれの内容を詳しく解説します。
贈与税額控除
相続人が被相続人から生前に贈与された財産のうち、亡くなった日から3年以内に贈与された財産は控除が受けられます。
3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象となるため、贈与税と相続税の二重課税を防ぐことを目的としています。
ただし、令和6年1月1日以降は、税制改定により3年以内ではなく7年以内に贈与された財産へと、範囲が延長されるためご注意ください。
控除される税額は、贈与を受けた際に支払った贈与税から加算税や延滞税、利子税を除外した金額です。
また、以下の場合は被相続人から贈与された財産であっても相続税の対象に加算する必要はありません。
- 贈与税の配偶者控除の特例を受けているまたは受ける予定の金額
- 直系尊属から贈与された住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた贈与額
- 直系尊属から一括贈与された教育資金のうち、非課税の適用を受けた贈与額
- 直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた贈与額
ただし、上記の場合でも贈与者が亡くなった際の管理残額については課税される場合があります。
参考:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
配偶者の税額控除
被相続人の配偶者は、最大1億6,000万円または配偶者の法定相続分の相続税の多い方の金額まで相続税を軽減できます。
配偶者にはなるべく相続税がかからないようにしようという目的で作られた制度です。ただし、内縁の配偶者は対象ではありません。
また、配偶者が最大限の財産を相続した場合、子供に課せられる相続税が多くなる恐れがあるため、気をつけましょう。
参考:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
障害者の税額控除
相続人が満85歳未満で障害がある場合は、障害者の税額控除を受けられます。
控除を受けられる金額は、一般障害者であるか、特別障害者であるかにより異なり、一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円です。
たとえば、81歳の一般障害者の場合は、以下の計算式で控除額が求められます。
(85歳−81歳)×10万円=40万円
控除額が障害者本人の相続税額を上回る場合は、上回った金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
参考:国税庁 No.4167 障害者の税額控除
未成年者の税額控除
相続人が満18歳未満の場合は、未成年者の税額控除を受けられます。控除を受けられる金額は、1年につき10万円です。
たとえば、相続人が14歳9ヶ月の場合は、以下の計算式で控除額が求められます。
(18歳−14歳)×10万円=40万円
なお、令和4年3月31日以前の相続または遺贈については満20歳未満が対象です。
未成年者控除額が未成年者本人の相続税額を上回る場合は、上回った金額を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
参考:国税庁 No.4164 未成年者の税額控除
相次相続控除
10年以内に相次いで相続が発生した方は、相次相続控除が受けられます。
短期間に相続が重なると、一つの財産に二重課税が課せられるため、前回の相続で納めていた相続税のうち1年につき10%割合で減額した金額を今回の相続で課せられる相続税額から控除します。
たとえば、10年以内に2回相続が発生した場合の2回目の相続における控除額は、以下の計算式で求められます。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=相次相続控除額
A〜Eの内容は以下のとおりです。
- A:1回目の相続で納めた相続税
- B:1回目の相続で得た純資産価額
- C:2回目の相続で得たすべての相続人の純資産価額の合計
- D:2回目の相続で得た純資産価額
- E:1回目の相続から2回目の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
前回の相続から期間が短ければ短いほど、控除額は大きくなります。
参考:国税庁 No.4168 相次相続控除
相続税の申告手順
相続税の申告書は、被相続人が亡くなったときの住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署長ではないため、注意しましょう。
相続税の申告書は、自身で作成することも可能ですが、手続きが複雑である上に、申告内容が間違っていると、税負担が重くなるペナルティを課せられることがあります。
そのため、相続税の申告は知識や経験が豊富な税理士に依頼し、サポートしてもらうのがおすすめです。
相続税の申告期限
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目の日までにしなければなりません。
被相続人の亡くなった日でなく、亡くなったことを知った日であることに注意しましょう。
申告期限の日が土曜日や日曜日、祝日などの休日に当たる場合は、本来の申告期限日の翌日に申告期限が変更されます。
申告期限に遅れて納税した場合は、延滞税や無申告加算税がかかるため、期限は必ず守りましょう。
参考:国税庁 相続税の申告のしかた(令和5年分用)
登記の名義変更が義務化されている
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。相続で不動産を取得した場合、相続人は「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。そのため、早めに名義変更を行い、手続きを済ませておくことが大切です。
なお、正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
あわせて読みたい
利用や売却に制限が生じる可能性がある
相続する土地によっては、利用や売却に制限がかかる場合があるため注意してください。たとえば、農地は転用許可が必要であり、市街化調整区域は建築制限があるため、相続後の活用方法が限られることがあります。さらに、売却の際、行政の許可が必要になることもあるでしょう。
これらの制限を把握せずに手続きを進めると、計画通りの利用や売却が難しくなる可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ

土地の相続税率は10〜55%で、土地の価値が高ければ高いほど税率も高くなります。そのため、土地によっては非常に高額な相続税が課せられるでしょう。
相続税を少しでも抑えるためには、アパートを経営するなどの土地活用をしたり、小規模宅地等の特特、贈与税額控除、障害者の税額控除、未成年者の税額控除、相次相続控除などの特例や控除を用いたりして工夫しましょう。
また、相続税には被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内という申告期限が設けられています。期限を過ぎると、ペナルティが課せられる場合があるため、早めに対応しましょう。

監修者
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
中川 祐一
現在、不動産会社で建築請負営業と土地・収益物件の仕入れを中心に担当している。これまで約20年間培ってきた、現場に密着した営業経験と建築知識、不動産知識を活かして業務に携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!