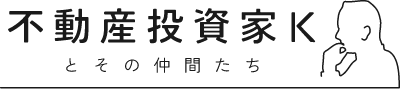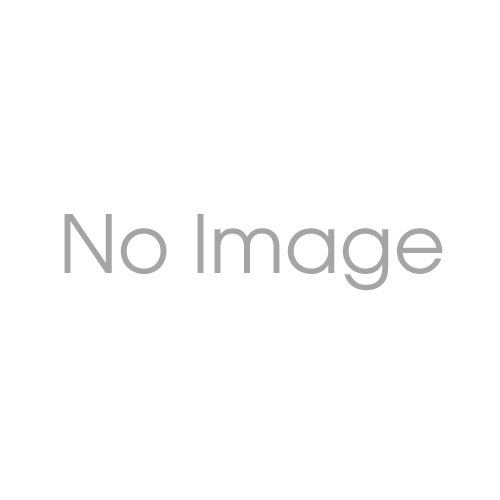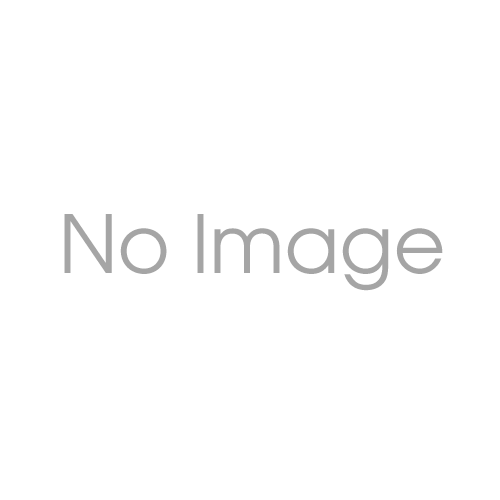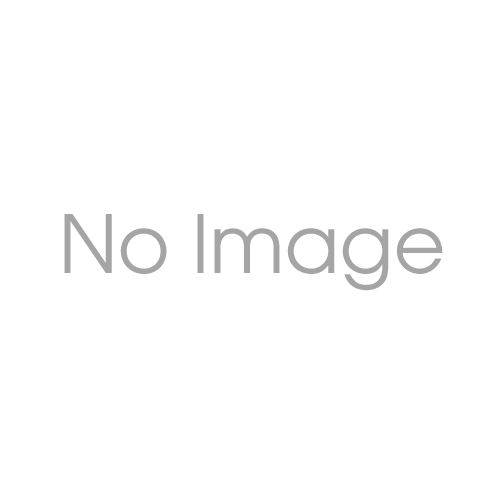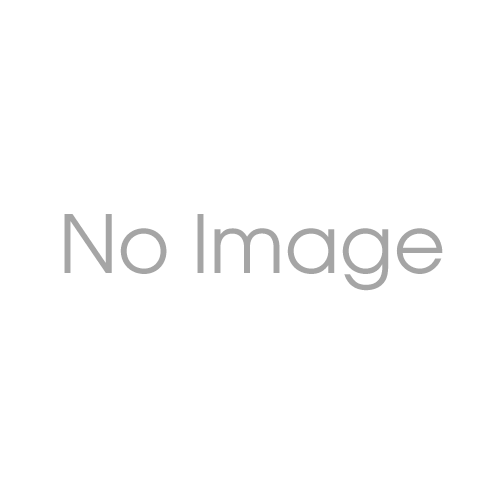資産承継は、財産を次世代に安全かつ計画的に引き継ぐための手段です。承継対象資産の整理や承継者の明確化を行い、遺言書や信託を活用することで、相続時の手続きや税負担を軽減できます。
本記事では、資産承継のステップや円滑に進めるためのポイントなどを詳しく解説します。

ポイント
- 資産承継とは、保有する資産を次世代や後継者へ引き継ぐこと
- 資産承継を円滑に進めるためには、計画と手順に沿った準備が大切
- 円満に資産承継するには資産の見直しや生前贈与の活用などのポイントがある
資産承継とは?相続との違い

資産承継とは、個人や企業が保有する資産を次世代や後継者へ引き継ぐことです。資産を引き継ぐという点で相続と似ていますが、意味は異なります。
相続は、法律に基づいて被相続人の死亡によって財産や権利義務が引き継がれることを指します。誰がどの財産を受け取るかは、遺言や民法の定める法定相続によって決まります。
一方、資産承継はより広い概念で、相続はもちろん生前贈与や事業承継などを通じて計画的に資産を次世代へ移転する取り組みを指します。相続は被相続人が亡くなった時点で法定相続人に権利が発生する仕組みであり、資産承継は生前に資産の引き継ぎを計画する要素が強いことが特徴です。
特に事業を営んでいたり不動産を保有していたりする場合には、相続発生後の混乱を避け、税負担を抑えながらスムーズに資産を移行させるために、資産承継の視点が重要になるでしょう。
資産承継のためのステップ
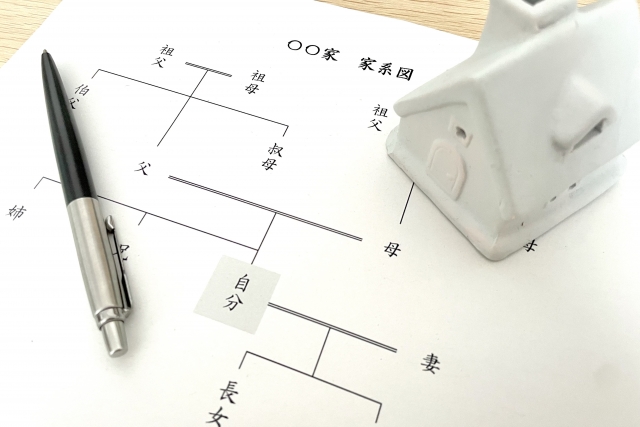
資産承継をスムーズに行うためには、生前からの計画的な準備が欠かせません。事前に資産の把握や承継者の確定、分割方法の検討などを行っておくことで、相続税の負担を軽減できるだけでなく、家族間のトラブルも未然に防止できます。
ここでは、資産承継を進める際に押さえておきたい基本ステップを解説します。
承継財産を把握する
資産承継を進めるうえで最初に行うことは、承継対象となる財産を正確に把握することです。現金や預貯金、不動産、株式などの有価証券に加え、事業用資産や負債も含めて整理する必要があります。
財産の全体像を正しく把握できていないと、思わぬ相続税負担や分配の偏りが生じる可能性があります。そのため、すべての資産を網羅的にリスト化し、評価額や権利関係も明確にしておくことが大切です。
こうした準備により、相続税対策や分配のシミュレーションが可能となり、後々の争いを防ぐ基盤が整います。
承継者を確定する
承継者を確定するステップでは、家族構成や事業の将来性を踏まえて、誰がどの財産や事業を引き継ぐかを明確にすることが重要です。
特に事業承継の場合は、後継者の経営能力や意欲を考慮し、早い段階で候補者と十分に話し合う必要があります。また、複数の承継者がいる場合には、役割分担や権限を整理し、遺言や契約書を通じて法的に明確化しておくことが不可欠です。
承継後の財務管理や税負担のシミュレーションも事前に行い、必要に応じて専門家の助言を得ることで、トラブルや負担の偏りを防ぎ、より円滑な承継を実現できるでしょう。
分割方法を決める
分割方法を決めるステップでは、承継財産をどのように分配するかを具体的に検討します。
相続が発生して遺言書がない場合、遺産の分割方法は相続人同士で話し合って決めることになります。意見がまとまらなければ、民法で定められた法定相続分を基に裁判所が判断するという流れです。
「公平に分けたい」と考えても、具体的な基準を決めるのは容易ではありません。そのため、自分の希望や意向を踏まえた分割方法を事前に定めておくことが、トラブルを避けて円滑に資産を承継するポイントです。
相続人の人数や財産の種類(不動産など)によって公平な分割が難しい場合もあるため、評価額をもとに現金で調整する方法や、共有名義にする方法、あるいは特定の承継者に集約して他の承継者には代償金を支払う方法など、適切な分割方法を検討する必要があるでしょう。
承継財産の性質に応じた方法を選ぶことで、家族間のトラブルを防ぎ、円滑な承継が可能となります。
遺言書を作成する
資産承継で「誰に、何を残したいか」という想いを形にするためには、遺言書の作成を検討しましょう。遺言書に具体的な分割方法を記載しておけば、希望通りの承継を実現できます。
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式があり、自身に合った形式を選びます。公正証書遺言は法的効力が強く、内容が無効となるリスクを抑えたい場合に有効です。さらに、遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きをスムーズに進められます。
法定相続人以外の人物や法人・団体へ財産を遺贈したい場合でも、遺言書に明記することで実現可能です。
納税資金を準備する
相続税は原則として相続開始から10カ月以内に納める必要があるため、承継する資産が高額な場合は納税資金の準備が必要です。
まず、相続税額のおおよその試算を行い、現金や預貯金で対応できるか確認します。不足が見込まれる場合には、生命保険の活用や不動産の一部売却、計画的な生前贈与などで資金を確保する方法を検討しましょう。
特に不動産が多い場合は流動性が低いため、早めに対策を講じることが重要です。納税資金を事前に準備することで、円滑な承継と相続人の負担軽減につながります。
円満な資産承継のためのポイント

資産承継は、単に財産を次世代へ引き継ぐだけでなく、家族間のトラブルを防ぎながら円滑に資産を移行させることが重要です。
早めの準備と生前贈与・信託の活用、適切な遺言書の準備などにより、相続税や手続きの負担を軽減しながら、安心して承継を進めることができます。
ここでは、円満に資産承継するためのポイントを解説します。
資産の見直しを検討する
資産承継を円満に進めるためには、保有資産の見直しが必要です。相続税は累進課税のため、相続財産が増えるほど税負担も大きくなります。何も対策をせず資産をそのまま残すと、多額の相続税が発生し、相続人の負担が増える可能性があります。
そのため、手持ちの資産を「相続に回すもの」「生前に贈与するもの」「売却して資金化し納税資金に充てるもの」の3つに分類し、計画的に管理・活用することが重要です。定期的に見直しを行うことで、税負担を抑えつつ、円満な資産承継を実現しやすくなるでしょう。
生前贈与や信託を利用する
保有資産が多い場合は、生前贈与や信託の活用が有効です。
生前贈与には、暦年課税で年間110万円までの贈与が非課税となる制度や、相続時精算課税制度で累計2,500万円までの贈与について、贈与時には贈与税がかからず、相続発生時に精算される制度などがあります。
これらを活用して相続発生前に財産を次世代へ移すことで、相続税負担の軽減が可能です。
信託とは、委託者が自分の財産を信頼できる人に託し、財産の管理や運用を任せる制度です。信託を利用すると、将来的な承継方法や受益者を指定できるため、承継の計画性や柔軟性が高まります。
いずれの方法も、専門家と相談して適切に設計するとよいでしょう。
遺言書を適切に準備する
円満な資産承継のためには、遺言書を適切に準備することが欠かせません。誰にどの財産を引き継ぐかを明確に示すことで、相続人同士の争いやトラブルを防げます。
作成にあたっては、財産の種類や分割方法、相続人同士の公平性を考慮し、将来のトラブルを防ぐ内容にすることが大切です。
加えて、遺言書の保管方法や更新のタイミングにも注意することで、法的効力を維持しつつ、変更が必要な場合にも柔軟に対応できます。専門家の助言を受けながら準備することで、安全かつ確実な承継が可能です。
事前に家族と共有する
資産承継を円滑に進めるためには、遺言書や承継計画の内容を事前に家族と共有しておくことが重要です。誰がどの資産を引き継ぐのか、分割方法や納税資金の準備状況などを話し合うことで、誤解やトラブルを未然に防げます。
また、家族の理解を得ておくことで、相続開始後の手続きや資産の受け渡しもスムーズに進み、円満に承継を行えるでしょう。
さらに、弁護士や税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と連携し、共有のタイミングや方法を検討することで、計画の実効性が高まります。
定期的な見直しを行う
資産承継計画は、一度作っただけでは十分とはいえません。家族構成の変化や資産の増減、税制改正、さらには事業環境の変化など、さまざまな要因に応じて定期的に見直すことが大切です。
計画を更新することで、承継方法や分割内容が現状に即したものとなり、相続時のトラブルや予期せぬ税負担の増大を防ぐことができます。
また、遺言書や信託の内容も最新の状況に合わせて修正しておけば、円滑な資産承継を実現できるでしょう。
あわせて読みたい
資産承継の相談先

円滑な資産承継を進めるためには、専門家への相談が欠かせません。まず税務面では、相続税や贈与税の計算、納税資金の準備などに対応できる税理士が重要な相談相手となります。
税務のほか、遺言書や信託の作成、財産分割の法的手続きについては弁護士や司法書士への相談が有効です。
特に複雑な不動産や事業承継の場合は、資産の種類や承継方法に応じた複数の専門家からの適切な助言が求められます。
また、金融機関や信託会社では、資産管理や信託を活用した資産引き継ぎのサポートを受けることも可能です。
複数の専門家と連携しながら相談することで、税負担や相続に関するトラブルを最小限に抑え、計画的かつ安心して資産承継を進めることができます。
早めに相談を始めることで、家族間の合意形成や納税資金の準備もスムーズに行えるでしょう。
まとめ

資産承継とは、財産を次世代に円滑かつ計画的に引き継ぐための重要なプロセスです。早めに承継対象となる資産を整理し、承継者や分割方法を明確にしておくことで、相続時のトラブルや思わぬ税負担を軽減できます。
さらに、遺言書や信託、生前贈与といった制度を活用し、必要に応じて専門家に相談することで、納税資金の確保もよりスムーズに行えます。定期的な計画の見直しや家族との情報共有を心がけることで、安心かつ円満な資産承継を実現できるでしょう。

監修者
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
中川 祐一
現在、不動産会社で建築請負営業と土地・収益物件の仕入れを中心に担当している。これまで約20年間培ってきた、現場に密着した営業経験と建築知識、不動産知識を活かして業務に携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!