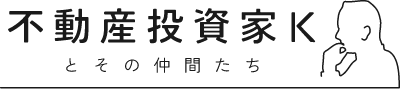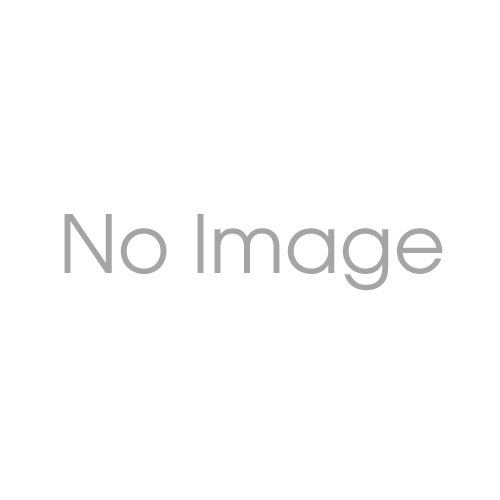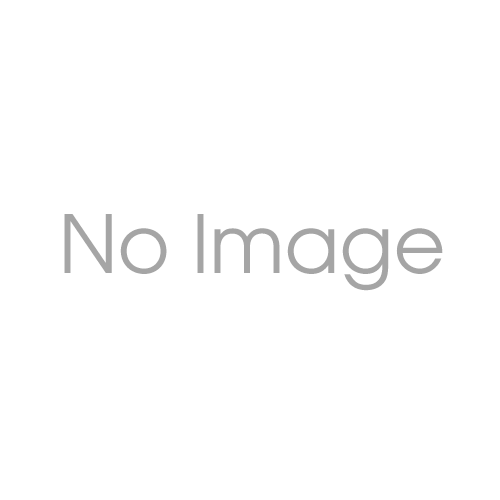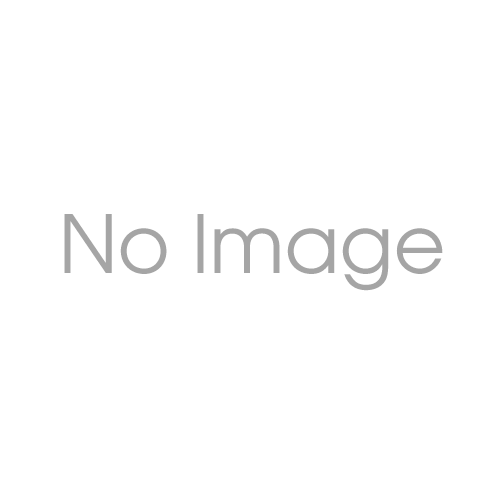
賃貸経営において入居率と稼働率は、どちらも空室状況や収益性を測るために重要な指標です。入居率はある時点にどれだけ部屋が埋まっているかを示すのに対し、稼働率は一定期間のうち実際に稼働していた割合を表すといった違いがあります。
本記事では、入居率と稼働率の違いやそれぞれが果たす役割、活用場面などをわかりやすく解説します。
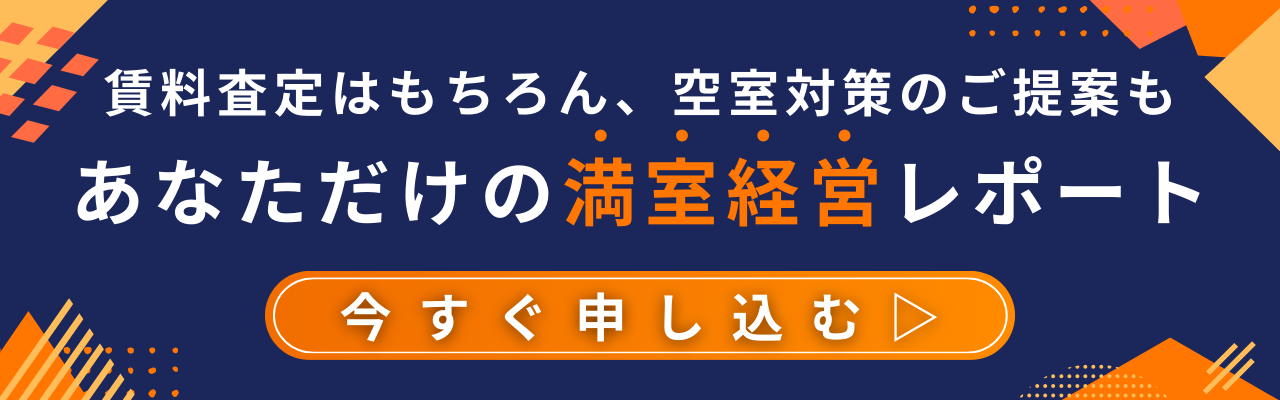
ポイント
- 入居率とはある時点の入居状況、稼働率は一定期間の入居状況を示す指標である
- 入居率と稼働率は、賃貸物件の現状把握や収益安定性の指標であり、経営判断に活用できる
- 入居率と稼働率は、計算方法や活用する場面が異なる
- 指標の活用には、入居率と稼働率のそれぞれの計算方法の違いや特性の理解が重要である
入居率とは?

入居率とは、賃貸物件で入居者がいる部屋の割合のことです。不動産投資では、収益性や人気度を把握するうえで重要な指標となります。
ここでは、入居率の計算方法や収益を確保できる目安を解説します。
入居率の計算方法
入居率は、以下の計算式で求めます。
入居率=入居戸数÷総戸数×100
たとえば、総戸数10戸で現在の入居が9戸の場合、入居率は以下のように計算できます。
9戸÷10戸×100=90%
入居率が高いほど家賃収入が増え、物件の収益性も向上します。一方、入居率が低い場合は収益の減少やローン返済負担の増加などのリスクが高まるでしょう。そのため、入居率は不動産経営の成功に直結する重要な要素です。
部屋数が多い場合は、1戸の空室が出ても収益にすぐに大きな影響はありませんが、所有部屋数が少ない場合1戸の空室でも収益に大きな影響があるため、入居率の管理が大切です。
入居率の目安
不動産投資における入居率の目安は、95%以上とされています。ただし、これはあくまで目安であり、立地や物件の種類、投資戦略によって適正値は変わります。
一般的には入居率が70〜80%の場合は経営状況がやや厳しいと判断され、50%以下になると収益確保が難しく、経営難に陥る状況といえるでしょう。
投資の安定性を保つためには、物件の特性や市場動向を踏まえ、適切な入居率を維持することが大切です。
稼働率の計算方法
稼働率は、以下の計算式で求めます。
稼働率=総入居日数 ÷(総戸数×総所有日数)× 100
たとえば、総戸数10戸で1年(365日)の稼働率を計算するケースで考えてみましょう。2戸で解約があり、それぞれ空室期間が70日間あった場合の稼働率は、以下のように計算できます。
(8戸×365日+2戸×(365日-70日))÷(10戸×365日)×100
=(2920日+590日)÷3650日×100
=3510日÷3650日×100=96.1%
稼働率は期間における入居割合を示す数値であり、数値が高いほど、継続的な収益を得られる運用ができていることを表します。収益の実態に即していると言え、不動産経営における「収益の安定性」を判断するうえで欠かせません。
空室が長期化すれば稼働率は低下し、収益減少が数値として明確に表れるため、物件やエリアが抱える空室リスクを客観的に把握する手がかりになります。
計算する期間が異なる
入居率と稼働率は、基準となる期間が異なります。入居率は、ある時点で何戸が埋まっているかを示す「瞬間的な指標」であり、現状の入居状況を把握する際に役立ちます。
一方、稼働率は年間や数カ月間、一定の期間を通じて部屋が実際に利用されていた割合を表す「期間的な指標」です。入退去の動きや空室期間の長さも反映されるため、より実態に即した経営状況を示すことができます。
入居率の場合
入居率は「何戸中何戸が埋まっているか」というシンプルな指標であり、現時点での人気度や入居状況の可視化ができます。
主に次のような場面で指標になります。
- オーナーが「現在どのくらい部屋が埋まっているか」を把握したいとき
- 投資家が物件を購入検討するときに、人気度や需要を確認したい場合
ただし、「満室=高収益」とは限らず、大幅な値下げをして入居率を維持している場合や、短期間での入居者の入れ替わりが多い場合、収益は落ちている可能性があります。
一方、入居率が低くても、長期入居者が多ければ稼働率は高くなる可能性があります。
稼働率の場合
稼働率は、一定期間の実際の稼働実績や収益性を把握するために使われます。長期的な収益力や経営安定性を確認する際に有効です。
主に次のような場面で指標となります。
- オーナーが年間収支を確認するとき
- 不動産投資家が利回りやキャッシュフローを計算するとき
- 金融機関が融資審査で「安定した収益があるか」を確認するとき
- 管理会社が運営状況をレポートする場合
入居率は宣伝や集客にも使われることが多く、「現状を示すシンプルな数字」であるのに対し、稼働率はオーナーや投資家 にとって実態を把握し、投資判断するための「実態を反映した数字」といえるでしょう。
入居率・稼働率を活用する場面と注意点

入居率と稼働率は、活用場面が異なります。賃貸経営の状況を正確に理解するには、両方をあわせて確認することが大切です。
ここでは、それぞれの活用場面と注意点を解説します。
入居率を活用する場面
入居率は、現時点での経営状況を把握したり、改善の判断を行ったりする際に活用できます。
具体的には、次のような場面で活用が可能です。
- 空室が多い月に、募集条件や賃料見直しの判断材料とする
- リフォームや設備投資の成果を測る効果検証に用いる
入居率が高いことは物件の需要の高さを示しますが、短期間の入居者入れ替わりが頻繁に起こる場合は、賃料が極端に高いなどの理由で短期解約につながっている可能性があります。また、短期解約は稼働率を低くする要因であるため、注意が必要です。
稼働率を活用する場面
稼働率は収益性を把握し、空室対策や賃料設定の見直しなど運営の改善に役立つ指標です。
月単位や年単位で集計することで、次のような活用ができます。
- 空室が長期化している部屋や季節的な需要変動を把握する
- リフォームや募集条件の見直しなど具体的な改善策を立てる
稼働率の平均値は地域によって大きく異なり、都心部など人気の高いエリアでは高くなる一方、地方都市では低くなる傾向があります。
また、物件の立地条件や築年数、設備なども稼働率に影響を与えるため、自身の物件の稼働率を地域平均と比較し、現状を客観的に分析することが大切です。
まとめ

入居率は「ある時点でどれだけ部屋が埋まっているか」を示す瞬間的な指標であり、物件の人気度や現状把握に適しています。稼働率は「一定期間を通じて実際に稼働していた割合」を表すため、収益の安定性や空室リスクの把握に役立つ指標です。
入居率は短期的な状態の確認、賃貸稼働率は長期的な収益性の評価に活用される指標であり、不動産経営において両方をあわせて活用することが大切です。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
久保田 克洋
不動産業界に20年以上従事。賃貸管理を中心に管理受託業務・売買仲介・民泊運営を担った幅広い知識と経験をベースに、現在はプロパティマネジメント・アセットマネジメントを担っている。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
石塚 佳穂
新卒で不動産会社に入社後、一貫して賃貸管理業務に従事。オーナーが所有する物件の価値向上に取り組み、実務経験を積んできた。現在は、セミナーやキャンペーンの企画・立案など、マーケティング業務にも携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!