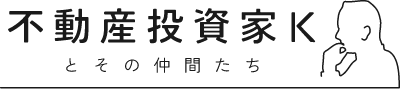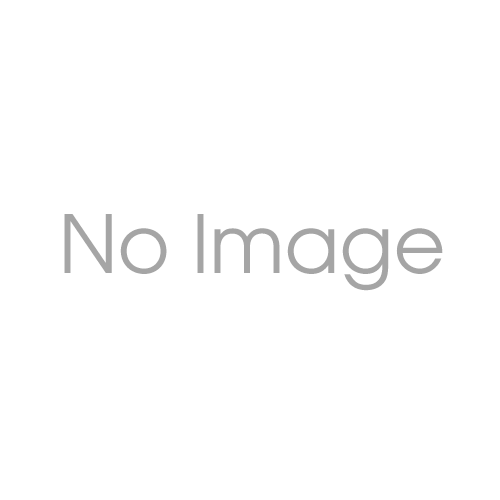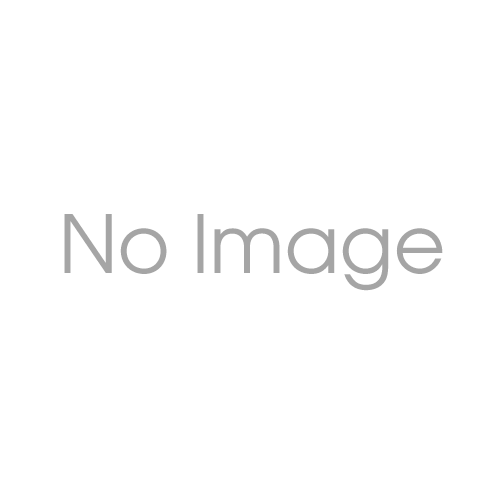
土地活用を検討する中で「100坪はどのくらいの広さ?」「どのように活用できる?」と、お悩みではありませんか?所有する土地を有効活用して収益化するためには、活用方法や注意点をあらかじめ把握しておくことが重要です。
この記事では具体例を用いて100坪の広さを解説するほか、100坪の土地活用の方法10選も紹介します。建築に関する制限や土地活用を成功させるポイントなどもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
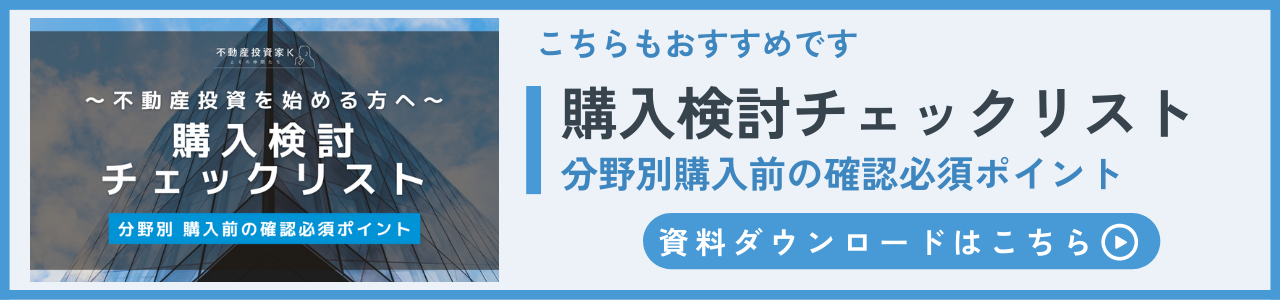
ポイント
- 100坪は330平米(㎡)・200畳程度の広さ
- 建物を建てる際は、建ぺい率・容積率などの制限に注意が必要
- 100坪の土地は賃貸アパート・マンション経営などに活用可能
100坪は330平米・200畳程度
1坪は、約3.3平米(㎡)です。100坪は、およそ330平米(㎡)となります。坪を畳で表す場合、1坪は2畳で換算し、100坪は畳約200枚分です。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
100坪の広さのイメージ例
100坪の広さは、たとえば以下と同程度です。
- 25mプール:6レーン分(小学校のプール約1つ分)
- バレーボールコート:2面分
- 一般的な3LDKマンション(70〜80㎡)の約4〜5戸分
住宅金融支援機構による2023年度の「フラット35利用者調査」によると、日本の住宅面積の平均は102.2㎡です。100坪は平均的な日本の住宅面積の3倍以上にあたり、複数世帯でもゆとりをもって暮らせる広さです。
2階建ての住宅を建てた場合でも、十分な庭や駐車スペースを確保でき、広々とした住環境を実現できるでしょう。
参考:住宅金融支援寄稿 「フラット35利用者調査」
100坪の土地に建てられる建物に関する4つの制限

100坪の土地に建物を建築する際は、各種制限に注意が必要です。制限に反する建物を建てた場合、建築基準法違反として行政処分を受ける可能性があります。所有する土地がある自治体のWebサイトで、都市計画情報などを確認しておきましょう。
ここでは、100坪の土地に建物を建築する際に注意すべき4つの制限について解説します。
1.建ぺい率
建ぺい率とは、土地の敷地面積に対する建物の建築面積の割合のことです。「土地のうち、どのくらいの面積を建物で覆ってよいか」を示すもので、建物を真上(上空)から見た際の面積を指します。
一般的には、1階部分の広さと一致するケースが多いでしょう。2階以上の部分に1階よりも張り出している箇所があれば、その面積も含む必要があります。
建ぺい率は主に以下の目的で都市計画によって設定され、地域や土地条件ごとに数値が異なります。
- 火災の延焼防止
- 風通しや日当たりの確保
- 景観の維持
たとえば、所有する100坪の土地の建ぺい率が70%の場合、最大70坪までの建築面積になるよう調整しなければなりません。
建ぺい率の計算方法は、以下のとおりです。
建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100
あわせて読みたい
2.容積率
容積率とは、「敷地に対して建物全体がどれだけの床面積を持てるか」を表す指標です。
建ぺい率の対象面積が1階部分など「建築面積」であることに対し、容積率は建物のすべての階の床面積を合計した「延床面積」を指します。ただし、玄関やロフト、バルコニー、地下室など、延床面積に含まれないスペースもあります。
「広さ」を規制する建ぺい率とは異なり、「高さ」を規制することで人口密度をコントロールし、効率的に都市計画を進めることが容積率の主な目的です。
容積率の計算方法は、以下のとおりです。
容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100
たとえば、容積率が80%の場合、100坪の土地では全階の延床面積が80坪までに収まるように調整する必要があります。仮に建ぺい率が70%(建築面積70坪まで)であれば、以下のような建物を建築可能です。
【建ぺい率70%、容積率80%の100坪の土地における建築例】
●平屋:最大70坪
●2階建て:1階40坪・2階40坪など
●3階建て:1階30坪・2階30坪・3階20坪など
あわせて読みたい
3.用途地域
用途地域とは、土地の合理的な利用を図るために、都市計画区域内の土地の用途を13区分に分類したものです。大きく分けて、住居系・商業系・工業系の3つの系統があり、さらに細かく13種類に分けられています。
用途地域によって、建築可能な建物の種類や規模の制限が異なるため、所有する土地の分類を確認しておきましょう。
たとえば、第一種低層住居専用地域では高さ制限や建ぺい率・容積率が特に厳しく設定されており、原則として商業施設は建築できません。商業地域では住宅から商業ビル、飲食店まで多様な建築が可能である一方、騒音や治安などに対する配慮が求められる可能性があります。
用途地域の種類や特徴は以下のとおりです。
| 種類 | 特徴 | 用途地域 |
|---|---|---|
| 住居系 | ● 住宅の建築が可能 ● 容積率の上限値が低めに制限されている |
第一種低層住居専用地域 |
| 第二種低層住居専用地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 第一種住居地域 | ||
| 第二種住居地域 | ||
| 準住居地域 | ||
| 田園住居地域 | ||
| 商業系 | ● 住宅の建築が可能 ● 容積率の上限値が高めに設定されている |
近隣商業地域 |
| 商業地域 | ||
| 工業系 | ● 工業専用地域では住宅の建築不可 | 準工業地域 |
| 工業地域 | ||
| 工業専用地域 |
参考:国土交通省 みんなで進めるまちづくりの話
4.高さ
所有する土地の高さ制限にも注意が必要です。たとえば「絶対高さ制限」が低く設定されているエリアの場合、高層マンション・アパートなどは建築できません。
高さ制限には以下5つの種類があり、最も厳しい制限に準じる必要があります。
- 絶対高さ制限:建物の高さを10mまたは12m以内に収める
- 道路斜線制限:前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線の中に建物を収める
- 隣地射線制限:隣地との境界線から一定の勾配で引いた斜線の中に建物を収める
- 北側射線制限:北側隣地との境界線から一定の勾配で引いた斜線の中に建物を収める
- 日影規制:中高層の建物によって冬至日に一定時間以上にわたって日影となる部分を、敷地境界線から一定の範囲内に収める囲み
建物の高さに関する各種制限は、用途地域ごとに適用の有無が異なります。以下に、主な用途地域と各制限の対応状況をまとめました(○=適用あり、-=適用なし)。
用途地域の分類によって、どの制限に該当するかを事前に確認しておくことが重要です。
| 用途地域 | 絶対高さ制限 | 道路斜線制限 | 隣地射線制限 | 北側射線制限 | 日影規制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 第二種低層住居専用地域 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 第一種中高層住居専用地域 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第二種中高層住居専用地域 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第一種住居地域 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 第二種住居地域 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 準住居地域 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 田園住居地域 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 近隣商業地域 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 商業地域 | - | ○ | ○ | - | - |
| 準工業地域 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 工業地域 | - | ○ | ○ | - | - |
| 工業専用地域 | - | ○ | ○ | - | - |
| 定めのない地域 | - | ○ | ○ | - | ○ |
100坪の土地活用の方法10選

100坪の土地は、さまざまな活用方法を検討できます。賃貸経営や事業用施設の運営など、収益性や節税効果を見込める選択肢も豊富です。立地や予算などに応じて活用方法を選ぶとよいでしょう。
ここでは、具体的な土地活用のアイデア10選を紹介します。
1.賃貸アパートを経営する
2.賃貸マンションを経営する
3.賃貸戸建てを経営する
4.駐車場を経営する
5.コインランドリーを経営する
6.トランクルームを経営する
7.コンビニエンスストアを賃貸・経営する
8.福祉施設を賃貸する
9.太陽光発電事業を経営する
10.賃貸併用住宅を経営する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.賃貸アパートを経営する
1つ目は、賃貸アパートを建築し、家賃収入を得る方法です。収益性が高めの土地活用方法で、土地の相続税や固定資産税の節税にもつながります。
たとえば容積率60%以上の土地の場合、1フロア30坪の2階建てのアパートに6~8室程度の単身向けの部屋を用意できるでしょう。残りの土地で、駐車場や駐輪場を備えることも可能です。
一般的に、容積率の上限設定が高いエリアほど収益を得やすい傾向があります。ただし、空室を回避するためには立地条件のよさが求められます。
なお、法律上はアパートとマンションに明確な違いはありませんが、一般的には木造・軽量鉄骨造の低層物件を「アパート」と呼ぶ傾向があります。
あわせて読みたい
2.賃貸マンションを経営する
2つ目は、賃貸マンションを建築し、家賃収入を得る方法です。
100坪の土地の場合、単身または2人暮らし向けのマンション経営が現実的でしょう。容積率によるものの、高さがあるマンションであるほど部屋数を増やせるため、アパートに比べて建設費用は高額ですが、その分高収益が期待できる点が特徴です。
なお、法的な違いはないものの、一般的に鉄筋コンクリート造や3階建て以上の集合住宅は「マンション」と呼ばれる傾向があります。
3.賃貸戸建てを経営する
3つ目は、主にファミリー層向けの戸建て住宅を建築し、賃料収入を得る方法です。100坪の土地であれば、2~3軒の戸建てを建築することが可能です。
戸建ては賃貸アパート・マンションと比べて希少価値が高く、競合が少ないエリアであれば顧客を獲得しやすいでしょう。ファミリー層の場合、比較的長く入居を継続してもらえる可能性が高く、引っ越しによる空室リスクを抑えられる点もメリットです。
一方、賃貸アパート・マンションと比べて戸数が少なくなりやすいため、運用効率が悪くなる可能性があります。
4.駐車場を経営する
4つ目は、月極の駐車場やコインパーキングを建設し、利用料を得る方法です。
100坪の土地があれば最大約20台の駐車スペースを確保可能です。建物の建設が不要なため、建ぺい率の制限を受けることなく土地をフル活用しやすいほか、初期費用も抑えやすいメリットがあります。また、運用の手間が少なく、無人経営も実現しやすい点も魅力です。
ただし、住宅用地と比べると固定資産税の優遇措置が適用されないため、節税効果には期待できません。
5.コインランドリーを経営する
5つ目は、コインランドリーを建築し、洗濯機や乾燥機の利用料を得る方法です。100坪の土地の場合、大型店舗を構えることが可能です。敷地内に駐車場スペースを備えてもよいでしょう。
住宅街が近い場合など、近隣住民による固定客がつけば、安定収入を期待できます。運用を業者に委託することで、管理の負担を軽減できる点も魅力です。
一方、洗濯機や乾燥機を設置するための高額な初期費用が必要です。
6.トランクルームを経営する
6つ目は、トランクルームを建築し、利用料を得る方法です。
アクセスや日当たりが悪い土地や騒音が気になる土地、変形地など、住居の建築には向かない条件の土地でも活用可能です。賃貸マンション・アパートなどの建築と比べて初期費用を抑えやすい点も魅力です。
一方、ニーズが少ないまたは過密状態のエリアなどでは、なかなか借り手がつかない恐れもあります。また借地借家法の適用外のため、相続税対策には不向きです。
7.コンビニエンスストアを賃貸・経営する
7つ目は、コンビニエンスストアを建築し、賃料収入を得る方法です。オーナー自らが経営することも可能です。
賃貸の契約期間が長めであることから、安定した収益を期待できます。また自ら経営する場合、成功すれば高い収入を得ることが可能です。
繁華街や幹線道路沿い、駅の周辺など、人通りが多く集客が見込めるエリアの土地に向いているでしょう。ただし出店できるエリアには制限があり、原則として第一種低層住居専用地域ではコンビニの建築が認められていません。
また居住用施設ではないため、固定資産税の軽減などによる節税効果も得られない点にも注意が必要です。
8.福祉施設を賃貸する
8つ目は、老人ホームやグループホームといった福祉施設を建築し、賃料収入を得る方法です。高齢者が多く居住するエリアでは、一定のニーズを期待できるでしょう。
運営は専門事業者に委託できるため、オーナー自身の管理負担は軽めです。また、国や自治体から建築費用の補助金を受けられる可能性もあります。
ただし、福祉施設はバリアフリー設計や消防設備など、特殊な仕様が求められるため、他用途への転用は困難です。長期的な需要動向や行政の方針も踏まえた上での検討が必要です。
9.太陽光発電事業を経営する
9つ目は、太陽光発電パネルを設置して電気を発電し、売電収入を得る方法です。特に、日当たりが良好で平坦な土地が最適です。
アクセスが悪く、賃貸経営には向かない郊外の土地でも活用しやすいでしょう。集客不要で、対人トラブルや空室リスクを避けられるほか、管理の手間が少ない点も魅力です。
一方、他の土地活用の方法と比べると収益性は低めです。初期費用が高額になりやすく、運用後は自然の影響を受けやすい点もデメリットにあげられます。
10.賃貸併用住宅を経営する
最後に紹介するのは、建築したアパート・マンションの1室に自分が居住し、他の部屋を貸し出して賃貸収入を得る方法です。
賃貸収入で建築費用を返済することで、実質負担なしで自分が住む新居を確保できます。一定の条件を満たせば、事業用よりも金利の低い住宅ローンを利用することも可能です。
一方、戸数が限られるぶん、通常のアパート・マンション経営に比べて利回りが低くなりやすいデメリットがあります。借主と同じ建物に住むため、対人トラブルなどへの対応が必要になる可能性も考慮しておく必要があります。
100坪の土地にかかる固定資産税

土地の所有者は、固定資産税を支払う必要があります。固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を保有している人にかかる税金です。
固定資産税額の計算式は、以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率
一般的に、課税標準額(固定資産税評価額)は公示地価の70%程度で、税率は1.4%です。公示地価とは、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月に公示する、1㎡あたりの標準地の価格を指します。
所有する土地に建物を建てることで、以下のように固定資産税の課税標準額の軽減措置を受けることが可能です。
| 敷地面積 | 軽減割合 |
|---|---|
| 200㎡超の部分 | 1/3 |
| 200㎡以下の部分 | 1/6 |
100坪の土地は約330㎡であるため、200㎡分は1/6、残りの130㎡分は1/3に、それぞれ課税標準額の軽減措置を受けることが可能です。
参考:国土交通省 地価公示
あわせて読みたい
100坪の土地活用を成功させるポイント

土地活用を成功させるには、収益性・安全性・継続性の3つの視点を持って検討することが大切です。専門的な知識が求められるため、土地活用のプロに相談することがおすすめです。
100坪の土地活用を成功させるポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.エリアニーズにあったものを選ぶ
土地活用では、「そのエリアに合ったニーズを把握すること」が成功の第一歩です。
たとえばファミリー層向けの戸建て住宅やマンションを建てたいという希望があったとしても、所有している土地のエリアがオフィス街であれば需要は少ないため、成功しにくいでしょう。
人口推移や商業施設、将来的な開発予定の有無の確認といったエリア調査を行い、どのようなニーズがあるか見極めたうえで、土地活用の方法を検討する必要があります。
2.初期費用と収益性のバランスを見極める
初期費用と収益性のバランスを考慮することも重要です。
長い年数をかけて行う土地活用は、見通しが甘ければ行き詰まる恐れがあります。建物の建築や設備の設置に高額な初期費用が必要な場合は、初期投資を上回る収益を「いつまでに」「どのくらい」見込めるか、特に念入りに確認しておきましょう。
長期的な視野をふまえて初期費用と収益性のバランスを見極め、無理のない収支計画を立てる必要があります。
3.法規制・税制を事前にチェックする
所有する土地や土地活用の方法に当てはまる法規制・税制について、事前にチェックしておく必要があります。
建物の建築に制限がある場合、100坪の土地をすべて活用できない可能性があります。独自の制限や条件を設けている自治体もあるため、注意が必要です。建築の計画を立てる前に、必ず所有する土地の法規制を確認しておきましょう。
また、土地活用の方法によって節税効果が異なります。固定資産税や相続税といった最新の税制度も把握しておくことが大切です。最新の税制度を確認するには、税理士や不動産専門家への相談も有効です。
4.専門家に相談する
自分1人で抱え込むのではなく、土地活用の検討段階から専門家の意見を取り入れることが重要です。
土地活用の際は、立地条件や周辺環境などの調査、各種制度・収益性などに関する専門知識が求められます。さまざまな選択肢から最善策を選ぶことは、容易ではありません。土地活用に詳しいプロフェッショナルとともに進めていくことが、成功への近道です。
業者を選ぶ際は、過去の実績や提案力、担当者の対応力などを重視して、信頼できるパートナーを見極めることが大切です。
まとめ

100坪は330平米(㎡)・200畳程度の広さで、賃貸アパート・マンション経営や駐車場経営など、さまざまな土地活用の方法を検討できます。
建物を建てる場合、土地の建ぺい率や容積率、用途地域などに関する制限に注意が必要です。土地活用には、エリアニーズの調査から法規制まで幅広い専門知識が求められるため、専門業者に相談することをおすすめします。

監修者
杉田 裕蔵
東京を中心に、20年以上アパート・マンション建築賃貸業界に従事。現場に密着した営業経験と建築知識、不動産知識を活かして業務に携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!