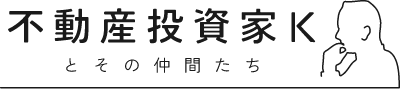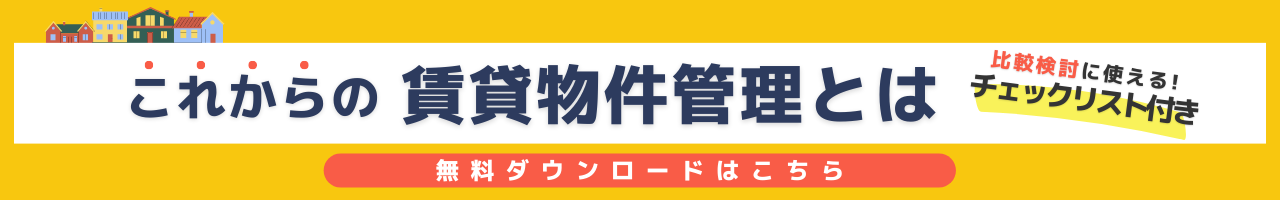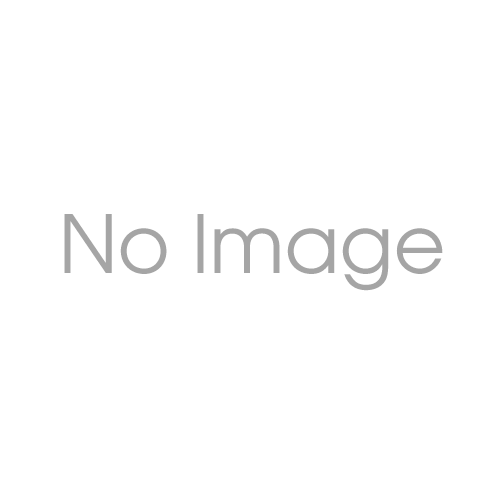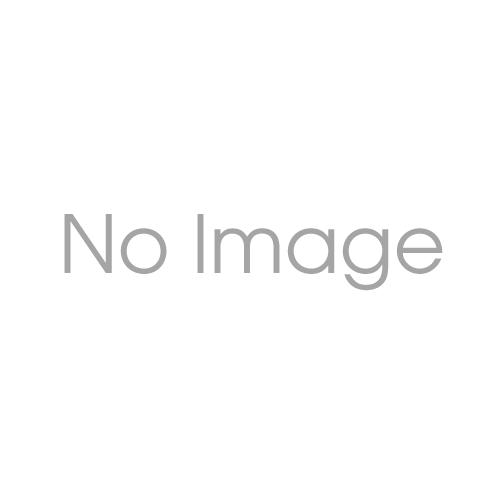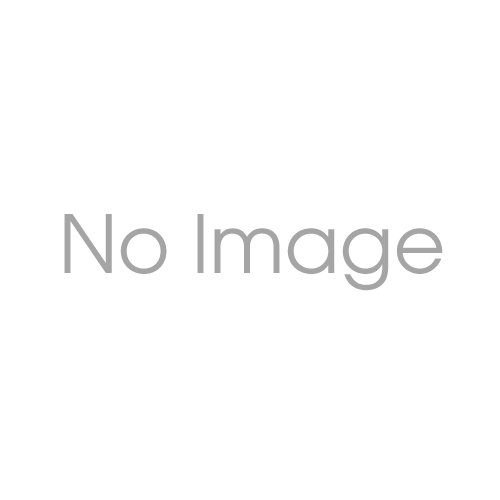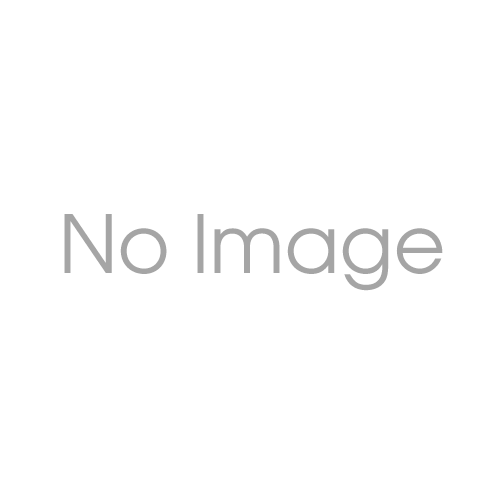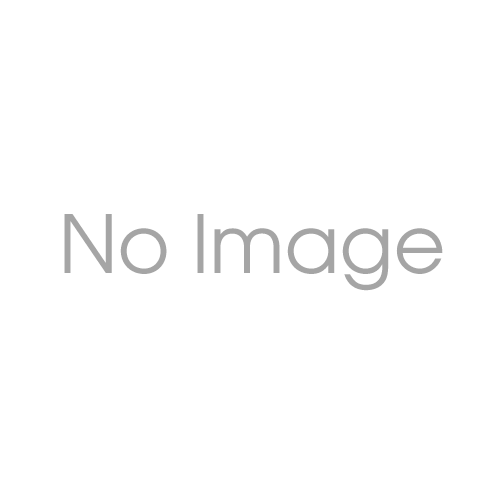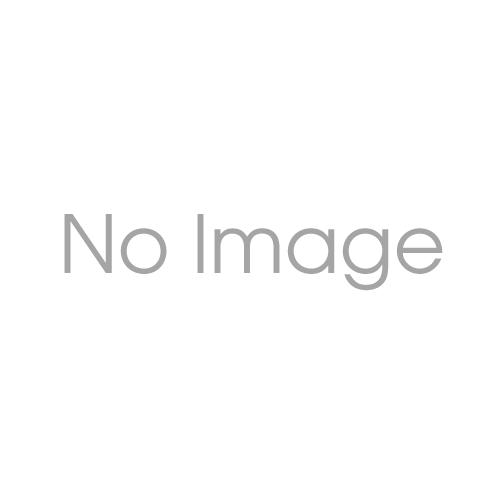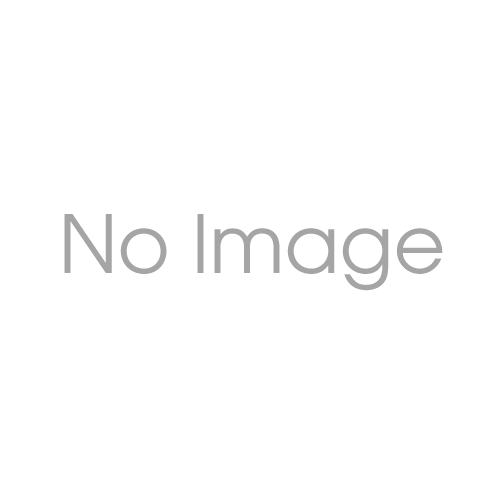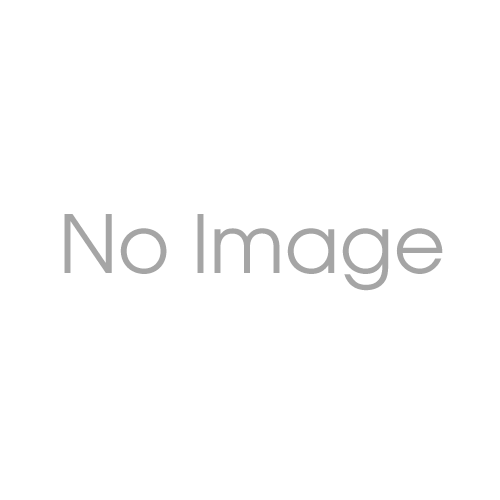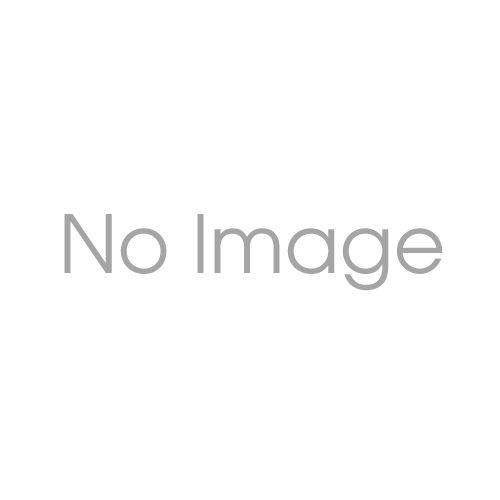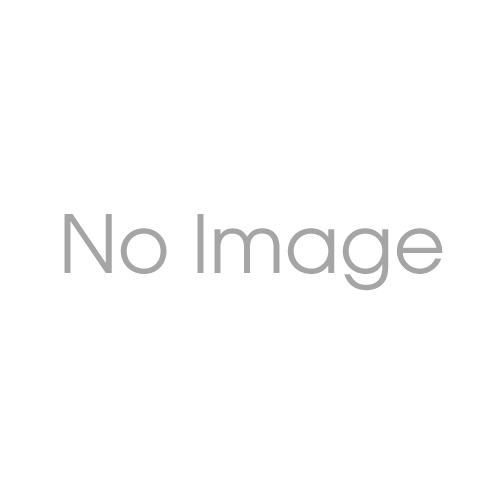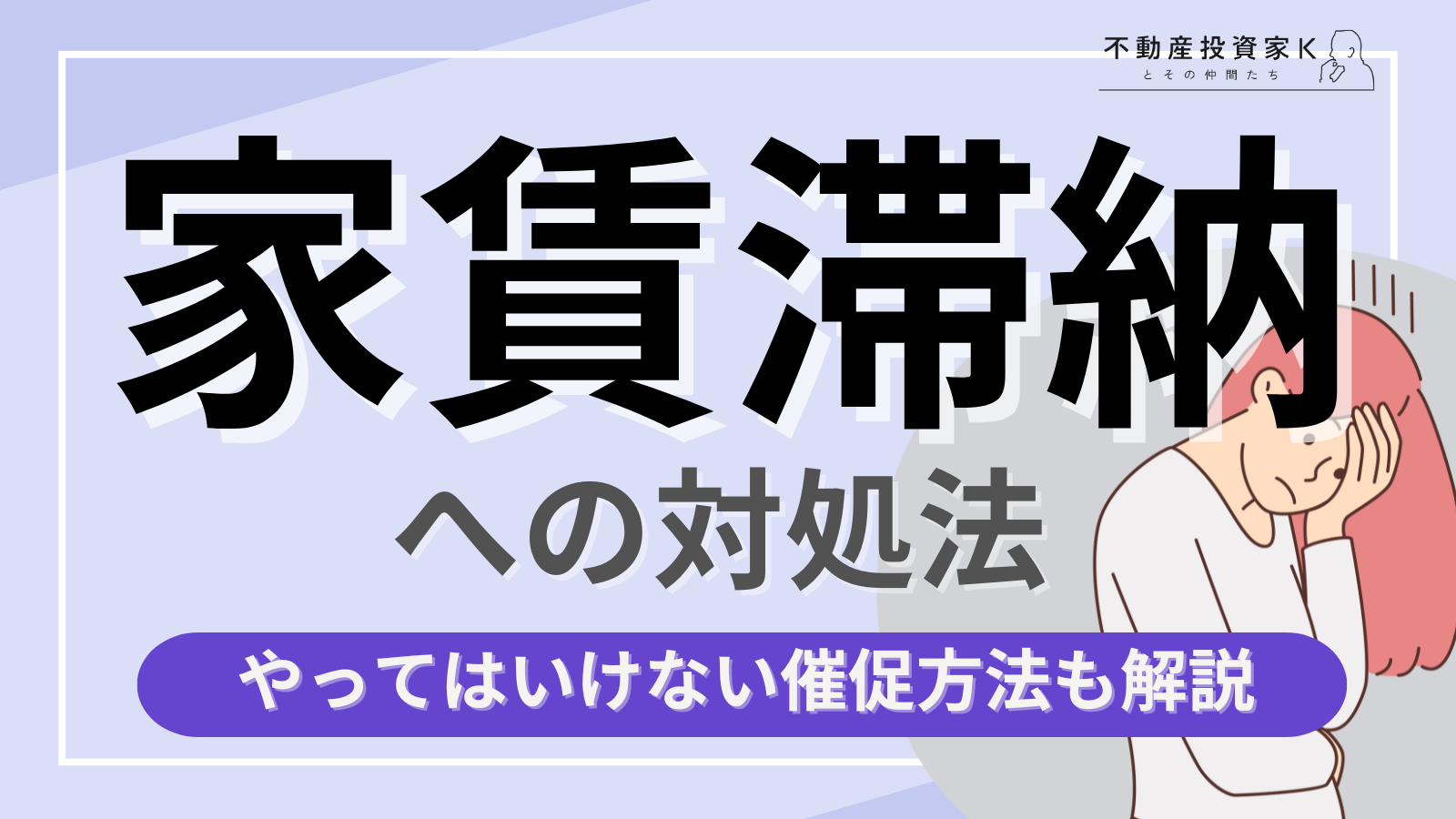
オーナー(賃貸人)にとって、家賃滞納は大きなリスクの1つです。滞納者に簡単に退去を求めることもできず、滞納が拡大すれば回収が難しくなるだけでなく、費用の負担がかかる場合もあります。
本記事では、家賃滞納が発生した場合の対処法ついて紹介します。
ポイント
- 家賃を催促する際の方法には注意が必要
- 家賃保証会社の利用により滞納リスクを減らすことができる
電話や書面、訪問により催促する
まずは電話・書面郵送・直接訪問などの方法で催促します。
最初のアプローチとしては、電話での催促となることが多いでしょう。その際、連絡がつかないからと、夜遅い時間や朝早い時間に電話をすることは止めましょう。
電話がつながらない場合や電話で支払いの約束をしたにもかかわらず滞納を続ける場合は、郵送や直接訪問により催促を行います。特に滞納が長期となった場合は直接訪問により催促します。直接訪問は手間がかかりますが、滞納者の状況を把握する上で有効です。また、滞納者が部屋で倒れていないか、夜逃げや失踪ではないかの確認も必要です。
ただし、執拗な催促や、早朝や深夜、職場などへの連絡により恐怖を感じさせるような行為は、脅迫罪や名誉毀損罪で訴えられてしまう場合があるため注意してください。
連帯保証人へ連絡する
滞納者本人に支払い能力がない場合や支払う意思がない場合には、連帯保証人へ連絡します。連帯保証人は、入居者が支払いできない場合に代わりに支払う義務を負います。もし滞納者からの支払いの目処が立たなければ、すみやかに連帯保証人へ連絡しましょう。
代位弁済(一般保証)型の家賃保証会社を利用している場合は、滞納発生時点で事故報告を行い期限内に代位弁済を受けるようにします。代位弁済が行われると、債券が保証会社に移り、以降は保証会社が滞納者に支払いを求めることになります。
内容証明郵便で請求する
催促しても支払いに応じない場合は、内容証明郵便による請求を行うという方法もあります。内容証明郵便とは、いつ誰がどのような内容の文書を誰に送ったのか法的に証明してくれる郵便物です。滞納者が内容証明郵便を受け取れば、滞納された家賃を求める内容を送ったことを証明できます。
交渉で解決できなかった場合には法的手段をとることになるため、督促を行った証明として内容証明郵便を利用するため、法的手段のための準備ともいえます。
家賃滞納者への内容証明郵便で記載すべき事項は、以下のとおりです。
・通知内容
・日付
・受取人の住所・氏名
・差出人の住所・氏名
・滞納金額
・支払い期限
・振込先
上記に加えて、再三の催告に応じない旨、期限までに支払われなければ法的措置をとる旨も明記しておきます。
自主管理オーナーの場合、ここまでの対応はすべて自身で行うことになります。
家賃保証会社を利用している場合
支払い保証型の家賃保証会社を利用していれば、催促から訴訟手続きまでオーナーが行う必要はありません。
支払い保証型の契約では、家賃保証会社が家賃の立て替えを行うため、入居者とオーナーとの間で家賃のやり取りは発生せず、催促や訴訟手続きはすべて家賃保証会社が行います。
家賃保証会社との契約には、代位弁済型(一般保証型)という滞納が発生した場合のみ立て替えを行う契約もあります。代位弁済型であれば、オーナーは家賃保証会社に事故報告を行う必要があります。代位弁済には免責期間があり、期間を過ぎると代位弁済が受けられなくなるため注意が必要です。
あわせて読みたい
法的手続きによる家賃回収
退去までは求めず滞納した家賃の回収をしたい場合は、以下の法的手段が考えられます。
- 支払督促
- 少額訴訟
訴訟と同様の効力があり、訴訟に比べると費用がかからず手続きも複雑ではないため、負担が少ない方法といえるでしょう。
支払督促
支払督促とは、家賃などの支払いがされない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて裁判所が滞納者に支払いを命じる略式の手続きです。
支払督促には、以下のメリットがあります。
- 書類審査のみで済む
- 訴訟に比べて金額が抑えられる
- 仮執行宣言付支払督促により強制執行を申し立てられる
メリットの1つは、書類審査のみで済むという簡便さです。支払督促は証拠がいらない上に、訴訟のように裁判を開く必要がなく、書類審査のみで済みます。証拠集めや裁判に出向く手間と時間を省けます。
ほかにも、訴訟に比べて金額が抑えられる点もメリットといえるでしょう。支払督促に必要な費用は、申立てにかかる手数料と書類の郵送料です。手数料は請求額によって異なり、10万円までは500円、100万円までは10万円を超えるごとに500円加算されます。
支払督促のあと相手から異議申し立てがない場合は、仮執行宣言の申し立てを行い、仮執行宣言付支払督促が送られます。これに異議申し立てがなく支払いもない場合は、明け渡し請求訴訟をせずに強制執行の申し立てが可能になります。
ただし、滞納者が異議申し立てを行うと、その時点から訴訟に移行することになります。そのため、訴訟より簡便な手続きであっても、訴訟に発展する可能性があることは理解しておきましょう。
少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭を請求する場合に利用できる訴訟手続です。
少額訴訟には、以下のメリットがあります。
- 審理は原則1回
- 勝訴すれば訴訟費用を相手負担として請求可能
審理は原則1回限りのため、すみやかな決着が見込めます。
少額訴訟にかかる費用は、申立て手数料と切手代です。手数料は請求金額によって異なり、10万円までは1,000円、10万円増えるごとに1,000円加算されます。切手代も裁判所とのやり取りの回数によって異なりますが、一般的には5,000円程度が目安です。
支払督促よりもかかる費用は少し高くなりますが、勝訴すれば訴訟費用を相手負担として請求できます。ただし、少額訴訟も支払督促と同様に相手が民事訴訟を求めれば、さらに時間や費用がかかります。
明け渡し請求訴訟を行う
明け渡し請求訴訟とは、訴訟により入居者に物件の明け渡しを求めることです。同時に滞納した家賃の請求も求めることができます。裁判により明け渡し請求が認められても、期日までに入居者が退去しない場合には、強制執行の申し立てを行うことになります。
明け渡し請求訴訟を行うと、費用がかかる上に半年から長ければ1年ほどと、時間がかかります。裁判中も家賃収入を得られない上に、裁判にも費用がかかります。
そのため、できる限り和解による早期解決を図ることが得策でしょう。
やってはいけない対処方法

滞納者には速やかに滞納家賃を支払ってもらいたいものです。だからといって、強引に督促することは認められていません。
- 深夜・早朝に連絡する
- 1日に何度も連絡する
- 玄関やポストに催促状を掲示する
- 学校や職場に連絡する
- 保証人以外に連絡する
- 無断で入室する
- 勝手に荷物を撤去する
- 勝手に鍵を交換する
もしこうした行動をしてしまった場合には、懲役や罰金の対象となるためご注意ください。
深夜・早朝に連絡する
家賃の支払いを催促することは正当な行為ですが、深夜や早朝の連絡は、相手に恐怖を与える行為として違法行為になる恐れがあります。
実際に深夜0時を過ぎても催促を行った賃貸人に対し、慰謝料請求が認められた事例があります。催促を行う時間帯には十分に注意しましょう。
参考:国土交通省 滞納・明け渡しを巡るトラブルについて
玄関やポストに督促状を掲示する
玄関やポストに掲示して、他の入居者などの第三者に滞納がわかる形で督促する行為はやめましょう。
滞納者以外に滞納している事実を明かすことは、名誉棄損に当たる可能性があります。
勝手に荷物を撤去する
たとえオーナーが所有している物件であったとしても、勝手に滞納者の荷物を捨てたり、持ち出したりする行為は違法です。もし勝手に荷物を撤去した場合には、器物損壊罪や窃盗罪の罪に問われることになります。また、自力救済禁止の原則に違反します。
自力救済禁止の原則とは、裁判など法律の手続きを行わず自力で侵害を排除することはできないという原則です。
勝手に鍵を交換する
勝手に鍵を交換する行為も、荷物を勝手に撤去するのと同様に自力救済禁止の原則に違反します。もし賃貸契約書に「家賃滞納時には鍵を交換可能」と記載されていたとしても、取り決めが無効になる可能性が高いです。実際に、契約内容によると鍵の交換が認められていたものの、滞納者の生活を阻害する行為としてオーナーと管理会社に損害賠償を命じた事例があります。
参考:一般財団法人不動産適正取引推進機構 建物賃貸借に関する紛争(1)契約-自力救済・貸室立入
家賃滞納を未然に防ぐ方法

家賃滞納は起こってしまうと解決には時間もお金もかかる場合が多いため、対策を行い、未然に防ぐことが重要です。家賃滞納の予防策は、以下のとおりです。
- 入居審査をしっかりと行う
- 口座振替・カード払いにする
- 家賃保証会社を利用する
入居審査をしっかりと行う
家賃滞納を防ぐには、入居審査をしっかりと行う必要があります。入居審査では、年収の高低ではなく、継続的に家賃を支払えるかどうかに重点をおくと良いでしょう。
入居審査の内容は、過去の滞納歴の確認、収入確認書類の提出、勤務先への在籍確認などがあります。また、親族以外の緊急連絡先を提出してもらうことも検討しましょう。厳しい入居審査により入居できない人が出る可能性もありますが、家賃滞納などのトラブルを防ぐにはある程度厳しいふるいにかけることも大切です。
ただし、築年数や交通の便、立地などの条件によっては、入居審査を厳しくしすぎると、そもそも入居者が集まらず、家賃収益が得られないという事態になる恐れがあるため、バランスを見て入居審査の内容を検討する必要があります。
あわせて読みたい
口座振替・カード払いにする
家賃支払いを口座振替やクレジットカード払いにすることでも、家賃滞納を防げます。
家賃を滞納する人の中には、うっかり入金を忘れていただけで、悪気がない場合もあります。そのようなケースを防ぐためにも、口座振替やカード払いで自動引き落としするのがおすすめです。
口座振替であれば、口座に残高がない場合は引き落としできませんが、カード払いであればそのような心配もいりません。
家賃保証会社を利用する
近年では連帯保証人をつけることが難しい場合も考慮し、連帯保証人の代わりに家賃保証会社を利用するケースが増えています。
家賃保証会社を利用すれば、滞納者がいても安定した家賃収入を得ることができます。支払保証型であれば、支払い催促や裁判をオーナーが行う必要もなく、裁判費用なども保証してもらえる場合が多いです。家賃保証会社の利用は、家賃滞納リスクを減らす手段としては非常に有効でしょう。
ただ、家賃保証会社を利用することで入居者の費用負担が増し入居が決まりにくくなる可能性があったり、家賃保証会社自体の倒産・破産の恐れがあったりします。家賃保証会社を利用する場合は、こうした注意点も念頭に入れて選びましょう。
あわせて読みたい
まとめ

家賃滞納は早期に解決したい重大な事項ですが、督促の仕方によっては違法行為で罰せられてしまう恐れがあるため、注意を払って支払いを求める必要があります。
また、家賃滞納はオーナーを悩ますだけでなく、滞納者にとっても日常生活を送る上でさまざまな弊害が生まれます。入居者自身が気をつけるだけでなく、オーナー自身も家賃滞納を未然に防ぐ対策を行いましょう。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
前田 英伸
10年以上にわたり不動産業界に従事。主にプロパティマネジメント業務を行う傍ら、家賃保証会社の設立に携わり、現在は取締役として契約者2万人を超える家賃保証会社の経営を担っている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!