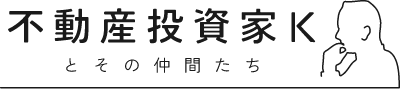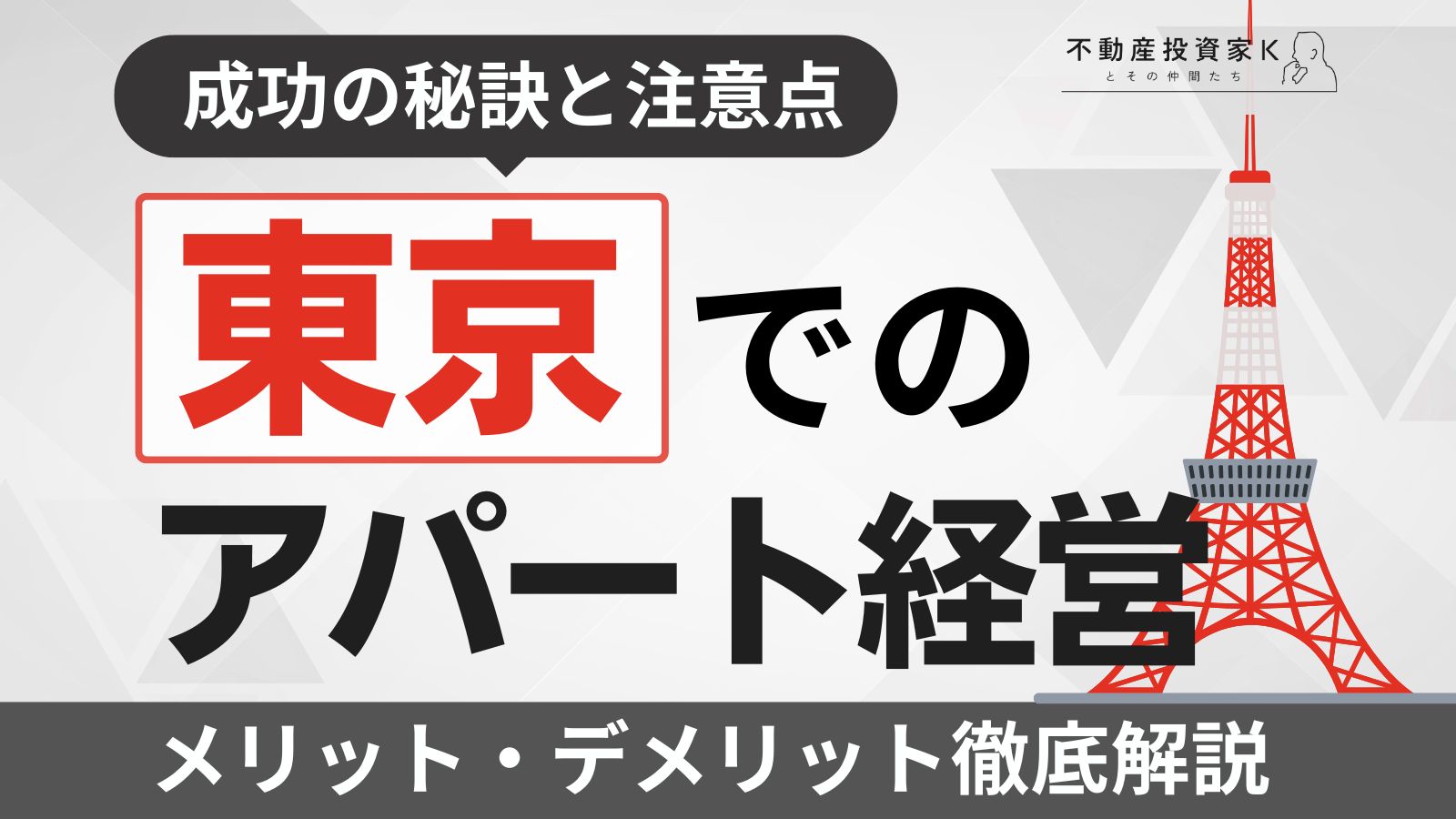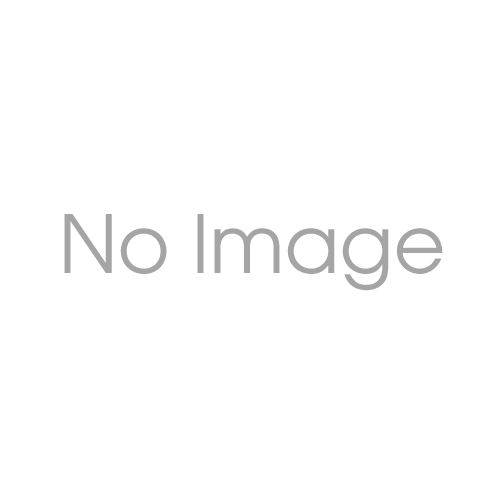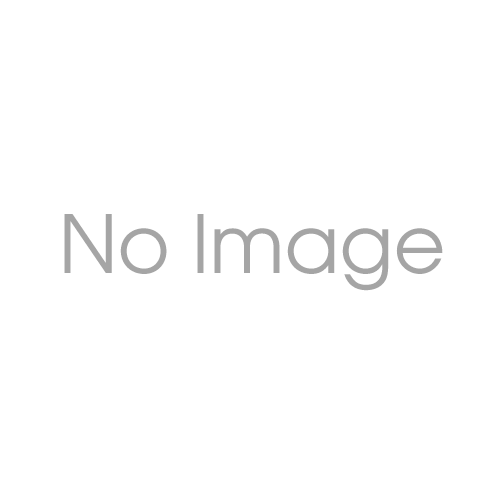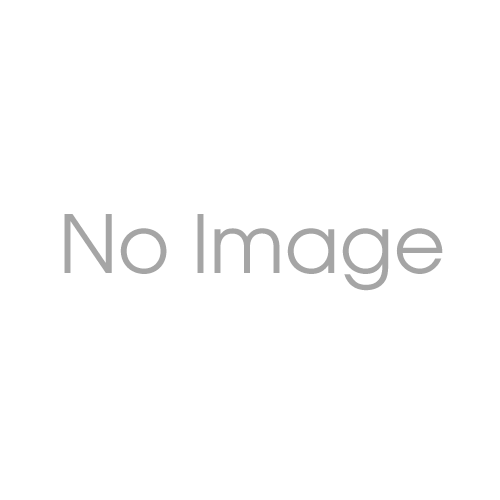
賃貸物件の設備不良が生じた場合、入居者の生活に支障が出てしまいます。賃貸物件の設備不良についてはオーナーが責任をとらなければならず、家賃減額の要因の1つです。
今回の記事では設備不良時に家賃減額になる条件や相場、対処法などを紹介します。
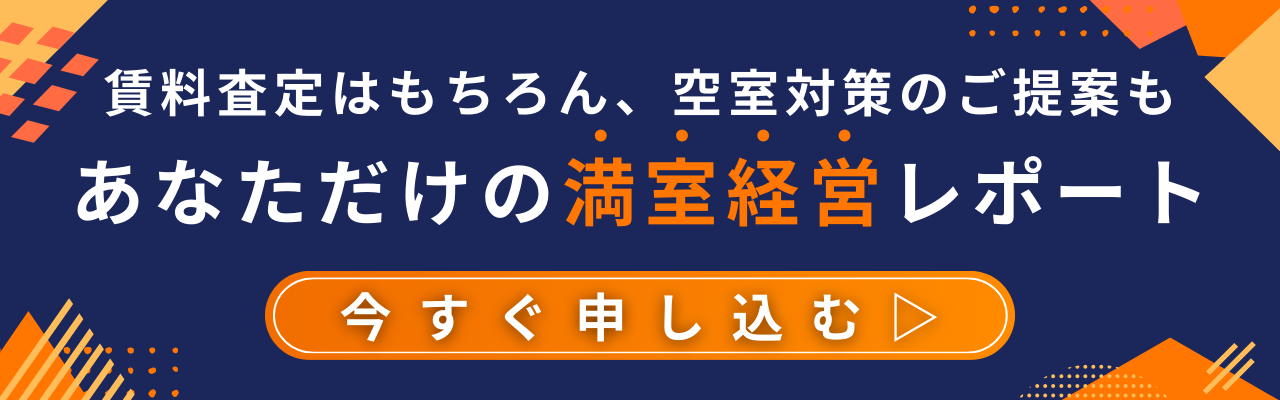
ポイント
- 民法改正により、設備の故障によるオーナーの責任が明確になった
- 入居者の生活に支障を与える程度によって、家賃の減額の割合が変わる
- 家賃の減額を避けるためには、事前のメンテナンスや保険などの活用が重要
民法改正によって設備不良・故障が家賃減額の対象に

賃貸物件で設備が故障した場合、入居者に落ち度がないのであれば責任は物件のオーナーにあります。ここでは、民法改正のポイントと不動産オーナーがとるべき対応を紹介します。
民法改正のポイント
責任の所在は変わっていませんが、2020年の民法改正によってオーナーの責任が明確化されました。改正後の民法では、下記のように記載されています。
「第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」
改正前の条文では「賃料の減額を請求できる」とあった記載が、「減額される」に変更されています。つまり賃貸物件の設備不良については、オーナーの責任が重くなったことを意味しています。
不動産オーナーがとるべき対応
設備不良による家賃収入の減少を最低限に抑えるために、設備の故障には従来以上に備えておくことが必要です。設備が故障した際には迅速に対応できるように、あらかじめ管理会社と対応フローを確認をしておきましょう。
また、民法改正を根拠に、設備故障期間を実際よりも長く申告されるリスクもあります。賃貸借契約書に「設備に不具合が発生した際は速やかに申し出る」などの特約を設けることも重要です。
1.該当設備が使用できないことで日常生活に影響がある
電気・ガス・水道・トイレ・風呂など、日常生活に不可欠なインフラが故障した場合は減額の対象となります。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)が発表している「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」では、減額の対象となる状況を次のA群・B群に該当するものとしています。
【A群】
・電気が使えない
・ガスが使えない
・水が使えない
【B群】
・トイレが使えない
・風呂が使えない
・エアコンが作動しない
・テレビ等通信設備が使えない
・雨漏りによる利用制限
いずれも該当設備が使用できないことで、日常生活に影響のあるものが対象とされています。
参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」改定のお知らせ
2.入居者に過失がない
入居者に過失がないことも、家賃減額の対象となる条件の1つです。つまり、設備に不具合が生じても、入居者に落ち度がある場合は減額の対象外となります。入居者に落ち度がある例としては、掃除を怠ったことによるエアコンのドレンホースの詰まりや、故意に設備を破壊した場合などがあげられます。このようなケースではオーナーに責任は生じず、家賃減額の対象となりません。
3.免責期間内に不具合を解消できなかった
免責期間内に不具合を解消できなかった場合も条件となります。前述の日管協のガイドラインでは、免責期間の目安を以下のように設定しています。
・電気が使えない:2日
・ガスが使えない:3日
・水が使えない:2日
・トイレが使えない:1日
・風呂が使えない:3日
・エアコンが作動しない:3日
・テレビ等通信設備が使えない:3日
・雨漏りによる利用制限:7日
参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」改定のお知らせ
免責期間とは、期間内に不具合を修正すれば、オーナーが責任を免れることができる期間です。たとえば、トイレの不具合の場合は免責期間の目安が1日であるため、1日で不具合を解消すれば家賃減額の対象となりません。一方、不具合解消に3日かかったのであれば、2日(3日-1日)が家賃減額の対象期間になります。
設備不良・故障でも家賃減額とならないケース

設備の不具合があったからといって、すべて家賃の減額対象になるわけではありません。前述のとおり、入居者の故意や過失による設備の故障の場合は、減額対象外です。また、電気やガス・水道に関する不具合であっても、供給元の問題で設備が使えない場合は、オーナーの責任とはなりません。
そのほか、照明器具や換気扇などの故障についても、過去の判例では減額が認められていません。軽微な故障で居住への影響が小さいと判断された場合は、オーナーの責任は問われず、家賃減額は認められないのが一般的です。
設備不良・故障による家賃減額に関する判例

オーナーとしては、賃貸物件の設備不良についてどこまで責任が問われるのか、気になるところでしょう。設備不良・故障による家賃減額が認められた事例と認められなかった事例をそれぞれを紹介します。
家賃減額が認められた事例
家賃の減額が認められるのは、日常生活に支障が生じた場合です。たとえば、給湯器の故障でお湯が出ず、修理工事が完了するまで実家に帰省するなどをしていたケースでは15%の家賃減額が認められています。
ほかにもエアコンが作動しなかった場合は30%の減額、上階からの漏水のケースでは50%もの減額が認められています。いずれのケースでも快適な日常生活を過ごせず、一時的に避難した場合もあるなど、入居者の生活を脅かしてしまったことが要因です。
参考:国土交通省 「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」について
家賃減額が認められなかった事例
家賃減額が認められなかったケースもあります。実際にあった事例では、入居者が壁の薄さを要因とした遮音性の低さを理由に、オーナーの修繕義務を根拠にして家賃の減額を請求したものの、認められませんでした。この事例では確かに壁は薄かったものの、賃貸借契約開始時点と壁の薄さが変わったわけではありませんでした。
オーナーの「修繕義務」は、「賃貸借契約の開始時点」を基準にしているため、もともと遮音性の低かった物件の、壁の薄さを原因とした家賃減額は認められません。オーナーとしては修繕義務をしっかりと果たしていれば、責任を負う必要がないことがわかる事例です。
参考:国土交通省 「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」について
家賃減額の相場とガイドライン

家賃減額が必要になった際、どれくらい減額すべきか相場を知っておくことで、入居者とのトラブルになるリスクを減らすことができます。日管協のガイドラインをもとに家賃減額の相場を紹介します。
設備ごとの減額割合の目安
ガイドラインでは、下記のように状況ごとの家賃減額割合の目安が定められています。
| 不具合の状況 | 家賃減額割合 |
|---|---|
| 電気が使えない | 40% |
| ガスが使えない | 10% |
| 水が使えない | 30% |
| トイレが使えない | 20% |
| 風呂が使えない | 10% |
| エアコンが作動しない | 10% |
| テレビ等通信設備が使えない | 10% |
| 雨漏りによる利用制限 | 5~50% |
出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」改定のお知らせ
故障により電気が使えない場合や水が使えない場合は、生活への影響が大きいため減額割合も高くなります。雨漏りも程度によっては日常生活が困難になることも想定され、最大で50%もの減額割合とされています。
一方で、ガスやエアコン、テレビなどは生活への影響はあるものの、日常生活を送れないほどではないことから低めの水準です。このように生活に支障の大きい箇所の故障になるほど、家賃の減額割合は高くなる傾向があります。
家賃減額の計算方法
家賃を減額する際は日割りで計算します。具体的な計算式は、下記の通りです。
月額家賃 × 家賃減額割合 × (使用不能日数 - 免責日数) ÷ 30日
たとえば、家賃10万円の物件でトイレが4日間使用不可(免責1日)だった場合、以下のように計算できます。
100,000円 × 20% × (4日 - 1日) ÷ 30日 = 2,000円
なお、免責日数は設備によって異なるため、日管協のガイドライン(https://www.jpm.jp/topics/72785)等を参考にしてください。
設備のメンテナンスと更新を欠かさない
設備の故障による家賃減額を防ぐためには、定期的なメンテナンスや設備の更新が欠かせません。定期的に設備の点検を行うのはもちろん、入居者が退去したタイミングで計画的に設備の更新を行いましょう。適切なメンテナンスを行うことで、設備の故障リスクを抑え、家賃減額の発生を防げます。
設備不良・故障時の対応を賃貸借契約書に明記する
トラブルを未然に防ぐためには、設備の故障について賃貸借契約書に明記しておくことも重要です。主要な設備が故障した場合に備え、ガイドラインを参考にしながら、減額割合や免責日数をあらかじめ具体的に盛り込んでおきましょう。契約書に明記しておくことで、入居者との見解の相違を防げます。
管理会社や保証サービスを活用する
管理会社と故障時の対応について、事前に打ち合わせしておくことも重要です。修理を行う際には、軽微な工事であればオーナーへの確認をしないなど事前に決めておくことでスピーディーに対応できます。また、設備の故障に対して保証してくれるサービスや、家賃減額を補償する保険などもあります。保険や保証サービスを活用することで、経営リスクを軽減することが可能です。
まとめ

賃貸アパートの設備が故障した際、入居者に非がなく免責期間を超えても改善しない場合の責任はオーナーにあります。そのため入居者の生活に支障が出る場合は、家賃の減額が認められています。
設備不良による家賃減額のリスクを下げるためには、定期的な設備のメンテナンスをすることが重要です。また、賃貸借契約に設備の故障時の対応について盛り込むことで、トラブルを未然に防げます。
設備不良による家賃減額を防ぐためにも、日々の対応と事前の対策が不可欠です。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
久保田 克洋
不動産業界に20年以上従事。賃貸管理を中心に管理受託業務・売買仲介・民泊運営を担った幅広い知識と経験をベースに、現在はプロパティマネジメント・アセットマネジメントを担っている。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
石塚 佳穂
新卒で不動産会社に入社後、一貫して賃貸管理業務に従事。オーナーが所有する物件の価値向上に取り組み、実務経験を積んできた。現在は、セミナーやキャンペーンの企画・立案など、マーケティング業務にも携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!