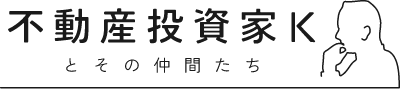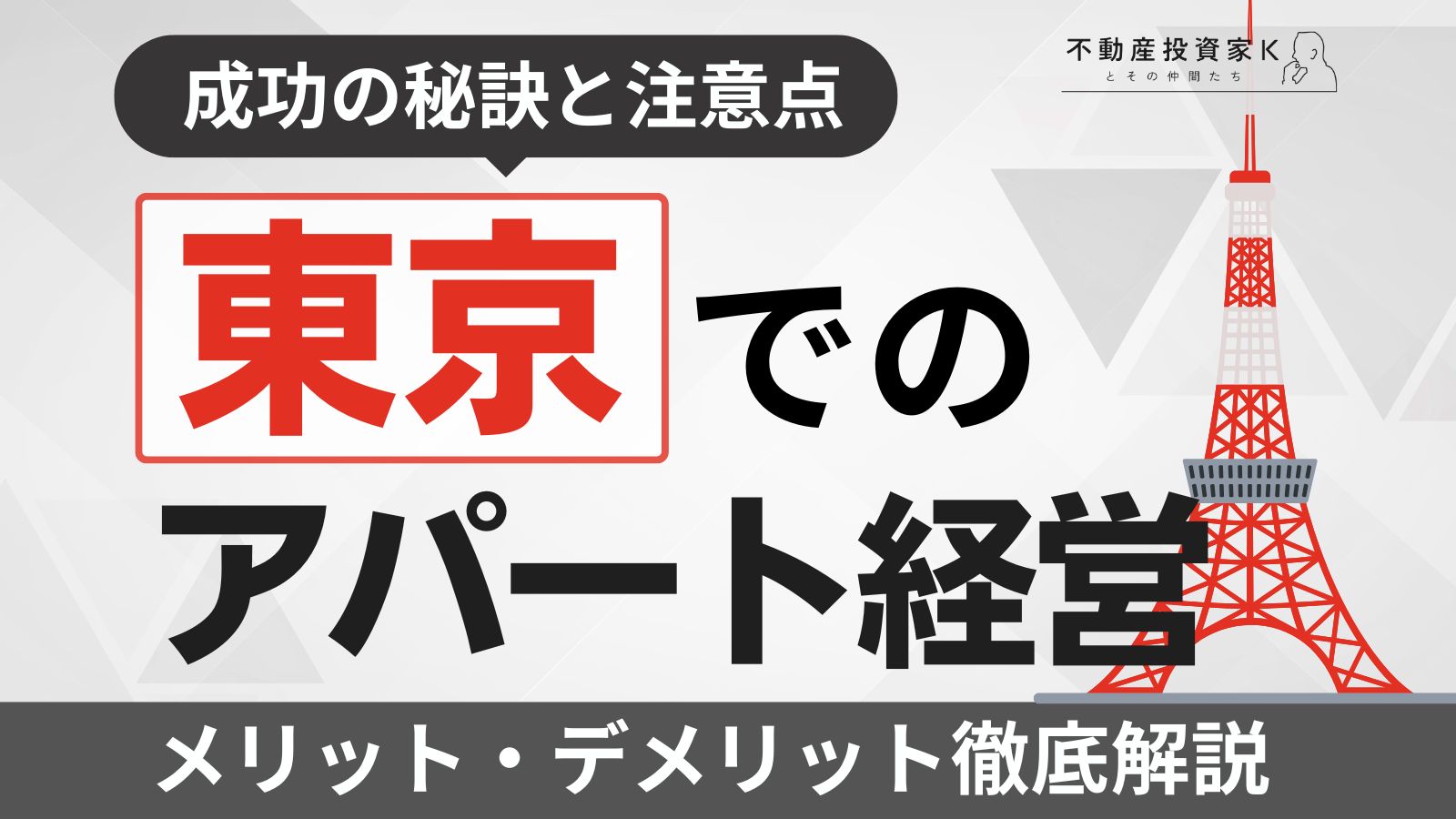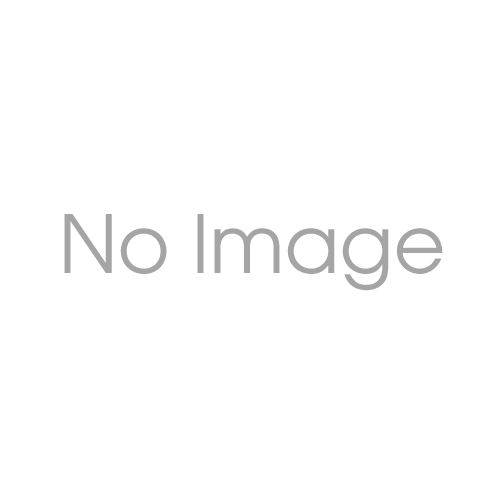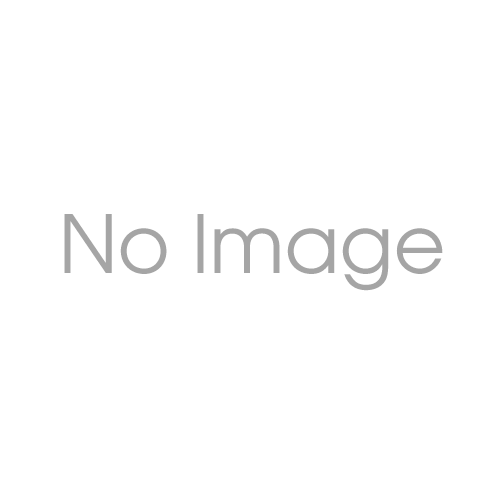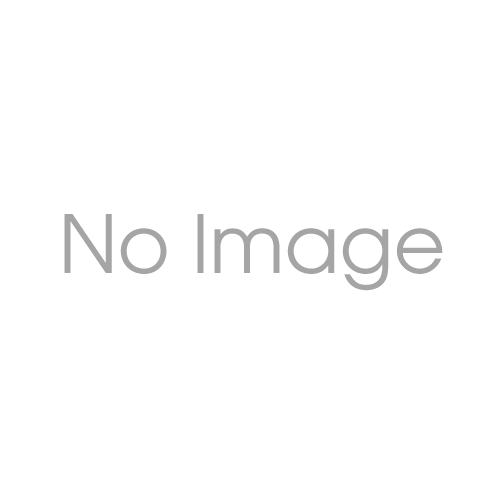
賃貸人は賃借人に対し、物件を使用・収益させるべき義務を負っており(民法第601条)、物件に不具合や故障が発生した場合には、適切に使用・収益ができるように修繕しなければなりません。修繕義務の範囲には個別判断が必要なことも多々あり、ケースごとの把握が必要です。
本記事では、賃貸人の修繕義務の範囲や設備が故障した場合の対応、賃貸人が負うリスクとその予防策について解説します。
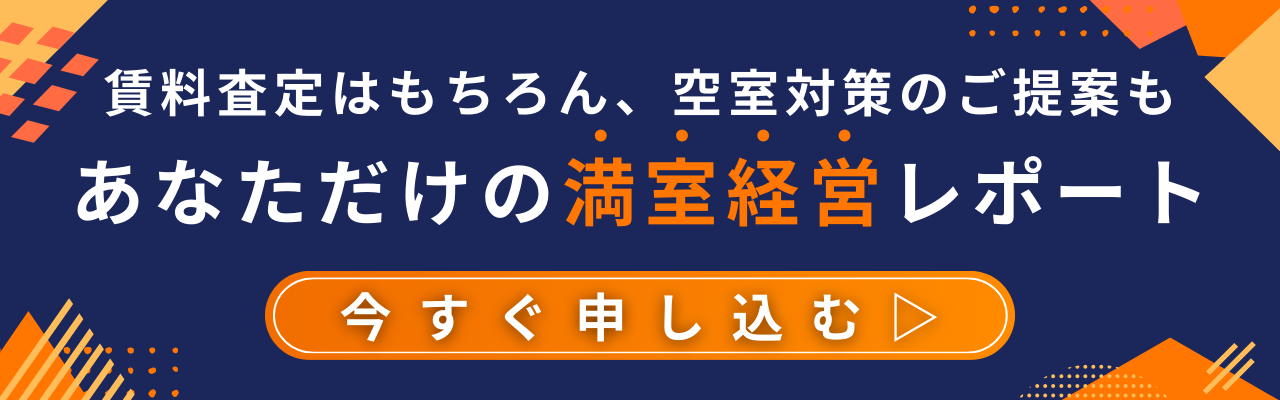
ポイント
- 賃貸人は、賃借人が賃貸物件について契約の目的に従った使用・収益をできるようにする義務を負う
- 設備が故障した場合の修繕義務は「初期設備」と「残置物」で異なる
- 設備故障による賃貸人が負うリスクと予防策について理解が必要
賃貸人の修繕義務とは?

賃貸人の修繕義務とは、賃借人が賃貸物件を通常どおり使用・収益できるように、建物や設備を適切な状態に保つ責任のことです。
民法第601条では、賃貸人は賃借人に物件を使用・収益させる義務を負うと定められています。これに基づき、建物や設備に不具合が発生した場合、基本的には賃貸人が修繕対応を行わなければなりません。
ただし、賃借人の通常の利用範囲を超えた使用によって損傷が生じた場合には、その修繕責任は賃貸人に及ばないとされています。
修繕義務の範囲

賃貸人には賃貸物件に対して一定の修繕義務が課されていますが、その具体的な範囲については、状況によって見解が分かれます。
ここでは、賃貸人が負う修繕義務の基本的な範囲と、契約内容やトラブルの内容によって個別に判断が必要となるケースについて解説します。
基本的な修繕義務の範囲
賃貸人の修繕義務がどこまで及ぶかは、「修繕をしないと、賃借人が契約の目的に従った使用・収益ができなくなるかどうか」で判断します。
基本的に、屋根・外壁の破損や給排水設備・電気・ガスなど、生活に欠かせない設備の故障については、賃貸人が修繕義務を負います。たとえば、水漏れや壁のひび割れ、ドアの不具合など、通常の使用によって生じた劣化は、賃貸人の負担により修繕する必要があります。
ただし、賃貸人の修繕義務の内容は当事者間の合意により変更することができるため、契約書で修繕の範囲や負担区分が具体的に定められている場合は、その内容が優先されます。
「どこまで修繕しなければならないか」という修繕の程度に関しては、最低限、居住の用を満たすだけの修理をすれば足り、利便性の高い最新の設備に変更する必要はありません。
天災など不可抗力の場合
地震や台風、大雨による土砂災害といった天災で賃貸物件に不具合や故障が発生した場合、「賃貸人の修繕義務が発生する」というのが裁判所の見解です。
台風等によって屋根が破損し、雨漏りが発生した事案について、「不可抗力であっても、使用・収益に支障が生じた場合は賃貸人に修繕義務がある」という判断が示されています。
そのため、天災など不可抗力によって賃貸物件が契約に定められた目的に従って使用・収益できない状態になったとき、賃貸人は修繕を行わなければなりません。
ただし、修繕義務はあくまで任意規定であり、異なる特約を設けることは可能です。不可抗力による損傷の場合に賃貸人は修繕義務を負わない旨を定めている場合、特約に賃借人の合意があれば、賃貸人は修繕義務を免れることになります。
また、不可抗力で特約のない場合でも、賃借人の故意または過失によって損傷が生じた場合、賃貸人の修繕義務が否定される可能性があります。
費用が高額になる場合
賃貸人に修繕義務があるケースでは、修繕に高額な費用がかかる場合もあります。金額によっては、賃料の金額に照らして採算がとれないこともあるでしょう。
費用が高額になる場合でも修繕義務を負うかが争われた事案で、裁判所は賃貸人の修繕義務を否定しています。
本来、賃貸人が負う修繕の責任は、賃借人が支払う賃料と釣り合う形で成立するものであり、賃貸物件の資産的な価値と賃借人が不具合によって受ける不便の程度を比較して判断されるというのが裁判所の見解です。
そのため、賃料額に照らし不相当に高額の費用を要する場合、賃貸人は修繕義務を負わないと判示しています。
賃借人の故意・過失に基づく場合
賃貸人には、賃借物件を使用可能な状態に維持する義務がありますが、賃借人自身の故意または過失によって物件が損傷・滅失した場合まで、その修繕義務を負わせるのは合理的ではありません。
そのため、賃借人自身が故意過失によって物件を毀損または滅失させた場合、賃貸人の修繕義務が免除されるか、修繕義務の範囲が小さくなる可能性があります。
実際の判例では、賃貸物件に備え付けのエアコンに軽微な水漏れがあったにもかかわらず、そのまま使用していた結果、水漏れが悪化して壁の一部が腐食し修理が必要になったケースにおいて、賃貸人の修繕義務が否定されています。
賃借人がエアコンの不具合(水漏れ)があることに気づいていながら賃貸人にそのことを告げず、放置して被害が拡大した場合、賃借人には民法第400条に基づいて善管注意義務違反の問題が生じるというのが判決の理由です。
賃貸物件で設備が故障した場合の修繕義務

エアコンや給湯器などの設備について賃貸人が修繕義務を負うかどうかは、それらが「初期設備」か「残置物」かによって変わります。
初期設備とは「最初から部屋などに備え付けられている設備」のことで、残置物は「前の入居者が設置した設備」を指します。
ここでは、賃貸物件の設備が故障した場合の賃貸人の修繕義務について、それぞれのケースに分けてみていきましょう。
設備が備え付けの場合
初期設備はもともと賃貸物件に備わっている設備であり、キッチン・トイレ・ドア・蛇口などが該当します。エアコンや給湯器も、はじめから備え付けられていれば初期設備です。
これらは賃貸人が所有するものであり、通常の使用によって故障した場合は、賃貸人が修繕義務を負います。
賃貸人が初期設備の修繕義務を負わないようにするには、賃貸借契約書において、特約として「これらの設備は賃貸人が修繕義務を負わない」「修繕は賃借人が行う」といった旨を明示しなければなりません。
ただし、このような特約が有効と認められるには、賃借人がその内容を十分に理解したうえで合意していることが求められます。
賃借人が備え付けた場合
前の入居者が設置した設備は「残置物」として扱われ、賃貸人には原則として修繕義務がありません。
特に、前の入居者が残していった設備については、募集時に「設備」として掲載してはいけないことが、不動産業界の慣例およびガイドラインで定められています。誤って「設備」として表示すると、修繕責任が生じるおそれがあるため注意が必要です。
また、現賃借人が持ち込んだ設備は賃借人の所有物であり、そもそも修繕が必要な「物件の不具合」には該当せず、賃貸人に修繕義務は発生しません。
残置物をめぐるトラブルを避けるためには、その取り扱いを契約書などで明確に定めておくことが重要です。
一般的に前の入居者が残した残置物の扱いは、「無償貸与」または「無償譲渡」のいずれかに分類されます。
無償貸与の場合、所有権は賃貸人にあり、賃借人が修理や処分を行うには事前に賃貸人の承諾が必要です。
一方、無償譲渡の場合は、所有権は賃借人に移るため、自由に修理・処分することができます。賃借人の希望に応じて、退去時に賃貸人が引き取ることも可能です。
設備が故障した場合の対処法

賃貸人が修繕義務を負う設備に不具合が生じた場合、その対応方法は「自主管理している場合」と「管理会社に管理を委託している場合」とで異なります。
それぞれのケースに応じた対処法について、具体的に解説します。
賃貸人が管理している場合
賃貸人が直接管理している賃貸物件で設備の故障が発生した場合、対応フローは次のとおりです。
- 1.
- 賃借人が、故障の内容を賃貸人に直接連絡する
- 2.
- 賃貸人が状況を確認し、必要に応じて修理業者を手配する
- 3.
- 修理業者が現地で点検・修理を実施する
- 4.
- 修理完了後、賃貸人が修理費用を負担する
対応フローを円滑に進めるためには、賃貸人と賃借人の間で迅速な連絡手段を確保しておくことが大切です。電話やLINEなど即時に対応できるツールを活用すれば、トラブルの早期解決につながります。
なお、2020年の民法改正により、設備の一部が使えなくなった場合、賃料はその使用不能部分の割合に応じて当然に減額されることになったことに注意が必要です。
賃料減額については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
あわせて読みたい
管理会社に管理を委託している場合
賃貸物件の管理を管理会社に委託している場合の対応フローは、次のとおりです。
- 1.
- 入居者が管理会社に連絡する
- 2.
- 管理会社が内容を確認し、必要に応じて賃貸人に報告・承諾を得る
- 3.
- 管理会社が修理業者を手配し、訪問日時を調整する
- 4.
- 修理完了後、賃貸人が費用を負担する
水漏れや鍵の不具合など、早急な対処が求められることもあります。こうした緊急対応については管理委託契約で事前に取り決めがなされているケースも多いでしょう。
明確な規定がない場合には、一定の判断を管理会社に任せられるようにしておくとスムーズな対応につながります。
設備故障で賃貸人が負うリスクとは?

賃貸人には、物件内の設備に関して修繕義務が課されているため、設備の故障によってさまざまなリスクが生じる可能性があります。
これらのリスクを事前に正しく把握し、適切に備えておくことが、安定した賃貸経営を続けるうえで重要です。
ここでは、賃貸人が負う可能性のある主なリスクについて解説します。
修繕義務による費用負担
賃貸人は、修繕責任を負う設備について、常に予期せぬ出費のリスクを抱えています。設備は経年劣化だけでなく、自然災害や突発的なトラブルによっても突然不具合が発生することがあり、その修繕には数万円から数十万円規模の高額な費用が必要になることも少なくありません。
特に、エアコン・給湯器・水回りといった生活インフラに関わる設備が故障した場合は、入居者の暮らしに直結するため、迅速かつ的確な対応が求められます。
こうした事態に備え、賃貸人には計画的なメンテナンスと修繕費用の備えが重要になるでしょう。
賃料減額請求権の発生
賃貸物件に備え付けられている設備に不具合が生じた場合、入居者から賃料の減額を求められるリスクが生じます。
民法改正により、設備の故障などで物件の一部が使用・収益できない状態となった場合、賃借人の請求がなくても、使用不能となった範囲に応じて自動的に賃料が減額されることが法律上明文化されました。
改正前は「賃料の減額を請求できる」にとどまっていたのに対し、改正後は当然に賃料が減額されることになり、賃貸人側にとってより厳しい内容となっています。
対象となるのは、単なる「一部滅失」にとどまらず、「使用が事実上困難になった場合」も含まれ、たとえばエアコンや給湯器の故障、水漏れなども賃料減額の原因となり得ます。
こうしたリスクを軽減するためには、賃貸借契約書に「設備の不具合が発生した場合は、速やかに賃貸人へ通知し、協議のうえ対応を決定する」といった条項を盛り込むことが望ましいでしょう。
居住者からの損害賠償請求
賃貸人が必要な修繕を怠った場合、物件を使用・収益するという本来の賃貸借契約の目的が達成されません。その結果、賃貸人は契約上の義務を果たしていないとみなされ、「債務不履行」として扱われる可能性があります。
このような状態が続くと、賃借人から契約違反を理由に修繕の履行を求められたり、損害賠償を請求されたりすることもあるでしょう。さらに深刻なケースでは、訴訟に発展して賃貸人が法的責任を負う事態に発展するおそれもあります。
訴訟にまでは至らなくとも、賃借人が不満を抱き、国民生活センターや弁護士、不動産の専門窓口などに相談するケースが想定されます。こうした相談を契機として、自治体や関係行政機関から賃貸人に対して改善を促す「行政指導」が行われることがあるでしょう。
行政指導は法的拘束力のある命令ではなく、あくまで是正を促す任意の指導にとどまるため、すぐに罰則や制裁が科されることはありません。ただし、指導に従わずに問題を放置し続けた場合には、悪質と判断されて行政処分などの法的措置に発展する可能性もあります。
特に近年は、入居者保護の観点から行政の対応が厳格になる傾向があるため、賃貸人としては迅速で誠実な対応が求められます。
賃貸契約の解除
賃借人から修繕の要望があったにもかかわらず、賃貸人が迅速かつ適切に対応しない場合、「修繕義務の不履行」と判断されるおそれがあります。
このような状況が続けば、賃借人は賃貸借契約の継続が困難であると主張し、正当な理由に基づいて契約を解除したり、物件を退去したりする可能性があります。
特に、給湯設備や水回り、空調機器など生活インフラに関わる設備の不具合が長期間放置された場合には、賃借人の退去が「正当事由に基づく解除」として法的にも認められやすくなるでしょう。
その結果、空室期間が発生して賃料収入が減少するだけでなく、新たな入居者募集にかかる経費や原状回復費用などの負担も増大します。
また、トラブルの対応遅れは物件の評価や賃貸人としての信頼性の低下にもつながるため、経済面・信用面の両面で損失を招くリスクがあります。
リスク回避に向けた賃貸人の予防策

修繕義務に関して起こりうるリスクを回避するためには、設備点検や迅速な連絡体制の整備など、あらかじめ予防策を講じる必要があります。
リスク回避に向けた予防策について、詳しく解説します。
定期的な設備点検・メンテナンス
給湯器やエアコン、水回り設備などの住宅設備は、経年劣化や使用頻度によって不具合が生じやすく、放置すると入居者の生活に支障をきたすだけでなく、賃貸人としての修繕義務を怠ったと判断されるおそれがあります。
これらのリスクを未然に防ぐためには、計画的・定期的な点検とメンテナンスの実施が欠かせません。
計画的な点検のためには、設備ごとに点検時期の目安を設け、以下のような定期スケジュールを組んで管理することが大切です。
- 給湯器:10年を目安に点検・交換を検討
- 水回りの設備:配管の詰まりや水漏れの兆候を定期的にチェック
- 電気設備:コンセントや照明の不具合、漏電のリスクを定期的にチェック
- 外壁や屋根の状態:ひび割れや塗装の劣化を確認
- 防災設備:法定点検に基づき、消火器・火災報知器の有効期限や動作状況を半年に1回確認
- 排水設備:年1回の高圧洗浄や詰まりの有無の確認
「音がうるさい」「水漏れが少しある」「温度調節にムラがある」などの軽度な不具合でも放置せず、早めに修理することで、設備全体の寿命を延ばすことができます。後回しにすると修繕費用が膨らむ可能性もあるでしょう。
日常的に使用する設備については、賃借人からの「異音」「水漏れ」などの報告が初期トラブル発見の手がかりになります。入居時や定期案内で、異常を感じた場合はすぐに連絡するよう案内しておくことも効果的です。
建物管理会社や設備メンテナンス業者などの専門業者と定期契約を結ぶという方法も有効です。専門的な視点による年次点検を実施することで、見落としを防ぎ、異常の早期発見が可能になります。点検記録を残しておけば、万一の際の説明責任にも対応できるでしょう。
定期的かつ計画的な点検と保守管理は、入居者満足度の向上にもつながります。長期的には、空室リスクの低下や修繕費の抑制にも寄与するでしょう。
迅速な連絡・修繕体制の整備
リスク回避のため、設備の故障に迅速に対応できる体制を整えておくことも重要です。特に夏場のエアコンや冬場の給湯器など、季節要因で利用頻度が高まる設備は、トラブルが賃借人の生活に直結し、クレームや退去の原因になりやすいため注意が必要です。
以下のような予防策を講じておくと、緊急時にもスムーズに対応できます。
- 連絡体制の整備
- 設備ごとの修理業者の事前選定
- 対応履歴の記録
トラブル時に賃借人がすぐに連絡できるよう、緊急連絡先を契約書や掲示などで明確にしておきます。管理会社を通じて24時間対応の窓口を設けると、安心感が高まるでしょう。
エアコン、給湯器、水回り、鍵など、よくあるトラブルの内容に応じて、それぞれ対応可能な業者をあらかじめリストアップしておくことも有効です。契約や覚書を交わしておくことで、緊急時にすぐ依頼できます。
また、過去のトラブルや対応内容を記録・共有しておくことで、次回以降の対応がスムーズになります。修繕傾向を把握できるため、予防にもつなげることもできるでしょう。
こうした体制を整備しておくことは、賃借人の満足度向上や信頼関係の維持につながり、退去防止や長期入居の促進にも効果的です。
住宅設備の保証サービスや保険への加入
設備の保証サービスや家財保険、借家人賠償責任保険に加入して、急な出費に備えることも大切です。
具体的には、以下のような備えがあると安心材料になるでしょう。
- 設備保証サービスの活用
- 火災保険・家財保険・借家人賠償責任保険の加入
- 緊急対応費用特約の付帯
設備保証サービスとは、エアコンや給湯器など特定の住宅設備について、故障時に無料または定額で修理・交換できるサービスです。特に築年数が経過した物件では故障リスクが高いため、導入しておくと突然の修繕費負担を軽減できます。
また、賃借人に火災保険(家財保険・借家人賠償責任保険)への加入を義務づけるだけでなく、賃貸人自身もオーナー向け保険に加入しておくとよいでしょう。
賃借人が借家人賠償責任保険に入っていても、補償されるのは賃借人の過失が問われる場合のみです。不審火や自然災害などについては賃貸人が修復しなければならず、速やかな修復が求められます。オーナー向け保険に加入していれば、これらの支出に対応可能です。
保険によっては、鍵の紛失、水漏れなど緊急対応の出動費用がカバーされる「緊急駆け付けサービス」が付帯しているものもあります。こうしたサービスを利用することでトラブル発生時の手間を軽減でき、入居者対応もスムーズになるでしょう。
保証や保険で修繕のリスクに備えることで、賃貸人の金銭的負担や精神的負担を軽減できるほか、賃借人にとっても安心して暮らせる環境を提供できます。
まとめ

賃貸人には、賃貸物件を適切に使用・収益できる状態に維持する義務があり、通常の使用によって発生した不具合や経年劣化による故障については、原則として賃貸人が修繕費用を負担します。
ただし、賃借人の故意・過失による損傷や、高額修繕が必要な場合など、修繕義務の範囲が制限されるケースもあります。
また、設備が「初期設備」か「残置物」かによって修繕の責任が異なるため、契約時に明確な区分と合意が欠かせません。
修繕義務を怠ると、賃料減額や契約解除、損害賠償などのリスクにつながるため、的確な対応と事前の予防策が大切です。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
久保田 克洋
不動産業界に20年以上従事。賃貸管理を中心に管理受託業務・売買仲介・民泊運営を担った幅広い知識と経験をベースに、現在はプロパティマネジメント・アセットマネジメントを担っている。

監修者
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
石塚 佳穂
新卒で不動産会社に入社後、一貫して賃貸管理業務に従事。オーナーが所有する物件の価値向上に取り組み、実務経験を積んできた。現在は、セミナーやキャンペーンの企画・立案など、マーケティング業務にも携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!