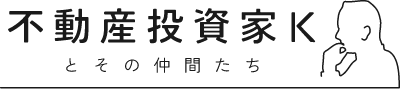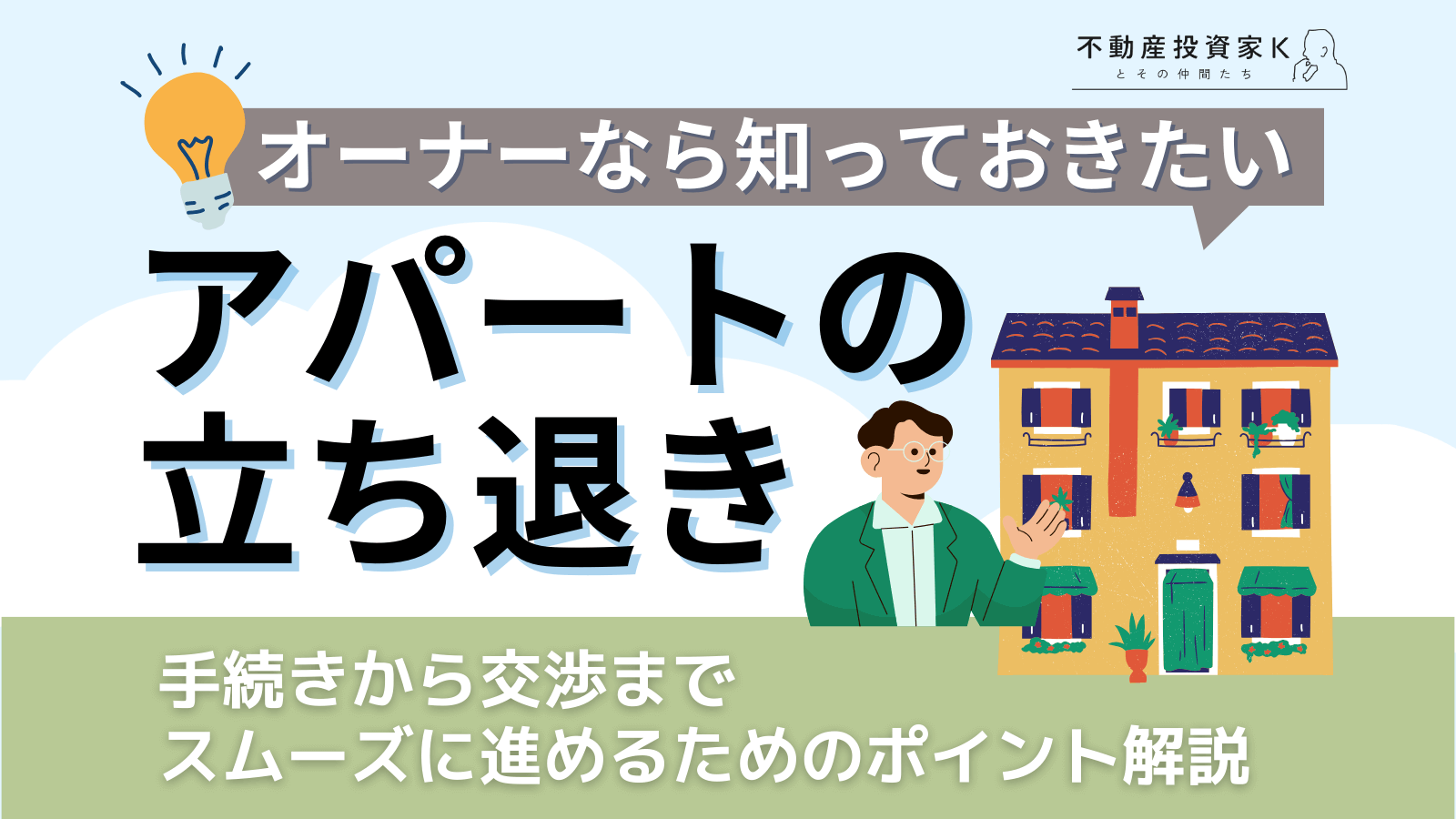
立ち退きとは、さまざまな事情により賃貸物件から出て行ってもらう行為を指します。アパートの立ち退きをスムーズに進めるには、なるべく早い段階から立ち退き交渉を行うことが大切です。
本記事では、アパートの立ち退きをスムーズに進めるための手続き、立退料の相場、交渉する際に抑えておくべきポイントを解説します。
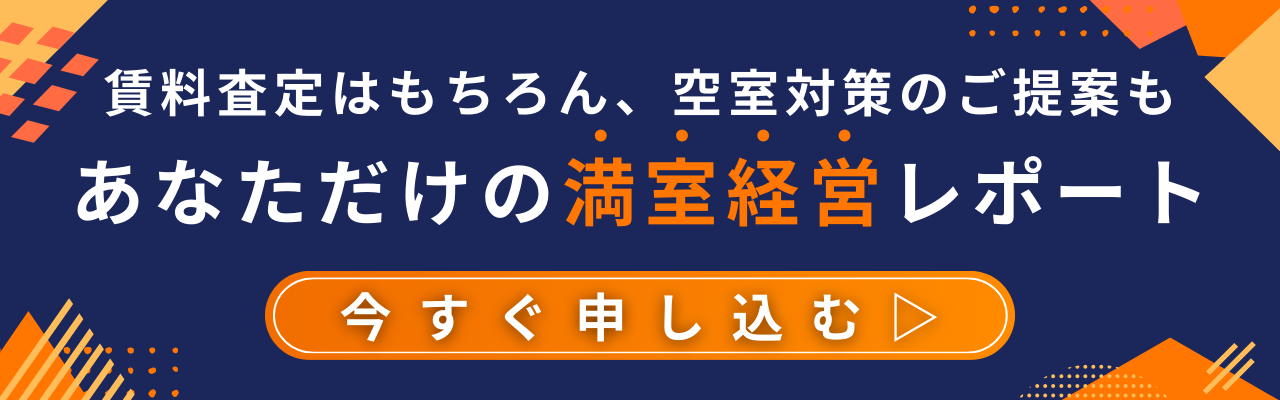
ポイント
- 住居の立ち退き交渉を行えるのは賃貸人もしくは弁護士
- 住居の立ち退き交渉は賃貸契約満了の6カ月〜1年前までに行う必要がある
- 立ち退きは必要性や正当な事由がなければ認められない
- 立ち退き料は当該者同士の合意で決める
立ち退きとは

立ち退きとは、賃貸契約を結んでいる賃借人に賃貸物件から退去を求めることです。たとえば、賃貸物件の老朽化により建て替えをしたいときに、誰か1人でも賃借人がいる場合はすぐに建て替えができません。そんなときに交渉して退去してもらう行為のことを立ち退きといいます。また、大前提として、立ち退き交渉は非弁行為に該当するため、弁護士または賃貸人しか行えないため注意が必要です。
立ち退きを求める場合は正当な理由が必要

いくら賃貸人に立ち退きを求める権利があるとしても、賃借人にとっては生活の根幹を揺るがす大問題です。そのため、賃借人の居住権は、法律によって保護されています。
立ち退きを求める際には、法律に則っていることはもちろん、納得のいく正当な理由を説明する必要があります。
ここでは賃貸人が立ち退きを求める際の正当な理由になり得る事情を解説します。
定期借家契約の契約期間が満了した
借家契約は定期借家契約と普通借家契約の2種類に分けられます。そのうち定期借家契約であれば期間満了に伴い契約は終了するため、立ち退きを求められます。
定期借家契約とは、契約期間を定めた借家契約です。契約の「更新」を前提にしておらず、更新する場合は双方の同意が必要で、その場合でも新たに契約を締結することになります。賃借人が更新を希望しても賃貸人はそれを拒絶することができ、契約期間満了を持って契約を解除できます。
しかし、普通借家契約の場合、契約期間そのものが設定されていないため、立ち退きには正当な理由が必要です。無条件に立ち退きを求めることはできません。
参考:e-GOV 借地借家法
賃借人が契約違反や問題行動を起こしている
賃借人が賃貸借契約に違反している場合や、違反ではなくとも問題行動を起こしている場合は、立ち退きを求める正当な理由になり得ます。
契約違反や問題行動に該当するのは次のようなケースです。
- 長期間、家賃を支払っていない
- 賃貸人や管理業者、ほかの賃借人に重大な迷惑行為がある
- 物件を犯罪行為に使用している
- 物件を許可なく第三者に又貸ししている など
契約違反ではない問題行動は、賃貸借契約における賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊するほど深刻である場合に限られます。
たとえば、苦情が出るほどの騒音や、ゴミ捨てのルールを守らない程度の理由では認められないケースが多い傾向にあります。
建物の老朽化などで居住し続けることが難しい
建物が老朽化し、継続して居住するには危険な場合も、立ち退きを求める正当な理由として認められます。
老朽化は賃貸人の責任ではなく、建物の物理的な寿命としてどうしても避けられない現象です。たとえば建物が損傷している、浸水で居住できない、耐震性能が大きく劣るといった場合が該当します。
また台風や洪水、地震といった災害による損壊や劣化も立ち退きの正当な理由です。専門家が「修繕困難である」「改修工事を必要とする状況だが技術的・経済的に実行できない」などと判断された場合が該当します。
再開発などで建物を取り壊す必要がある
都市計画やインフラ整備などの再開発プロジェクトのエリア内にある建物の取り壊しが必要となる場合は、外的要因は所有者の責任ではないため、立ち退きの正当な理由として認められています。
再開発が公表されると計画した自治体が関係住民に対して説明会を開き、立ち退きの必要性を伝え、立ち退き料や新たな住居の紹介といった補償内容を提示します。
再開発は地域の発展を目指すためのプロジェクトですが、同時に立ち退きを余儀なくされる住民が不利益を被らないような配慮が欠かせません。
大家や大家の家族が賃借中の物件に住む必要がある
大家や大家の家族が、賃借中の物件に住まざるを得ない場合も、立ち退きの理由として認められることがあります。
ただし、「なぜ貸主がその物件を必要としているのか」といった正当な理由が必要です。通例では、次のようなやむを得ない事情がある場合に認められやすいといわれています。
- 経済的な余裕がないため一般の賃貸住宅に居住できない
- 介護が必要な家族の住宅と近い
- 通院する病院が近い
- 子どもの学区を変えたくない など
参考:弁護士法人エジソン法律事務所 立ち退きとは?|正当事由や立ち退き料についてわかりやすく解説
立ち退きに伴う補償と立ち退き料

賃貸人の都合により立ち退きを行う場合は、基本的に立ち退きに伴う補償と立ち退き料の支払いが必要です。立ち退きに伴う補償には、住居の場合は借家権の補償です。
借家権とは、賃貸借契約によって得られる賃借人の権利です。経済的価値のある財産権を1つ失うため、これを補填するための料金を補償します。
立ち退きに伴う補償と立ち退き料は、どんなケースでも必要なわけではありません。
- 賃貸物件に老朽化が差し迫った危険がある
- 入居者が契約違反を犯している
- 定期建物賃貸借契約期間の満了
上記に該当する場合は、立ち退きに伴う補償と立ち退き料なしで手続きを進められます。
賃貸住宅の立ち退き料の相場
立ち退きに伴う補償と立ち退き料は、具体的な金額の取り決めはありませんが、一般的には住居の場合は家賃6カ月〜1年分が相場とされています。
ただし、賃貸人と賃借人の関係性や交渉の行方によって、金額は増減する可能性が高いです。裁判例では、家賃5〜10万円程度の老朽化が進んだマンションの立ち退き料が200万円程度と算出された事例もあります。
立ち退きがなければ本来住み続けられたことを考慮し、移転先でも移転前と同じように生活ができるような金額を検討するようにしましょう。
立ち退き料の内訳
立ち退き料には、主に以下が含まれます。
- 移転にかかる費用
- 新居の初期費用
- 通信環境の整備費用
- 慰謝料
移転にかかる費用は、荷物の梱包や運搬、家具の処分など、引越しにかかる費用を指します。新居の初期費用とは、移転先の家賃、敷金、礼金、仲介手数料、保険などです。通信環境の整備費用には、新居に新たな電話回線を引いたり、インターネットの通信費用などがあります。
慰謝料は移転する手間や住む環境の変化によるストレスを考慮した費用です。
賃借人に対して立ち退き料が発生しないケース
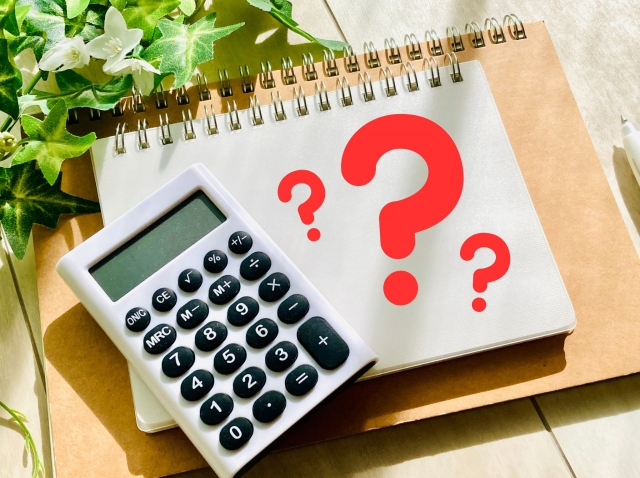
賃貸物件からの立ち退きを求められても、立ち退き料が発生する場合と発生しない場合があることにも注意が必要です。
ここでは立ち退きの際、立ち退き料が発生しないケースを4つ見てみましょう。
立ち退き料が発生しないことに合意した場合
賃借人が「立ち退きの際、立ち退き料を受け取らない」ことに合意している場合、立ち退き料は発生しません。具体的には、契約の際に建物の老朽化等の現状を鑑みて合意する場合や、契約中に賃貸人と協議し合意した場合などが該当します。
また、一旦は合意していても後で「十分な説明がなかった」などと主張し、立ち退き料を請求される可能性もあるため、契約時に双方が署名・押印した「合意契約書」のような書面を作成しておくことが重要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、賃借人には事前にしっかり説明し、理解と同時に納得を得ることが必要です。
債務不履行解除が発生した場合
債務不履行が原因で契約解除が発生した場合、立ち退き料は発生しません。
債務不履行とは、契約で交わしたさまざまな債務、つまり守らなければならない責任を守らないことです。たとえば「月の末日までに翌月分の家賃を指定の口座に振り込む」や「物件を無断で他人に又貸ししない」などが債務にあたります。
賃借人が上記のような契約違反など債務不履行に該当しているのであれば、賃貸人は賃貸借契約の債務不履行解除が可能です。ただし家賃の滞納であれば「3カ月分」が1つの目安といわれており、1カ月程度であれば契約解除は認められません。3カ月以上滞納していれば、解約または更新を拒絶できる可能性が出てきます。
契約期間の満了により立ち退きを行う場合
建物を一定期間に限って賃貸借する「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」の契約期間満了で立ち退く場合も、立ち退き料は発生しません。定期借家契約は、契約更新がない契約であるため、特に事情がなくても契約関係を終了できます。
ただし、定期借家契約には次のような要件が必須です。
- 「建物」の賃貸借契約であること
- 契約期間を明記すること
- 書面によって契約すること
- 期間満了により賃貸借契約を終了する旨が明記された書面を賃貸人が交付し説明すること
災害や老朽化などで建物の利用が危険な場合
災害や老朽化などの理由で建物を利用するには重大な危険がある場合、賃貸借契約を終了する理由として認められるため立ち退き料は不要とされます。
ただしこの状況に該当するのは、たとえば、地震による損壊、居住するには危険な耐震性能の低下、大雨や洪水による浸水などです。まれなケースではあるものの、近年では、さまざまな地域で「数十年に一度」といわれるほどの災害が発生しています。あまり考えたくないですが、災害など不可抗力の場合は立ち退き料が発生しないきちんと把握しておきましょう。
立ち退き手続きの流れ

立ち退き手続きは、以下の流れで行います。
- 1.
- 立ち退きの通知
- 2.
- 立ち退きの交渉
- 3.
- 退去の手続き
万が一、交渉が決裂した場合には裁判に発展することもあります。手続きについて詳しく解説します。
立ち退きの通知
まずは立ち退き依頼を書面で通知しましょう。立ち退きの通知は、契約期間満了の1年〜6カ月前までに行う必要があります。
また、期間を守っていたとしても、正当な事由がなければ立ち退きは認められません。送付する書面は、「解約申し入れの通知」または「更新拒絶の通知」です。契約期間中に契約を解除する場合は「解約申し入れの通知」、契約満了時に引き続き契約しないようにする場合は「更新拒絶の通知」を送ります。
決まった書式はありませんが、以下の内容を含むようにしましょう。
- 契約当事者
- 契約内容
- 通知書提出日
- 契約締結日
- 解約予定日
- 解約理由
書面は弁護士などの専門家に任せても、自分で作成したものでも構いません。
立ち退きの交渉〜期限と条件
立ち退きは書面で通知するだけではなく、対面でも交渉することが大切です。書面で通知してから早い段階で対面での交渉日を調整しましょう。
対面で交渉する際は、立ち退きの理由を書面よりも具体的に説明すると、賃借人に納得してもらいやすくなるでしょう。
立ち退きの交渉で注意すべき点は、嘘の理由を伝えたり隠しごとをしないことです。賃借人が不信感を抱き、交渉が決裂する恐れがあるため、気をつけましょう。
退去の手続き
正当な事由により、立ち退きが認められた場合は、退去の手続きに進みます。ただし、必ずしも正当な事由がある場合のみが退去の手続きに進めるわけではありません。もし法律上の正当な事由がなくとも、賃貸人と賃借人の話し合いによって合意が得られれば、立ち退きが認められます。
たとえば、立ち退き料を支払うことで、立ち退きに合意した場合などが当てはまります。
交渉が決裂する場合は裁判に
立ち退き交渉が決裂する場合は、調停または裁判をすることになります。調停では調停委員が間に入り、当事者間の話し合いで和解を目指す方法です。調停でも解決が見込めない場合は、裁判に進みます。
裁判で争点となるのは、主に以下の2点です。
- 正当事由が認められるか
- 立ち退き料の金額が妥当か
下される判決は、「妥当な立ち退き料を渡し、当該不動産を引き渡す」または「当該不動産の明け渡しを棄却する」のどちらかです。もし立ち退きを認める判決が下されたにも関わらず、明け渡さない場合は強制執行することができます。
立ち退き交渉のポイント

立ち退きは賃借人にとって負担が大きく、交渉が難航することがあります。また、金銭的な問題も絡み、トラブルになりやすいでしょう。
そのため、立ち退き交渉をスムーズに進めるには、ポイントを押さえておくことが大切です。立ち退き交渉におけるポイントについて解説します。
交渉の前に押さえておくべきポイント
交渉の前に押さえておくべきポイントとして、以下の3点があげられます。
- 立ち退きの必要性と正当事由を把握しておく
- 譲歩できる点を検討しておく
- 借地借家法を理解しておく
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
立ち退きの必要性と正当事由
立ち退く必要性がなければ、立ち退きは原則認められません。たとえば、賃貸物件を自分や家族が使用するために立ち退きを求める場合、他に多くの不動産や土地を所有していないことや当該土地が必要な理由が必要です。
また、立ち退きには正当な事由が必要だと、借地借家法の第28条により定められています。正当な事由とは、以下のような場合が該当します。
- 賃貸物件の老朽化による取り壊し
- 賃貸物件の建て替え
- 賃借人が賃貸物件をゴミ屋敷にした
- 賃借人が長期間にわたり家賃を滞納している
老朽化により住み続けていると危険な場合や築年数が古く、現在の耐震基準を満たしていない場合、賃貸人が契約違反行為をした場合、賃貸契約を継続することが難しい場合などは、正当な事由として認められる可能性が高いです。
ただし、病気や失業により家賃が払えない場合などは、やむを得ない事情があると正当な事由として認められないこともあります。
賃借人の都合により立ち退きを求める場合は、払う経済力はあるにも関わらず、故意に家賃を支払わないなど、賃貸人と賃借人との信頼関係が崩壊したと言えるほどの理由が必要です。
譲歩できる点を検討しておく
賃借人にも都合があるため、譲歩できる点を検討しておきましょう。たとえば、以下のような例があげられます。
- 原状回復請求の放棄
- 立ち退きの時期は相手の希望を尊重する
- 立ち退き料を前払いする
本来であれば、賃借人がゴミ屋敷にした場合は、賃借人が責任を取り、原状回復の費用を支払うべきです。しかし、予想外の立ち退きにより費用が用意できない可能性もあります。
円滑に立ち退きを進めるためには、原状回復請求を放棄することも検討しましょう。特に取り壊して建て替える場合は、原状回復の必要はありません。
また、立ち退きの時期はなるべく早い方が良いと思うかもしれませんが、賃借人は新しい住居を探す期間が必要です。立ち退く時期はなるべく賃借人の希望するタイミングを受け入れましょう。
さらに、新しい移転先の敷金や礼金などの初期費用が払えず、立ち退きが難しい場合もあるかもしれません。立退料の一部を前払いすることで、資金繰りが楽になるでしょう。
借地借家法を理解しておく
借地借家法は土地や建物の貸し借りについて定められたもので、賃借人に有利な法律です。 普通賃貸借契約を結んでいる場合、契約期間が満了したからといって、賃貸人が強制的に立ち退きを行うことはできません。
また、賃借人に騒音がうるさいからなどといった理由で退去を求めたとしても、裁判により正当な事由と認められなければ退去させることは難しくなります。
もし裁判に発展した場合でも、借地借家法により裁判所は賃借人を守ろうとするでしょう。
立退料についても、賃貸人の希望の金額に寄せられてしまうことが多くあります。
こうした前提を踏まえて、立ち退き交渉を行うことが大切です。
代替物件を提案する
立ち退く場合、賃借人は移転先を探さなければなりません。しかし、探す時間があまり持てなかったり、地域によってはすぐに見つからなかったりするケースもあります。
特に住居の場合は移転先が見つからないと、大きなストレスになるでしょう。賃貸人が複数の物件を所有している場合は、代替物件にあっせんするなど、移転先を提案してあげると立ち退き交渉が円滑に進みやすくなります。
代替物件を提供する場合は、なるべく現在の生活環境を変えなくて済む物件を用意しましょう。
交渉内容を書面に残す
交渉で取り決めた内容は、書面に残すのが安心です。口約束では時間が経過すると、曖昧になり、トラブルが起こる可能性があります。
書面には、以下の内容を記しましょう。
- 賃貸契約解除の合意
- 立ち退き料の金額
- 立ち退き料の支払い日
- 物件の明け渡し日
- 残存物の取り扱い
- 契約終了後の使用損害料の金額
- 返還すべき敷金の金額
これらは賃貸人と賃借人との話し合いによって、取り決めます。また、書面は双方が保管しておくようにしましょう。
誠意をもって対応する
近年では、立ち退き料が貰えるケースがあることを知っている賃借人が多いでしょう。そのため、最初から立ち退き料を支払うつもりがないというスタンスでのぞむと、賃借人の反感を買って交渉が長引くうえに金額が膨らんでしまう恐れがあります。
対面で交渉する際に、ある程度の補償はさせていただきますといったように、物腰低く打診することで、無用なトラブルを避けることにもつながるでしょう。
立ち退きはアパート経営・法律のプロに相談する

立ち退きをアパート経営・法律のプロに相談する方法もあります。プロに相談すると費用はかかりますが、知識や経験が豊富であるため、交渉を短期間で終わらせ、賃貸人の精神的なストレス軽減にもつながります。プロにすべてを任せるのではなく、アドバイスを受ける形で利用するのも可能です。 たとえば、自分が立ち退きを求める理由が正当な事由として認められるかどうかや立ち退き料の相場を知らない方が多いのではないでしょうか。
プロにアドバイスをもらえば、立ち退き料の大体の金額などを詳しく知ることができ、安心して交渉を進められます。スムーズに立ち退きを進めるには、早い段階でプロに相談しましょう。
また、最初にお伝えしたとおり、実際の立ち退き交渉は非弁行為に該当するため、弁護士または賃貸人しか行えない点は注意しておきましょう。
まとめ

アパートの立ち退きは、立ち退きの通知、立ち退きの交渉、退去の手続き、同意に至らない場合は調停や裁判といった手順で進めます。
スムーズに立ち退き手続きを進めるには、早い段階で通知しておくことが大切です。立ち退き依頼を通知する目安は、契約更新日の6カ月〜1年程度前と言われています。
立ち退きは賃貸人に大きな負担を与えるため、自分の希望ばかりではなく、譲歩できる点を検討し、賃貸人に寄り添うことが円滑に立ち退きしてもらうポイントです。
スムーズにかつストレスなく立ち退きを進めたい場合や安心して交渉を進めるためには、プロに相談するのも良いでしょう。

監修者
宅地建物取引士
長谷川 昌彦
関東・関西を中心に、不動産・建築業に従事し30年以上。賃貸仲介・管理業務をはじめ不動産売買・仲介業務全般、分譲住宅の仕入・企画・販売、収益物件土地・建物の仕入・販売等、幅広い経験を持つ。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「アパートに空室が増えてきた」「管理会社の対応に不満がある」「建物が老朽化してきた」など、アパート管理に関するお悩みをお持ちのオーナー様のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!