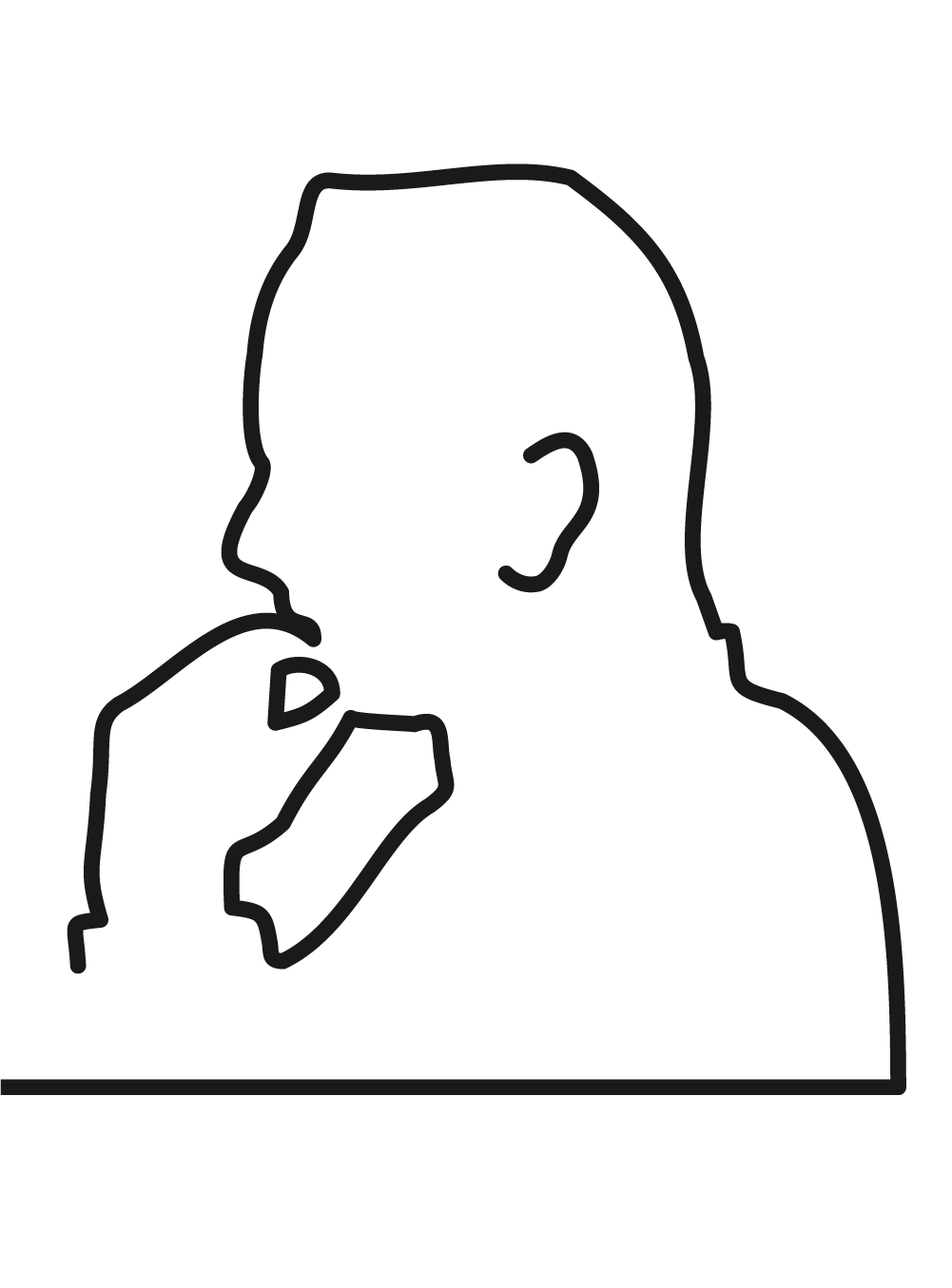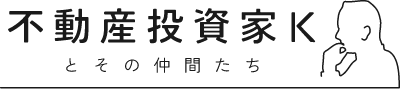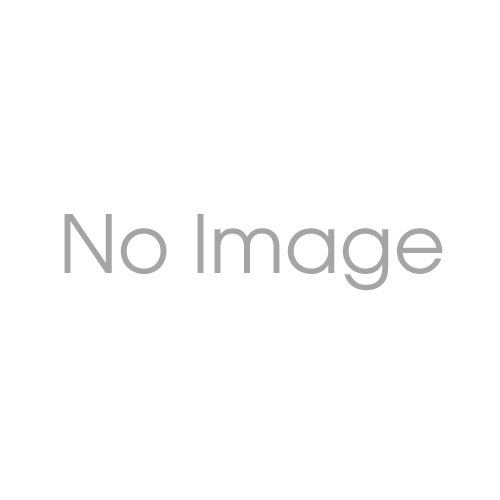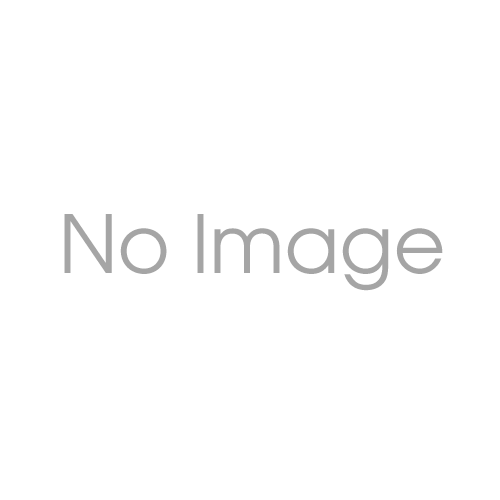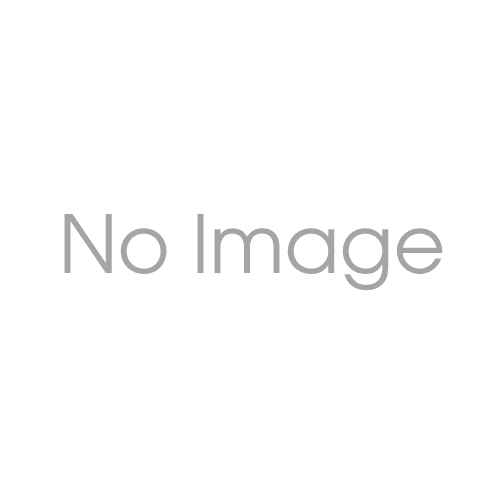
アパート経営のオーナーが確定申告をする場合には、経費として計上できるものとできないものがあることに注意が必要です。
今回は、アパート経営をする際の確定申告の経費を詳しく解説します。確定申告が必要なケースや実施したほうがお得なケース、経費で落とせるかどうかの基準などをチェックしていきましょう。
ポイント
- アパート経営に関係するかが経費となる基準
- 正しい確定申告をすることで節税対策になる
アパート経営で確定申告が必要・不必要なケース
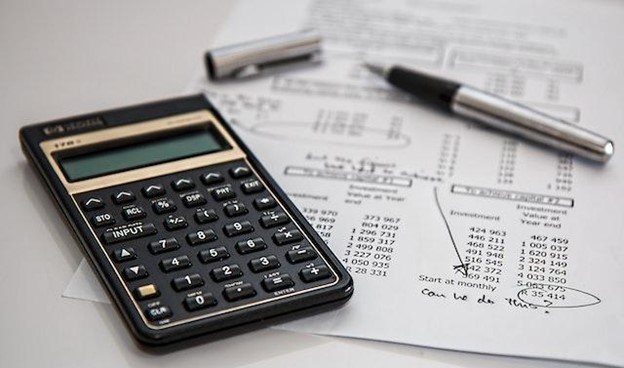
アパート経営のオーナーには、不動産所得による確定申告が必要なケースと不要なケース、実施したほうがお得なケースの3つのパターンがあります。はじめに、確定申告をする必要があるのかどうかについて、不動産所得の観点からチェックしていきましょう。
確定申告が必要なケース
一般的な確定申告が必要な場合の条件には、「給与収入が2,000万円を超える人」や「公的年金等の収入が400万円以上の人」などがあります。アパート経営のオーナーにとって確定申告が必要かどうかを判断する際は、会社から受け取る給与や公的年金など以外の所得が20万円を超えるかどうかです。
つまり、不動産所得を含め、源泉徴収されていない部分の所得が20万円を超える人は、所得税の確定申告をする必要があります。したがって、アパート経営をしている人は、確定申告が必要になるケースに含まれる人が多いでしょう。
確定申告した方がお得なケース
必要経費として認められる経費のみを差し引いた状態で、不動産所得が20万円以下になる人であっても、確定申告した方がお得なケースがあります。不動産所得が赤字になっていて、そのほかに所得がある場合であれば、損益通算ができるため確定申告した方がお得になるのです。
不動産所得と給与所得などを合算して確定申告を行うことで、不動産所得として赤字であった金額の分だけ課税所得を少なく申告できます。課税所得が少なくなると所得税や住民税の節税が可能なため、不動産所得が赤字になった場合、確定申告するのがおすすめです。
アパート経営で経費で落とせる・落とせないの基準
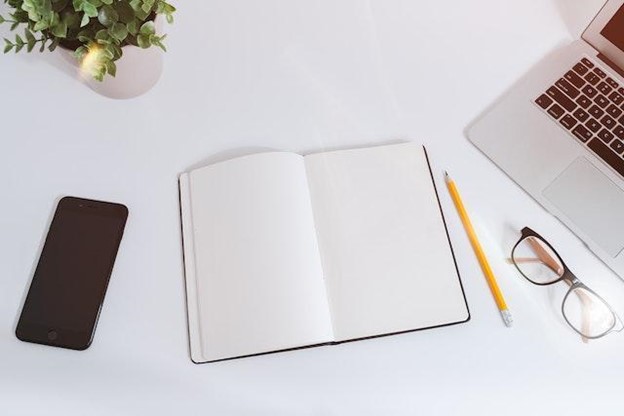
アパートオーナーが不動産所得の確定申告を行う際には、必要経費として計上できるものとできないものがあります。必要経費として計上できるものはどのような費用で、どのような違いがあるのか、その基準について詳しくチェックしていきましょう。
アパート経営に直接関係している費用なのか
必要経費になる基準の1つが、アパート経営に直接関係しているのかどうかです。「共用部の修繕費」や「管理費」などはアパート経営に直接関係のある費用のため、経費として計上できます。しかし、プライベートでの食事代金などは経費には認められません。
その経費がアパート経営にどのように寄与するのかなど使用の目的も問われるため、アパート経営に直接関係のない費用を計上しないように注意しましょう。
アパート経営用の金額を明確に区別できるか
必要経費かどうかの判断ポイントとして、金額を明確にアパート経営のものであると区別できることが大切です。たとえば、租税公課、管理費、通信費、借入金利息、交通費、新聞図書費などについては、アパート経営の金額を明確に区別可能であれば経費として計上できます。
しかし、アパート経営に関係があるものの、プライベートのためにも使っている費用もあるものです。この場合には、アパート経営で必要な割合を明確に区別できるようであればその割合から経費として挙げられる金額を算出しましょう。これを家事按分といいます。
こちらの記事もおすすめです
アパート経営、引継ぎか売却か? 相続前に確認すべきポイント
減価償却費
減価償却とは、時間の経過や使用などにより価値が変わる建物や設備などに対する会計処理のことです。アパートの購入金額のうち建物部分の購入金額を法定耐用年数(木造アパートの場合は法定耐用年数22年)で割った金額を分割して、毎年経費として計上します。アパート経営で必要経費として落とせるもののなかでも、とくに割合の大きな費用です。
管理費・管理委託費
管理費とは、エレベーターなどの設備点検費用や清掃費用、保守管理費用などのことです。自分で管理した場合だけではなく業者に委託した場合にも経費として計上可能で、委託した業者に支払う場合には管理委託費などといいます。
修繕費
アパートの修繕のために、必要となった費用も経費として計上可能です。たとえば、退去時のクリーニング代や壊れたキッチンの修理、排水溝の修理、定期的な外壁の塗装などが含まれます。
ただし、もしも修繕により建物本体や設備の価値を高められたり使用可能期間が長くなったりする場合には資本的支出と考え、建物として資産計上し、建物の耐用年数で減価償却しましょう。
あわせて読みたい
損害保険料(火災保険料など)
アパート経営をする際は、施設賠償保険や火災保険、地震保険などの損害保険料についても経費として計上が可能です。1年ごとの費用であればそのまま計上し、複数年契約の場合には1年ごとの費用を計算して計上しましょう。
共有部分の水道光熱費
共有部分の水道光熱費も、アパート経営の際の経費として計上可能です。たとえば、共有部分に置かれた防犯カメラの電気代などが共有部分の水道光熱費にあたります。各居室で使った水道光熱費は入居者負担です。
入居者募集時の仲介手数料
アパート経営で空室が発生した場合、通常は不動産会社に入居者の募集を依頼します。入居者募集で仲介してもらうために支払った仲介手数料は、経費として計上可能です。
ちなみに、不動産会社が仲介手数料として受け取れる金額は、賃料の1カ月分が上限です。宅建業法によるルールであるため、1カ月分以上を支払う必要はありません。
集客に使った広告宣伝費
集客のための広告宣伝費も、アパート経営の際の経費として計上できるもののひとつです。具体的には、入居者の集客のために不動産会社に依頼した際の費用や自身で集客するために使ったパンフレット費用などが含まれます。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに発生する税金です。一般的に所有権移転の登記をしてから約4カ月〜1年ほど経過した時期に、自治体から納付書が送付されます。
不動産取得税の税額は、固定資産税評価額の4%ですが、特例により標準税率が軽減されます。
- 土地と住宅:3%(2027年3月31日まで)
- 住宅以外の家屋:4%
アパート経営で発生した不動産取得税は、経費として計上できます。
参考:千葉県 不動産取得税の納税通知書はいつ頃届きますか。
兵庫県 不動産取得税について
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記手続きの際に国に納付する税金のことで、土地と建物の両方とも課税されます。登録免許税が課税されるのは、主に以下のケースです。
- 土地の所有権移転登記(売買・相続など)
- 建物の所有権保存登記
- 抵当権の設定登記
登録免許税の税額は、土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。登録免許税も経費計上が可能です。
印紙税
印紙税も経費として扱える支出の1つです。アパートを売買する際に締結する契約書には、収入印紙を貼ることが義務付けられています。
印紙税の税額は契約金額によって変動し、たとえば契約額が1千万円を超え5千万円以下の場合は2万円、1億円を超え5億円以下の場合は10万円です。
固定資産税
固定資産税とは、土地・家屋・償却資産などの固定資産を持っている人が、固定資産の価値に応じて負担する税のことです。固定資産税も、アパート経営において経費として計上できます。
固定資産税額は、課税標準額に税率1.4%を掛けて算出します。土地には住宅用地の軽減措置が適用され、一定の割合で減額されます。
参考:総務省 固定資産税
都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充当するため、目的税として課される税金で、アパート経営の経費となります。
毎年1月1日時点の都市計画で指定されている市街化区域内の不動産のオーナーが都市計画税の対象です。都市計画税の基本税率は0.3%で、固定資産税評価額に基づいて算出した課税標準額に掛けることで税額が算出されます。
金融機関に支払う事務手数料
不動産の取得で金融機関から融資を受ける場合、金融機関側に事務手数料を支払うことになり、その事務手数料は経費に計上できます。
事務手数料は定額制と定率制の2種類があります。定額制は3万円〜5万円程度、定率制はローン金額に一定の率を掛けた金額です。
定額制は金額負担が軽くなるケースが多いですが、ローン金利が高い、保証料が別途必要など、定率制のほうが有利になる場合もあります。
保証会社に支払う保証料
多くの金融機関は、保証会社との契約を融資の条件としています。融資を保証してくれる保証会社へ支払う保証料は、経費として計上できます。
保証料の支払方法には、融資を受ける際に一括払いする方法、返済時に保証料を含めて支払う方法の2つがあります。一括払いする場合、保証料は融資総額の1%~2%程度が相場です。
青色事業専従者給与
青色申告による確定申告をしていて、かつ、事業的規模と認められるときは、アパート経営に携わる家族がいる場合、「青色事業専従者給与」として経費にできます。青色事業専従者給与とは、「申告者と生計を同一にしている配偶者または15歳以上のその他の親族への給与」のことです。
青色申告をしていて、かつ5棟10室以上のアパートである場合、青色事業専従者給与を経費とすることが可能です。
あわせて読みたい
給料・賃金
アパート経営で従業員を雇用している場合、従業員への給料賃金も必要経費として扱えます。ただし、経費として認定されるには、相応の労働を伴っていることが条件です。
必ず実際に雇用している方のみ経費計上するようにしましょう。
新聞図書費
アパート経営において、情報収集用に購入した新聞や図書・資料などの購入代金は、費用として計上可能です。不動産系・投資系の業界新聞、アパート経営を学習するための書籍などが例としてあげられます。
経費として扱えるのは事業に直接関係のあるものだけです。無関係の出費を含めないように注意しましょう。
地代・家賃
借地でアパート経営をしているケースにおいては、地代も経費として扱えます。他の方が所有する物件を借りて、転貸をしてアパート経営をする場合も、支払っている家賃を経費にすることが可能です。
注意点として、土地や建物の所有者が家族ではなく、他人である必要があります。生計を一にしている家族から借りている場合、地代や家賃は経費として認められません。
立ち退き料や解体費
新たなアパートを建てるために、物件を解体する解体費と入居者に退去してもらうために支払った立ち退き料も、経費に計上可能です。ただし、投資用のアパートの建て替えでないと、経費として認められません。
たとえば解体の目的が所有者自身が住むための自宅への転用である場合、アパート経営で利益を得る目的ではないため、経費にはなりません。
アパート経営とは関係がない交通費
アパート経営とは関係がない交通費も、経費として計上できません。アパート経営に関連して使った電車賃などであれば計上できますが、プライベートで使った交通費は含められないため注意してください。
修繕積立金
修繕積立金も、積み立てたタイミングでは経費にできません。修繕積立金とは大規模修繕を行う際のために積み立てていくお金のことです。実際に修繕をする際に、かかった費用について修繕費として計上します。
アパート経営とは関係がない消耗品費
消耗品費とは、事業活動で使用する消耗品や消耗性のある資材に関する支出です。耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、文房具や備品などの代金が該当します。
アパート経営で使う消耗品であれば経費にできますが、無関係のものは経費にできません。自宅などプライベートで使う消耗品費を含めないよう注意しましょう。
不動産の購入代金
アパートや土地を購入するための代金を、必要経費にできないかと考える方もいるでしょう。しかし、自己資金として用意する頭金、融資でまかなった分のいずれでも、経費として認められません。
不動産の購入代金は、貸借対照表上の「資産」を得るための支出です。「資本的支出」にあたり、費用ではないため、経費として計上することはできません。
団体信用生命保険特約料
団体信用生命保険(団信)とは、契約者が万が一の事故や病気によって、ローン返済ができなくなった場合、返済義務が免除される保険です。金融機関からローンを借りる場合、団体信用生命保険への加入が義務とされるケースもあります。
団体信用生命保険への加入は、自分の身に万が一のことがあった場合への備えです。アパート経営で収益を得るために必要な支出ではないため、アパート経営における必要経費とはなりません。
固定資産税清算金
毎年1月1日時点の所有者はその年の固定資産税や都市計画税を納める義務があるため、売主からすると不動産を売却した年は実際には所有していない期間の税金も払っていることになります。固定資産税清算金とは、売主が払いすぎてしまう税金を、買主が負担するために売買価格に上乗せされるものです。
固定資産税精算金は税金を調整するためのやりとりですが、不動産の売買価格への上乗せという形をとります。よって、不動産購入代金と同様、経費として計上することは不可能です。
アパート経営での節税ポイント

アパート経営をすると、さまざまな税金の軽減制度を受けられます。そのため、アパート経営における節税は、ポイントを適切に理解したうえで確定申告などをすれば可能です。
赤字経営になってしまったときには、損益通算することで所得税や住民税を節税できますし、相続税や贈与税の節税効果もあります。
最後に、アパート経営での節税のポイントをチェックしていきましょう。
経費をもれなく計上する
不動産所得税の申告時に、収入から経費を差し引いた所得に税金がかかります。経費を計上するほど所得が少なくなり、その分税金が安くなりますので、アパート経営の経費をもれなく計上することが節税のポイントです。
経費計上によって不動産所得税がどれほど変化するのか、以下の例でシミュレーションをしてみましょう。
- 木造アパート(ワンルーム10室)
- 年間不動産収入:600万円
- 年間の経費:180万円
経費を差し引いた課税所得金額は420万円で、所得税は420万円×0.2-42万7,500=41万2,500円です。一方、経費を差し引かないと課税所得が600万円のため、所得税は600万円×0.2-42万7,500=77万2,500円となります。
経費を計上することで、所得税の税額を抑えられることがわかります。
参考:国税庁 「No.2260 所得税の税率」
損益通算を活用する
損益通算とは、収益を別の損失で通算することによって、相殺することです。たとえば500万円の収益を200万円の損失と通算すると、300万円に減らせます。
不動産所得では損益通算が認められており、損失を他の黒字となっている収益と合算して課税所得を計算することが可能です。アパート経営の場合、給与所得など不動産所得以外の所得から、不動産事業の赤字分を差し引くことにより、所得税や住民税を減らせます。
損益通算を活用すると、給与所得から源泉徴収されている所得税が還付されることがあります。ただし、不動産所得でも土地などの取得に関する借入金の利子部分は対象外のため注意しましょう。
法人化する
アパート経営の規模が大きくなり、収入も増加してくると、法人化も視野に入ってきます。法人は個人よりも経費の範囲が広がるため、計上できる経費がより多くなる場合があります。
法人化することで利用できる経費の例として、役員報酬があります。収入から経費を引いた不動産所得を、会社から社長への役員報酬として支給すると、会社の所得は0円になり、法人税は課税されません。
社長が受け取る役員報酬には所得税がかかるものの、申告の際には給与所得控除が適用されるため、課税所得は減ります。また、家族を役員として在籍させると、その分も役員報酬として経費にすることが可能です。
さらに、法人化すると赤字の繰り越し期間も長くなります。個人の場合は最大3年間ですが、法人にすると10年間の繰り越しが可能です。
あわせて読みたい
複数の業者に問い合わせをする
適切に節税をしながらアパート経営をするには、経費にできるものを事前に把握しておくことが大切です。しかし、所有者の努力だけですべて判断するのは困難でしょう。アパート経営に精通している建築会社やアパートメーカーなどをパートナーとして選定することも重要です。
信頼できるアパートメーカーや建築会社を見つけるには、まず複数の会社に問い合わせをしましょう。会社が提示する収支計画・初期費用・ランニングコストをチェックし、他の会社と比較することで、現実性の高い会社を選べます。
税理士に相談する
青色申告や法人化など、節税するためのポイントはさまざまなものがあります。経費に関する知識がきちんと身に付いていない場合、節税対策ができずに損をする可能性があるでしょう。
また、税務署から指摘が入ってしまうケースもあります。節税対策などを行うには、税理士に相談することをおすすめします。
アパート経営の確定申告の手順

初めて確定申告をする場合、何をどうすればいいのかわからなくて難しそうと感じるかもしれません。まず、確定申告には、5つのステップがあることを把握することが大切です。
確定申告の方法や流れを、5つのステップで解説します。
1:青色申告承認申請書の提出
確定申告には青色申告と白色申告があり、どちらで行うかを決めます。青色申告をする場合は開業から2カ月以内に「青色申告申請書」を提出する必要があるなどの条件があります。
青色申告のメリットは、特別控除として最大65万円の控除を受けられることです。収入から最大65万円が差し引かれるため、所得税や住民税の節税ができます。
一方、複式簿記で帳簿付けをする必要があるため、白色申告よりも簿記に関する知識が必要です。帳簿付けをサポートする機能のある会計ソフトなどを使うとよいでしょう。
青色申告承認申請書を入手するには、所轄の税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードする必要があります。必要事項を記入した後、税務署の窓口に提出するか郵送をします。
また、e-Tax(電子申告)で提出することも可能です。
2:提出書類の準備
次に、確定申告で提出する書類を準備していきます。具体的には以下のとおりです。
- 請求書
- 源泉徴収票
- 控除証明書
- 各種明細書
- 領収書
- レシート
これらは売上・仕入・経費・控除などを証明するための大切な書類です。取得方法や時期などは異なりますので、抜けや漏れのないよう準備しましょう。
売上や仕入の請求書は、客先・仕入先ごとにまとめましょう。領収書やレシートなどは、「消耗品費」「交通費」など勘定科目ごとにまとめます。
また、確定申告書の提出時には、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカードの表面と裏面のコピー、持っていない方は番号確認書類(通知書など)と身分証明書(運転免許証など)を用意しましょう。
3:収入や経費の計算
3つ目のステップは、アパート経営で得た収入や発生した経費の計算です。前年の1月1日〜12月31日に発生したアパート経営の収入と経費を計算しておく必要があります。
確定申告の受付期間は、毎年2月16日〜3月15日の1カ月間で、この期間に間に合うように計算する必要があります。日頃から帳簿付けを進めておくことで、ゆとりを持って準備できるでしょう。
青色申告では、複式簿記による帳簿付けが必須です。簿記の知識も学びながら、帳簿付けに取り組みましょう。
4:確定申告書類の作成
収入や費用の計算が終わると、確定申告書類の作成に進みます。確定申告書の様式は国税庁の公式サイトでダウンロードできるほか、税務署や市町村の窓口でもらったり、税務署から郵送してもらったりすることで入手可能です。
帳簿付けで会計ソフト・アプリを使用している場合、確定申告書の作成にも対応しているケースが多いため、ソフトやアプリを使って作成できます。
また、国税庁公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」では、画面の項目に従って必要事項を入力するだけで書類を作成できます。
5:確定申告書類の提出
確定申告書類が完成したら、提出して完了です。提出方法は、税務署への持参、税務署への郵送、e-Taxの3種類があります。
持参または郵送で提出する場合は、アパートを経営するオーナーの居住地を管轄する税務署へと提出する必要があります。物件のエリアを管轄する税務署ではないので、間違えないように注意しましょう。
国税庁による電子申告・納税システムの「e-Tax」を利用すれば、インターネットで確定申告書類の提出が可能です。e-Taxを利用するには、利用者識別番号や電子証明書の取得が必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。
まとめ
アパート経営について、どのくらいの不動産所得で確定申告が必要になるのか。また何が経費になるのかの基準や、具体的な経費となる項目などについて触れ、正しい確定申告が節税になることを説明しました。
アパート経営のオーナーには、不動産所得による確定申告が必要なケースと不要なケース、実施したほうがお得なケースの3つのパターンがあります。アパート経営のオーナーにとって確定申告が必要かどうかを判断する際は、会社から受け取る給与や公的年金など以外の所得で20万円以上あるかどうかです。
つまり、不動産所得を含め、源泉徴収されていない部分の所得が20万円以上ある人は、確定申告をする必要があります。
必要経費になる基準は、アパート経営に直接関係しているのかどうか、アパート経営用の金額を明確に区別できるかどうかです。節税につながるため、経費として認められるものを確認し、しっかりと計上するようにしましょう。
監修者
澁谷 有紀枝
- 資格
- 税理士
- 略歴
- 外資系税理士法人に長く勤務した後、主に外資系企業で会計、税務を担当。2020年8月より不動産会社の経理部にて月次、年次決算、申告業務に携わっている。

監修者
中川 祐一
- 資格
- 宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 略歴
- 現在、不動産会社で建築請負営業と土地・収益物件の仕入れを中心に担当している。これまで約20年間培ってきた、現場に密着した営業経験と建築知識、不動産知識を活かして業務に携わっている。