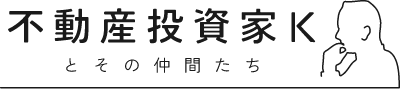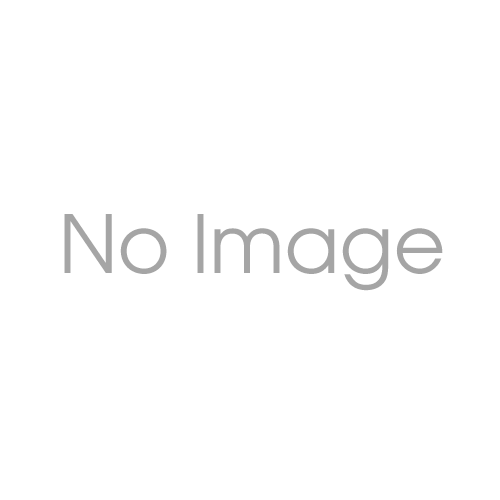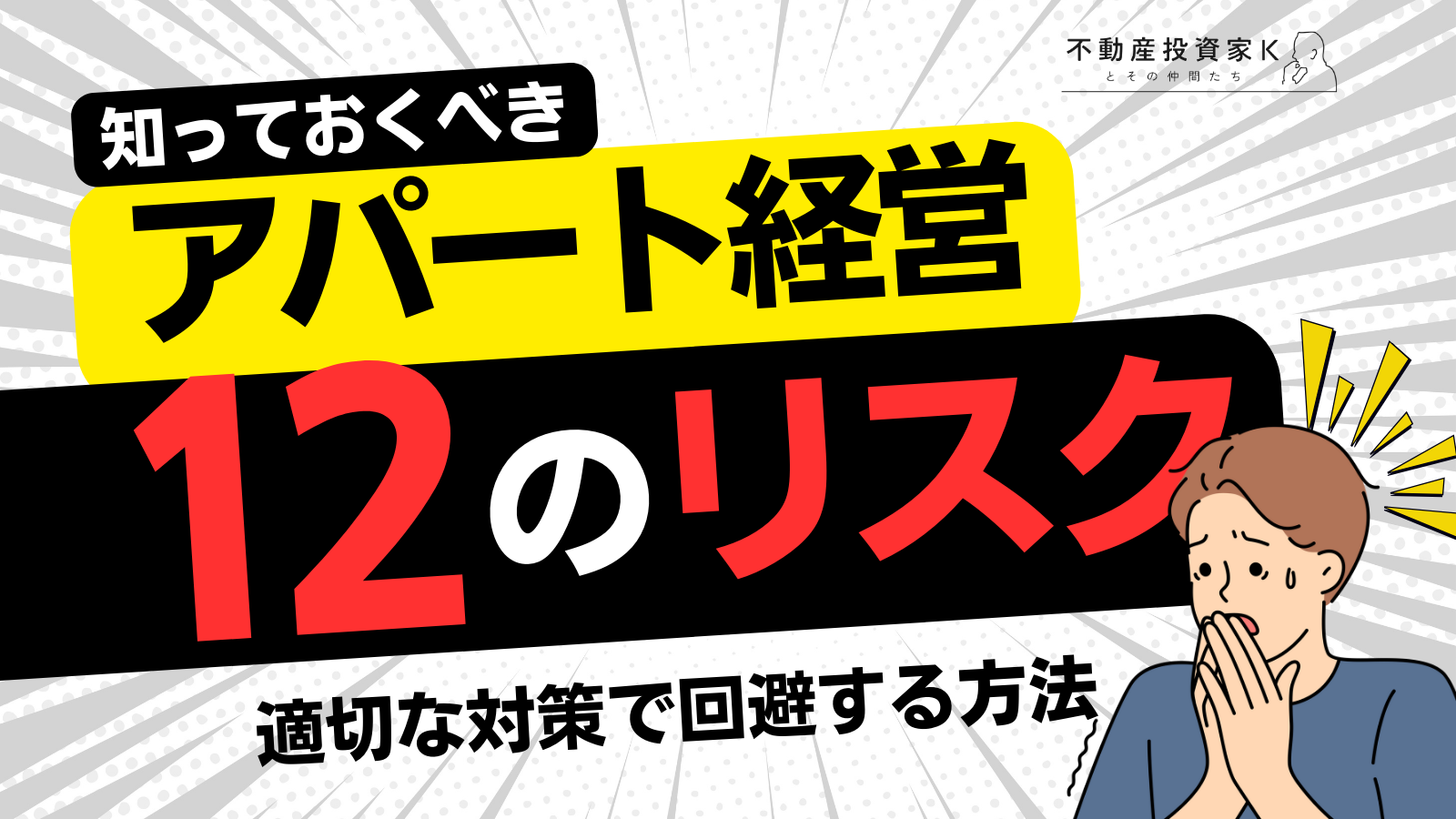
アパートを経営する場合、空室リスクや家賃の下落リスクなど、さまざまなリスクがあることを知っておかなければなりません。アパート経営にはリスクがありますが、市場調査をはじめ適切な対策を実施すれば、これらのリスクを軽減できます。
本記事では、アパート経営の12のリスクと対策について解説します。また、アパート経営に失敗しやすい人の特徴もまとめています。ぜひ最後までご覧ください。
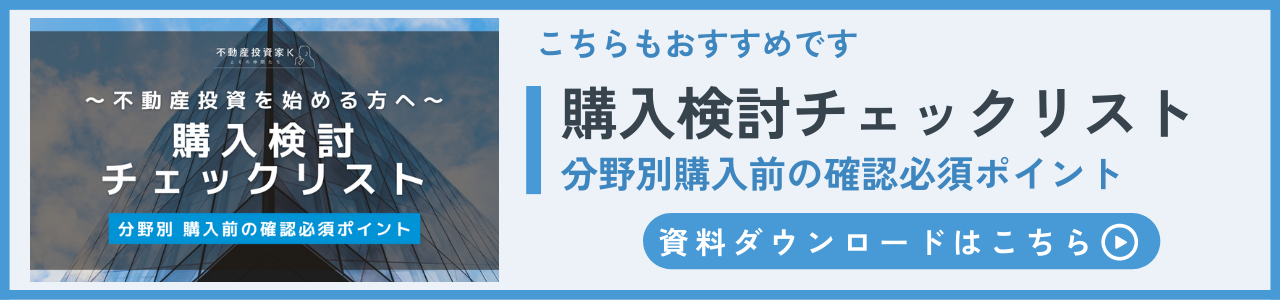
ポイント
- アパート経営には、空室リスクをはじめさまざまなリスクが存在する
- 適切な対策をすれば、アパート経営のリスクを最小限に抑えられる
- アパートの経営計画は、各種リスクを想定しながら長期的な視点で考える必要がある
アパート経営で知っておきたいリスク

アパート経営とは、所有しているアパートの部屋を貸し出し、家賃収入を得る不動産事業です。一度経営が軌道に乗れば、安定して利益を出し続けられるため、アパート経営に興味のある人も多いのではないでしょうか。
ただし、アパート経営にはさまざまなリスクが存在します。以下では、アパートの経営にあたって押さえておきたいリスクについて解説します。
空室リスク
代表的なリスクに、空室リスクがあります。所有しているアパートの居室に入居者が決まらず、空室となるリスクです。
空室になってしまうと家賃、つまり収入を得られなくなってしまいます。空室期間が長く続くと賃料収入が大きく減ってしまい、場合によってはアパートローンの返済にも影響が及ぶ可能性も否定できません。
なお、空室の発生にはさまざまな要因があります。
経年劣化による空室
空室リスクが発生する原因の1つが、経年劣化による競争力の低下です。年数の経過による劣化を防ぐことはできませんが、建物が老朽化すると、築浅の物件と比較して入居者が集まりにくくなってしまいます。
アパートで経年劣化が進行すると、以下のような事態が発生します。
- 外壁のヒビや汚れ
- 日焼けによる天井や壁、床の変色
- 浴室やトイレの壁の黄ばみ
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
こうした建物や設備の老朽化を放置していると、見た目から印象が悪くなり、入居希望者に選ばれにくくなる原因となります。また、築浅でも管理状態が良くないと、実際の築年数以上に劣化した印象をもたれてしまうこともあるでしょう。
過剰供給による空室
アパートの空室リスクが高まる原因として、過剰供給も考えられます。
同じエリアに同じような見た目、間取りのアパートが集中して建築すると、入居者の獲得合戦が発生することになります。その際、他のアパートと差別化できていないと、入居者を獲得できず、空室が発生してしまいます。
賃貸需要を見誤ったことによる空室
賃貸需要を見誤った場合も、空室が発生するリスクが高まります。入居希望者の需要を満たせなければ、どれだけ立派なアパートを建築しても入居者は見込めません。
賃貸需要を見誤ってしまった例としては以下のようなものがあります。
- 過疎化が進んでいるエリアにアパートを建てた
- 最寄駅から遠いエリアにアパートを建てた
- 商業施設や学校がないエリアにアパートを建てた
- アパートが飽和しているエリアにアパートを建てた
- 単身世帯が多いエリアにファミリー向けのアパートを建てた
- 大学の移転を知らず、学生向けのアパートを建てた
賃貸需要のミスマッチを防げなければ、アパートの空室リスクは上がってしまいます。
建物の設備やデザインによる空室
建物の設備やデザインが、アパートの空室リスクを発生させる原因になっているケースもあります。アパート経営を始めるにあたって、初期費用不足の問題を解決するために、設備やデザインにお金をかけずに経費削減をするケースは少なくありません。
しかし、アパートの設備や見た目は重要です。賃貸物件を探している人の多くは、できるだけ住み心地の良い、条件の良い物件を探しています。設備が不十分なアパートや見た目が悪いアパートは、魅力もなく、生活の利便性も低いと判断され、敬遠されるでしょう。
設備やデザインに問題があると、内見すらしてもらえない可能性もあります。結果、入居希望者が集まらず、空室のリスクも高まってしまうのです。
家賃下落リスク
知っておくべきリスクの1つは、家賃下落リスクです。家賃はアパート経営における主な収入源ですが、さまざまな要因によって変動します。
代表的な家賃が下がる要因として、周辺環境の変化があげられます。たとえば、アパートを建築したエリアに新しく大学が移転した場合、アパートの需要が増加するため、家賃の上昇が期待できるでしょう。
逆に大学が他のエリアに移転してしまうと、アパートに対する需要が低下し、入居者を見つけるのが困難になります。その場合、家賃を下げて入居者を確保するのが一般的です。しかし、一度家賃を下げてしまうと、家賃の水準を再びもとに戻すのは簡単ではありません。
家賃が下落すれば、当然収入も減少してしまいます。アパート経営を行う場合は、家賃の下落リスクをできるだけ抑えるような戦略を考える必要があります。
建物・設備の老朽化リスク
空室リスクや家賃下落リスクにも関係があるリスクとして、建物や設備の老朽化リスクが存在します。建物や設備はどれだけ大切に使用しても、月日が経てば老朽化が進行しトラブルが発生する可能性が高まります。
建物の老朽化を放置すると、先の空室リスクにつながるだけではなく、設備故障により想定していなかったタイミングでの修繕費が増えてしまい、経営の悪化につながる恐れがあります。計画的に建物の修繕や設備の入れ替えを実施して、建物や設備の老朽化リスクを最小限に抑える必要があります。
また、老朽化により入居者が集まりにくくなれば、家賃の見直しをすることになり、家賃下落リスクにもつながります。
家賃滞納リスク
アパート経営には、家賃滞納リスクも存在します。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が実施した調査によると、2023年時点の全国の月末での家賃の1カ月滞納率は1.2%、2カ月以上滞納率は0.5%でした。家賃の滞納が発生してしまうと収入が減少してしまいます。
しかも、家賃を滞納しているからといって、簡単に入居者を追い出すこともできません。これは借地借家法によって、入居者の権利が強く保護されているためです。裁判手続きを経て、家賃を滞納している入居者を強制退去させることもできますが、時間もお金もかかります。
入居前の審査を厳しくする、保証会社への加入を入居の条件にするなどの対策が必要です。
参考:日本賃貸住宅管理協会 市場データ(日管協短観)
入居者トラブルリスク
入居者トラブルも、発生しやすいリスクの1つです。アパートにはさまざまな人が集まりますが、アパートの入居者同士の相性が必ずしもよいとは限りません。
そのため、入居者の間で以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 騒音トラブル
- ゴミ出しのルールにまつわるトラブル
- 共用スペースの利用に関するトラブル
- 異臭トラブル
- ペット関連トラブル
- 駐車、駐輪に関するトラブル
- 勘違いや被害妄想によるトラブル
入居者の間でトラブルが発生すると、当事者はもちろん、ほかの入居者たちの退去につながる場合があります。トラブルの当事者だけがアパートに残る事態になれば、新しい入居者が見つかってもトラブルに巻き込まれるのを恐れ、早々に別のアパートに引っ越されかねません。
立ち退きリスク
アパート経営には、立ち退きリスクがある点も理解しておきましょう。アパートが老朽化した場合、安全性を確保するために一度建物自体を取り壊して建て直すことがあります。
アパートを取り壊す場合、すでに入居している住人たちには一度アパートを出ていってもらう必要がありますが、なかにはアパートから出ていくのを拒否する方もいます。立ち退きを拒否されてしまうと、当然アパートの建て直しはできません。
強制的に退去させようとしても、先述のとおり入居者の権利は借地借家法によって強く保護されているため、簡単に実行できるものではありません。立ち退きの同意を得られても、貸主都合で立ち退き、つまり賃貸契約の解除をする場合、正当な理由とともに立ち退き料の支払いが必要です。
また、立ち退き料は法律で金額がとくに決まっておらず、入居者が金額に納得できず交渉が決裂してしまうケースもあります。
あわせて読みたい
金利上昇リスク
アパートローンには固定金利型と変動金利型、そして固定金利期間選択型の3種類が存在します。
変動金利型のアパートローンは、市場の影響を受けて金利が上下動するため、金利が上昇してしまうと返済額が増大します。たとえば、1億円の融資を受けた場合、金利が1%上昇するだけで年間の負担額が100万円上昇することになります。
とくに近年は金利上昇の兆しも伺えるため、目先の金利に惑わされず、長期的な視点でアパートローンの金利を選択する必要があるでしょう。
ローン返済リスク
不動産投資用にアパートを購入、または建築する際、アパートローンを利用する方は少なくありません。借入金額が大きくなれば、比例してローンの返済の負担は大きくなります。万が一空室の増加や家賃の下落などによって収入が減少し、ローンの返済が滞ってしまうと、債務不履行で物件が競売にかけられてしまいます。
それでも残債が発生してしまうと、最悪の場合自己破産に至りかねません。ローン返済リスクを下げるためには、無理のない範囲でローンを利用し、現実的な返済計画を立てることが大切です。
災害リスク
日本でアパート経営をする場合、必ず考慮しなければならないリスクが災害リスクです。日本は世界でも有数の災害大国として知られており、地震や台風、洪水など、毎年全国各地でさまざまな災害が発生しています。
そのため、災害が原因で所有しているアパートが大きな被害に遭う可能性は、決して低くありません。万が一災害が原因でアパートが倒壊してしまうと、その時点で家賃収入が途絶えてしまいます。
保険に入っていればある程度リスクを抑えられますが、災害の種類によっては保険の補償が受けられません。たとえば、地震や津波の被害は火災保険の対象外です。その場合、建物を失いローンだけ手元に残る事態になりかねません。
アパート建築予定地の災害発生リスクの調査をはじめ、可能な限り災害のリスクを抑える方法を考える必要があります。
環境変化のリスク
環境変化のリスクも、アパート経営において考慮すべきリスクの1つです。周辺環境は、アパート経営に大きな影響を与えます。
たとえば、学校や企業など近隣施設の移転によって、そのエリアのアパート需要が変化することはよくあります。
その結果、アパートの新規入居者を確保できず、アパート経営が悪化する可能性が高くなります。
そのため、アパートを建築する際、周辺環境が大きく変化する可能性はないか調査する、また無料Wi-Fiの完備をはじめ、環境が変化しても対応できる独自の強みを持つなどの対策を考える必要があります。
サブリース契約のリスク
サブリース契約とは、部屋を業者が借り上げ、入居者に又貸しする契約のことです。サブリース契約の最大のメリットとして、空室や家賃滞納による収入の空白が発生しない点があげられます。これは、業者が一棟丸ごとの借り上げ家賃を長期契約で払うためです。
また、アパート経営の実務を専門家に任せることで、入居者とオーナーの間で直接の責任問題も発生しません。一見よいことばかりに思えますが、サブリース契約には以下のようなリスクも存在します。
- 一定期間ごとの家賃の見直し
- 免責期間の存在
- 広告費をはじめとする突発的な支出
とくに家賃改定に関する確認を怠ってしまうと、想定していた家賃収入を得られず、アパート経営に悪影響を与える可能性もあります。そのため、メリットとデメリット、両方を知ったうえで、サブリース契約を採用するか慎重に検討しましょう。
あわせて読みたい
売却が難しくなるリスク
一定期間が経過したらアパートを売却するアパート経営者は珍しくありません。アパートを売却し、現金化することで、次の事業の頭金も獲得できます。もし不動産価格が高くなったタイミングで売却が成立すれば、かなりの譲渡益を得られるでしょう。
ただし、これらのメリットはあくまでアパートの売却に成功した場合に得られるものです。必ずしも自分が売却したいタイミングに希望の金額で売却できるとは限りません。また、アパートには法定耐用年数が存在しており、たとえば木造なら22年、軽量鉄骨造は19年〜34年ですが、この年数を超えてしまうと売却が成立しにくくなります。
売却できたとしても、値段がほとんどつかない可能性もあります。売却を考えている場合は、売却のタイミングを見極める、最低限のリフォームをするなどの工夫が必要になるでしょう。
リスクを軽減する方法

アパート経営には、さまざまなリスクが存在します。そのため、アパート経営に興味を持っていても、二の足を踏んで諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、適切な対策を行うことができれば、アパート経営のリスクを最小限に抑えられます。以下では、アパート経営のリスクを軽減する具体的な方法について解説します。
市場調査による適切な立地や設計
まずは、適切な市場調査を行い、立地の設定や設計の計画を立てましょう。アパート経営における最大のリスクの1つが、空室リスクです。空室を防ぐためには、アパートを探している方たちに選ばれるアパートを建てなければなりません。
そのために必要なのが、市場調査です。市場調査では、以下のような点をチェックします。
- 立地条件
- エリアニーズ
- 競合アパートの空室状況
- 再開発や地価の動向
運営計画を立てるにあたっては、自身がアパートの建築を検討しているエリアにある類似のアパートが、どの程度の金額の家賃を設定し、入居者を募集しているか調べてみると良いでしょう。調査の方法としては、地元の不動産屋から話を聞く、オンライン上で関連情報を検索する、自分の足で調査するなどがあげられます。
長期的視点による運営計画
アパート経営における各種リスクを抑えるには、長期的視点による運営計画が欠かせません。アパート経営でありがちなのが、成果を出すのに焦ってしまい、黒字化に失敗してしまうケースです。
アパート経営は建築費をはじめ、巨額の初期費用を用意しなければならないため、利益が出るようになるまでどうしても時間がかかります。どの程度でアパート経営が黒字化するかは空室率や経営状況、ローンの借入金額によって異なりますが、10年が1つの目安です。
そのため、不足の事態が発生しても対応できるように、運営計画も長期視点で考える必要があります。なお、具体的な運営計画を立てる際に考えておきたいポイントは、以下のとおりです。
- メンテナンスコスト
- ローン返済計画
- 空室や家賃下落リスクへの対応
- 出口戦略(売却や相続)について
メンテナンスとリノベーションの重要性
入居希望者がアパート探しにおいて「建物の外観が清潔に保たれているか」、「新しさやきれいさがあるか」を重視する方は少なくありません。
そのため、老朽化が進んだアパートは、入居者の確保に苦戦する可能性が高いといえます。しかし、メンテナンスやリノベーションを実施し、アパートの状態を維持できれば、入居者が途絶えるリスクを減らせます。
また、定期的な点検を行うことで、雨漏りをはじめとする大きなトラブルを未然に防ぎ、全体のメンテナンスコストを抑える効果も期待できるでしょう。
空室対策のアイデアと実践
アパート経営のリスクを削減する方法として、空室対策も欠かせません。
アパート経営にまつわるリスクの多くは、空室に起因しています。そのため、以下のような空室対策を積極的に行いましょう。
- ターゲットの見直し
- 入居者の費用負担の軽減(家賃の見直し)
- 募集資料の見直し
- 定期的な清掃と修繕の実施
- 新しい設備の導入
家賃の見直しは収入の減少にもつながるため、二の足を踏んでしまいがちですが、必要な場合もあります。
また、新しい入居者の募集やアパートの賃貸借契約について、不動産会社に一任するケースは少なくありません。積極的に不動産会社との交流を図ることで、アパートを探している人に自分の所有しているアパートを優先的に紹介してもらいやすくなる可能性もあるでしょう。
あわせて読みたい
保険加入とリスク分散の考え方
保険は自分で負うべきリスクを外部、この場合は保険会社に肩代わりしてもらう手段です。つまり、リスク分散の1種といえます。
保険は、火災保険だけでなく地震保険にも加入すると良いでしょう。火災保険と地震保険は、補償範囲が異なります。
たとえば、火災保険は火災や自然災害による被害をカバーしてくれますが、地震や噴火、津波などの被害は対象外です。これら対象外の被害をカバーしてくれるのが、地震保険です。
ただし、複数社の保険に入った結果、アパート経営のランニングコストが嵩んでしまっては意味がありません。リスクと補償内容のバランスを見ながら、本当に必要な保険を見極めることが大切です。
賃貸管理会社の活用
アパートの運営業務は多岐に渡るため、ノウハウがない方がすべてを対応するのは難易度が高いといえるでしょう。しかし、経験豊富な賃貸管理会社に任せることで、効率のよいアパート経営を実現できます。
また、家賃滞納をはじめ、対応に苦心するトラブルが発生したときも、対応経験を活かして被害を最小限に抑えるように動いてくれる点もメリットです。賃貸管理会社を選ぶ際は、サービスと手数料のバランス、委託先の変更ができるかどうかなどをチェックしましょう。
信頼できる専門家のサポート
賃貸管理会社以外にも、アパート経営のサポートをしてくれる専門家は複数存在します。
- 税理士(節税対策や確定申告に関するサポート)
- 司法書士(登記に関するサポート)
- ファイナンシャルプランナー(資金計画に関するサポート)
アパート経営を成功させるためには専門知識が必要ですが、最初からすべてを1人で行うのは困難です。必要に応じて、信頼できる専門家の力を借りましょう。
なお、専門家のサポートを受ける場合は、候補となる複数の専門家に相見積もりを依頼し、提案内容や費用の比較することをおすすめします。
アパート経営に失敗しやすい人の特徴と注意点

アパート経営にリスクはつきものですが、市場調査や運営計画の立案など、適切な対策を行えば、リスクの発生を最小限に抑えられます。ただし、どれだけリスク対策を行っても、そもそもアパート経営に向いていない方は、アパート経営に失敗する可能性が高くなるでしょう
アパート経営に失敗しやすい人物の特徴について解説します。
リスクを想定した経営計画を立てていない
アパート経営に失敗しやすい人物の特徴として、リスクを想定した経営計画を立てていないことがあげられます。経営計画を立てるにあたって、各種リスクを想定することは重要です。アパート経営は、災害リスクや家賃下落リスクなど、長期的にさまざまな不確定要素の高いリスクに晒されます。
そのため、リスクを考慮せず、見通しの甘い経営計画を立ててしまうと、トラブルに対して適切に対処できず、アパート経営の悪化につながりかねません。しかし、あらかじめ経営計画を立てる段階でどのようなリスクが存在するのか把握できていれば、適切な対策が取れるだけでなく、いざ問題が発生したときに慌てずに対処できます。
自分で情報収集をしない/知識が不足している
自分で情報収集をしない方や、アパート経営に関する知識が不足している方も、アパート経営に失敗しやすい傾向にあります。アパート経営を成功させるためには、自主的に情報収集を行い、新しい知識を習得する姿勢が求められます。
専門家に任せるのは、精神的にも体力的にも負担が少なく、効率的に見えるかもしれません。しかし、業者の話をすべて鵜呑みにしてしまうと、高額な物件を購入させられる、不必要な工事をさせられるなど、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
一方、アパート経営に成功している方は、専門家の話を聞きつつ、自分でも情報収集を行い、しっかり考えてから判断する傾向があります。常に中立的な視点で裏を取る癖をつけると、アパート経営に失敗するリスクを減らせるでしょう。
長期的な視点がない
アパート経営に失敗しやすい人の特徴として、長期的な視点がないこともあげられます。
アパート経営は、初期投資の回収に時間がかかる事業です。また、初期投資を回収するまでには建物の老朽化や家賃の下落をはじめ、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。そのため、想定外の事態に備えたリスクヘッジをはじめ、長期的な視野での経営計画や、余裕のある資金計画を考えなければなりません。
長期的な視点で経営計画を考えるにあたって、大切なのは目標の設定です。目標を設定することで、ブレのない判断基準ができ、しっかりと計画を立てられます。
アパート経営のリスクに対する考え方

アパート経営にはリスクが存在しますが、そのリスクが大きいと考えるか、それとも小さいと考えるかは人によって異なります。以下では、アパート経営のリスクに対してどのように向き合えばよいか、考え方について解説します。
アパート経営にリスクはあると認識する
まず、アパート経営にリスクはつきものと認識しましょう。アパート経営は不動産投資の一種です。そして不動産投資に限らず、リスクが存在しない投資は存在しません。
もともとリスクとリターンは、表裏一体の存在です。収益を得ようとすると、必ず何らかのリスクが伴います。「確実に収益があがる」アパート経営は現実的ではありません。
事前にリスクの中身を認識し、しっかりと準備することで回避できるリスクはあります。適切な対策を実施できれば、リスクの発生を最小限に抑えられるでしょう。
「リスク」=「損失」だと考えない
アパート経営など投資において、リスクとは「損失」「危険」ではありません。
投資におけるリスクとは、損失の発生するかもしれない可能性であり、リターンの振れ幅でもあります。「リスクが大きい」という場合、損失だけが大きいのではなく、「損失の可能性」も「収益の可能性」も同じだけの大きさなのです。
リスクを単なる「避けるべきもの」として怖がるのではなく、「適切に取り扱うもの」として捉えることが重要です。アパート経営において、リスクを損失としてだけ認識してしまうと、エリア選定や物件選びの場面でも正確な判断ができなくなることもあります。
アパート経営に関する正しい知識とリスク管理の手法をしっかり学び、うまくリスクを減らしながら安定した運営を行うことが重要です。
まとめ

アパート経営には空室リスクや家賃の下落リスク、そして建物や設備の老朽化リスクなどさまざまなリスクが存在します。
しかし、市場調査や長期的な経営計画の立案など、適切な対策を行えばアパート経営の各種リスクを軽減することは十分可能です。なお、対策を考えるのは個人だけでは限界があるため、場合によっては信頼できる専門家の力を借りることも検討しましょう。

監修者
宅地建物取引士
佐藤 智彦
東京・仙台を中心に、20年以上アパート・マンション建築賃貸業界に従事している。これまで500棟以上の新築アパート・マンションの企画・設計・建築・運営に携わり培ってきたリアルな知見が強み。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!