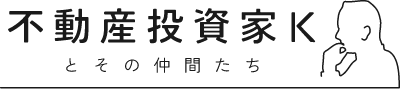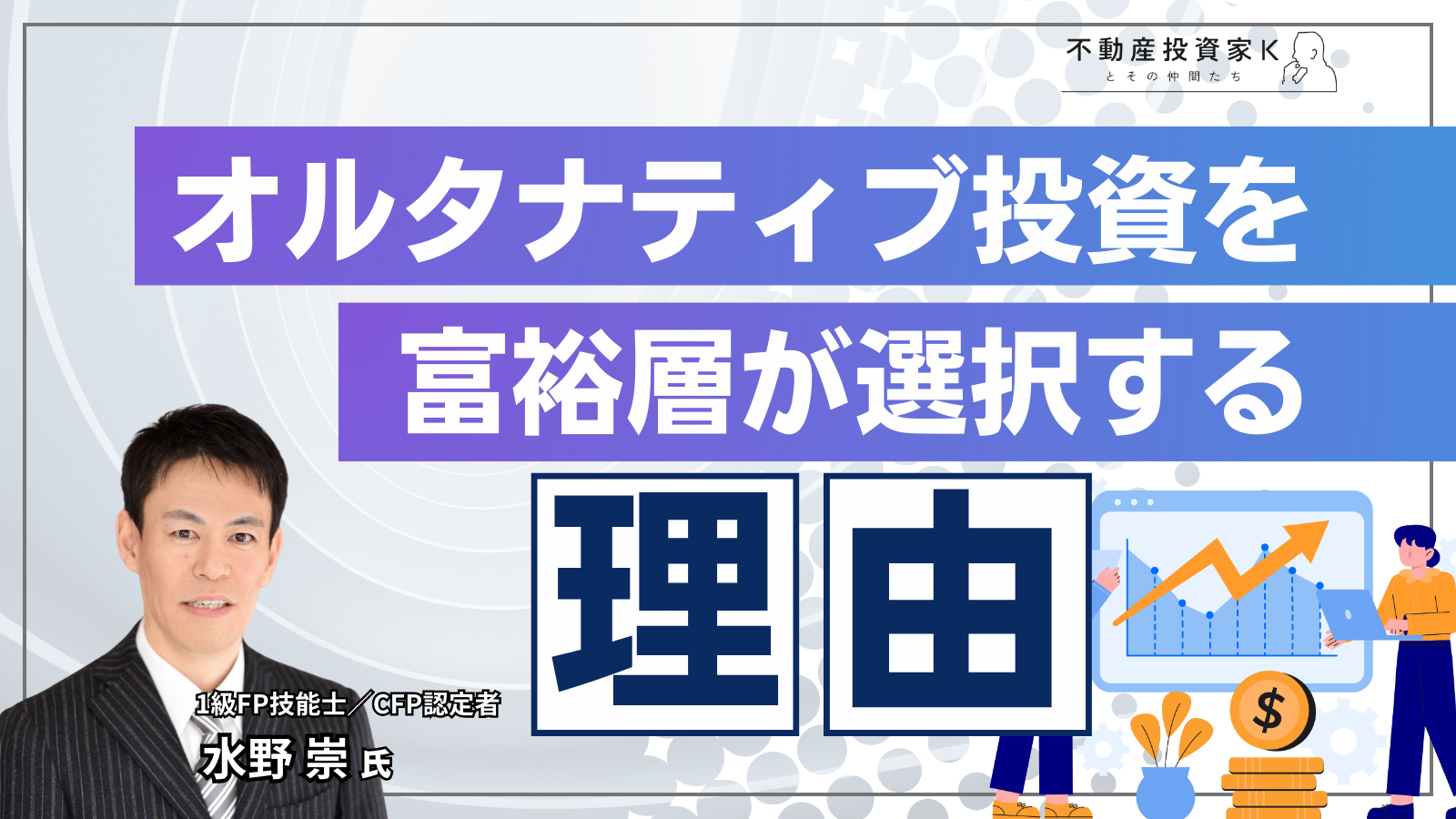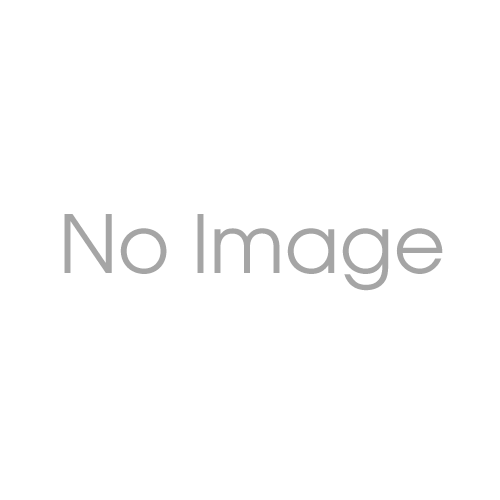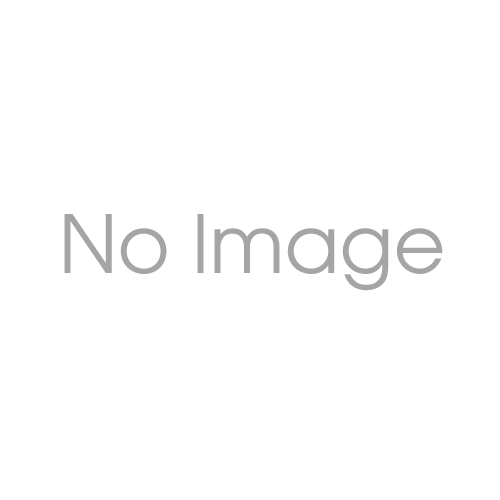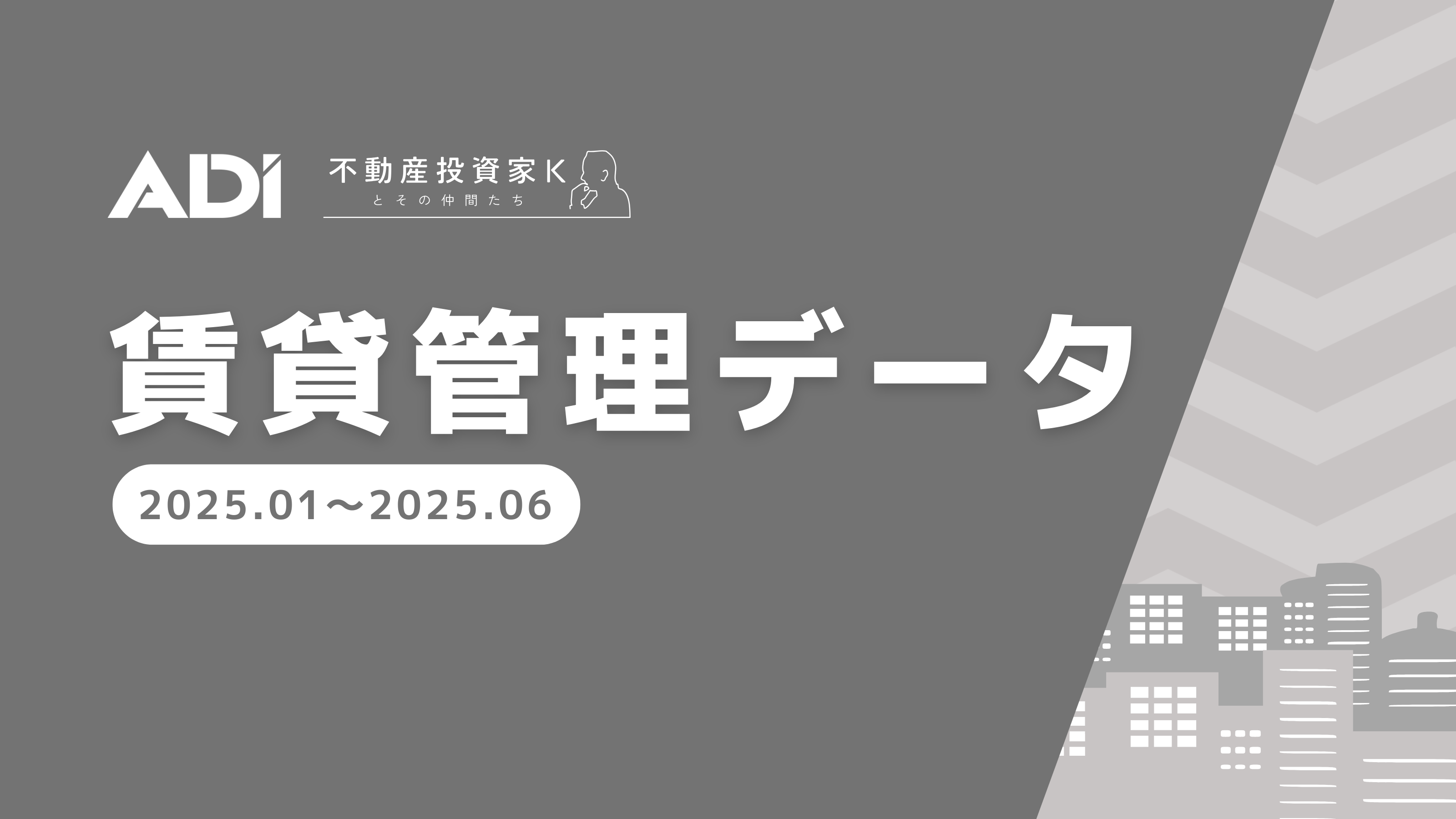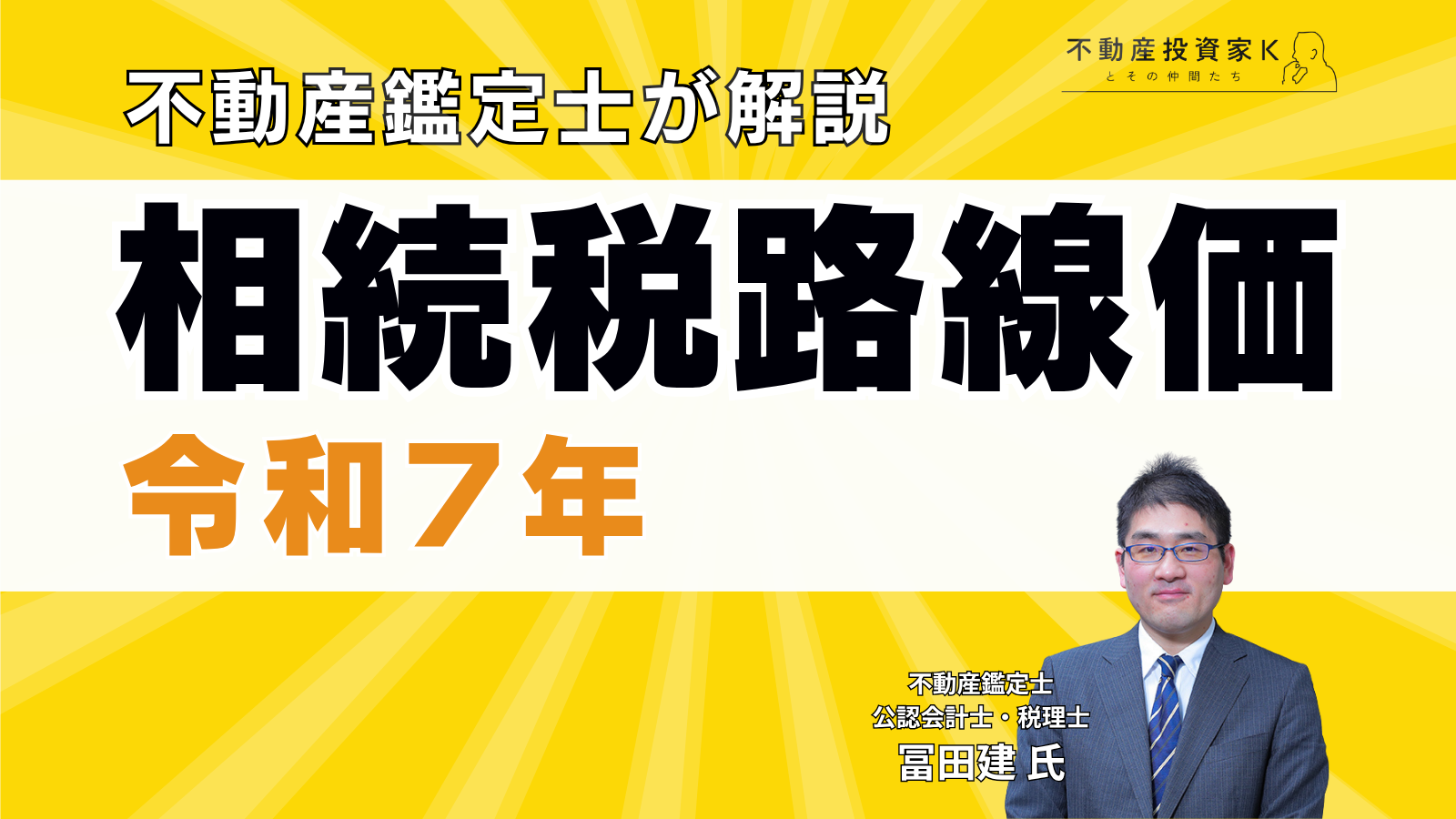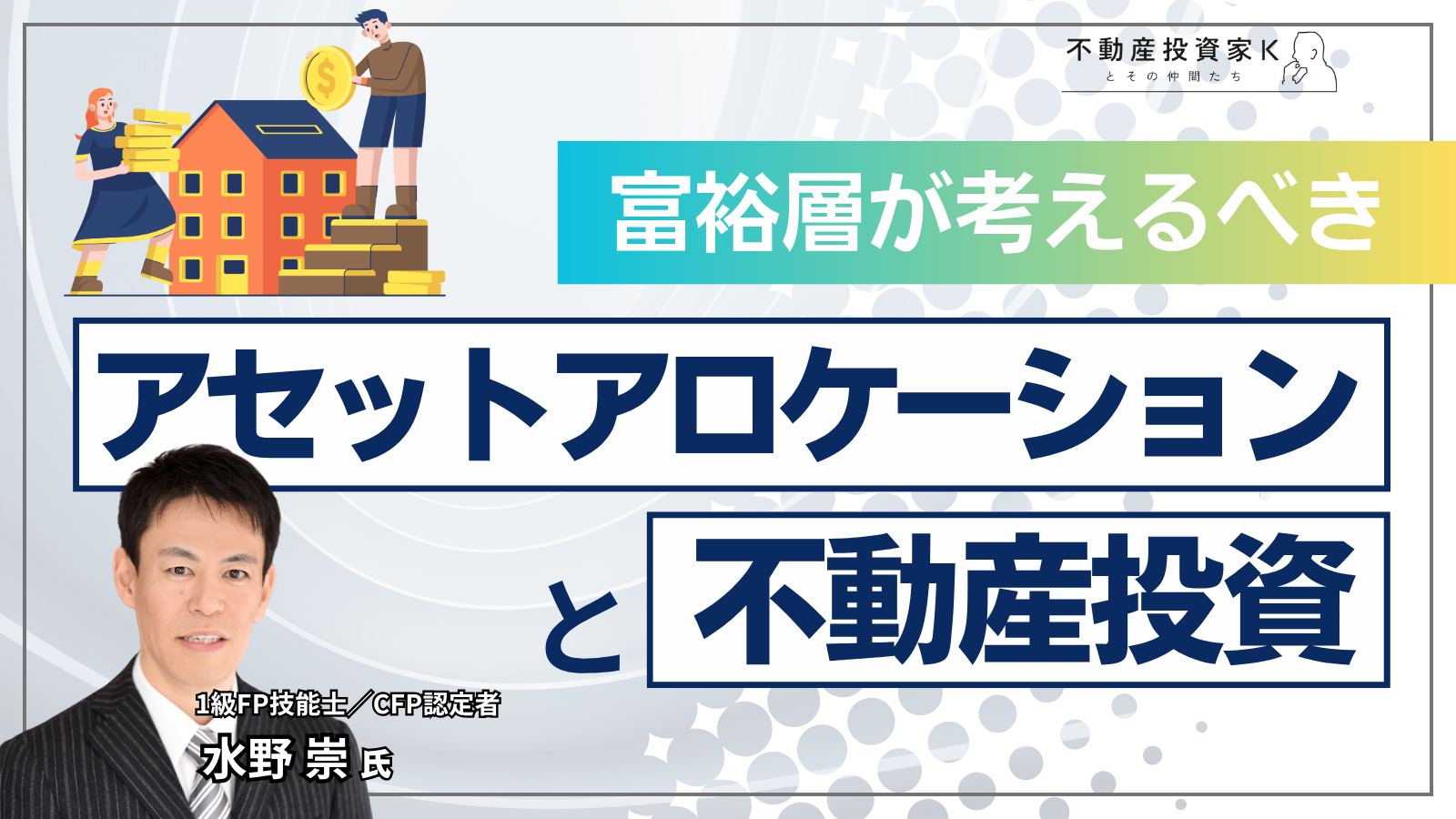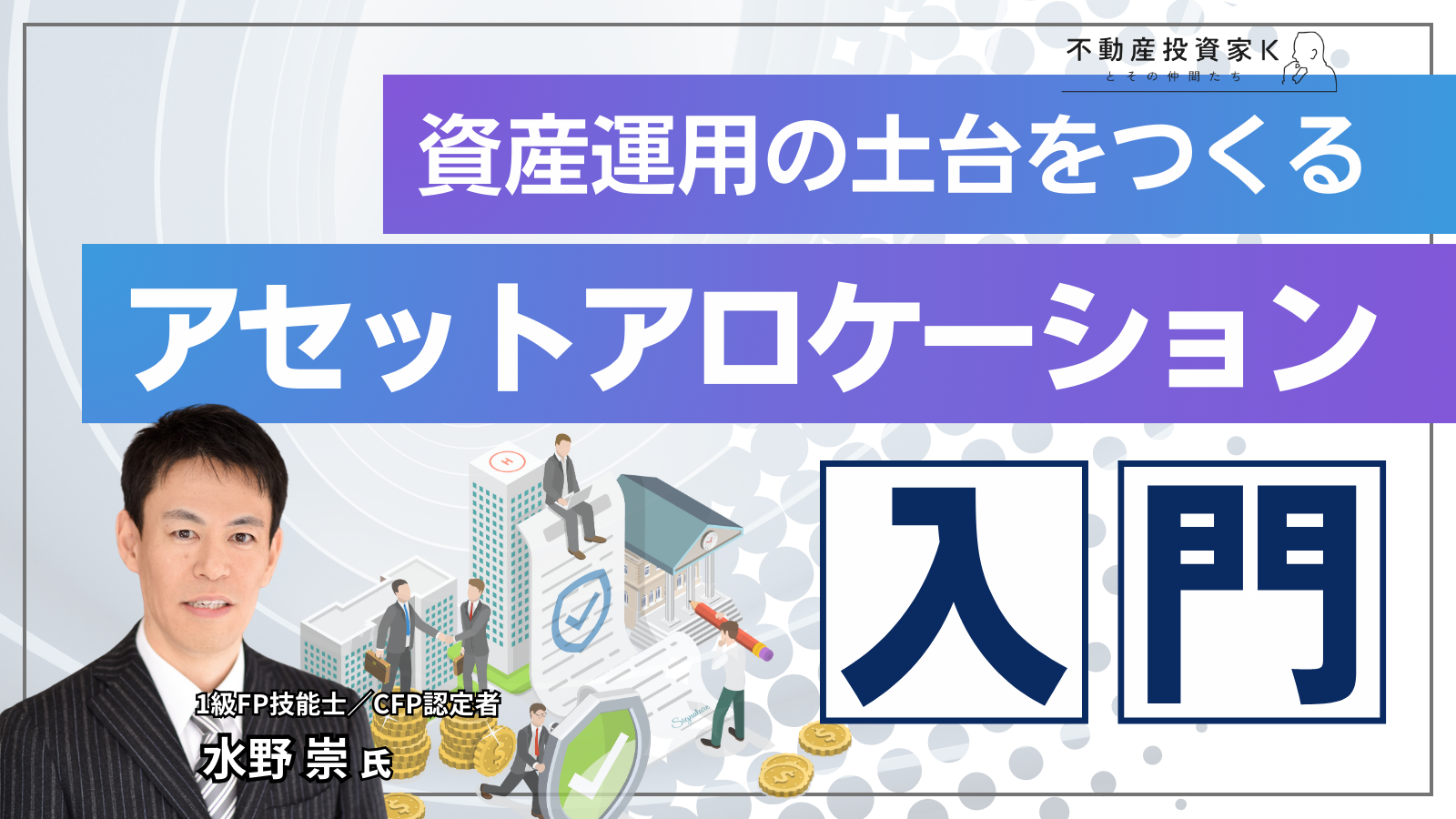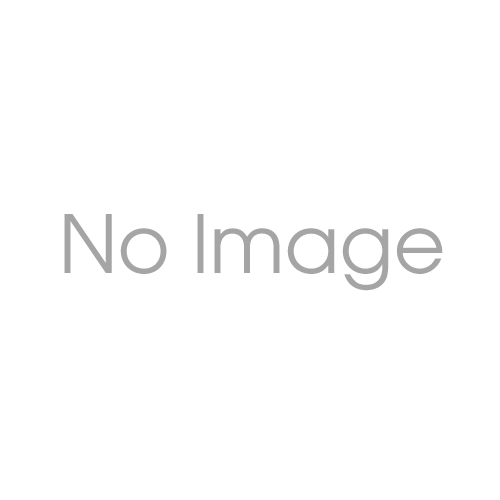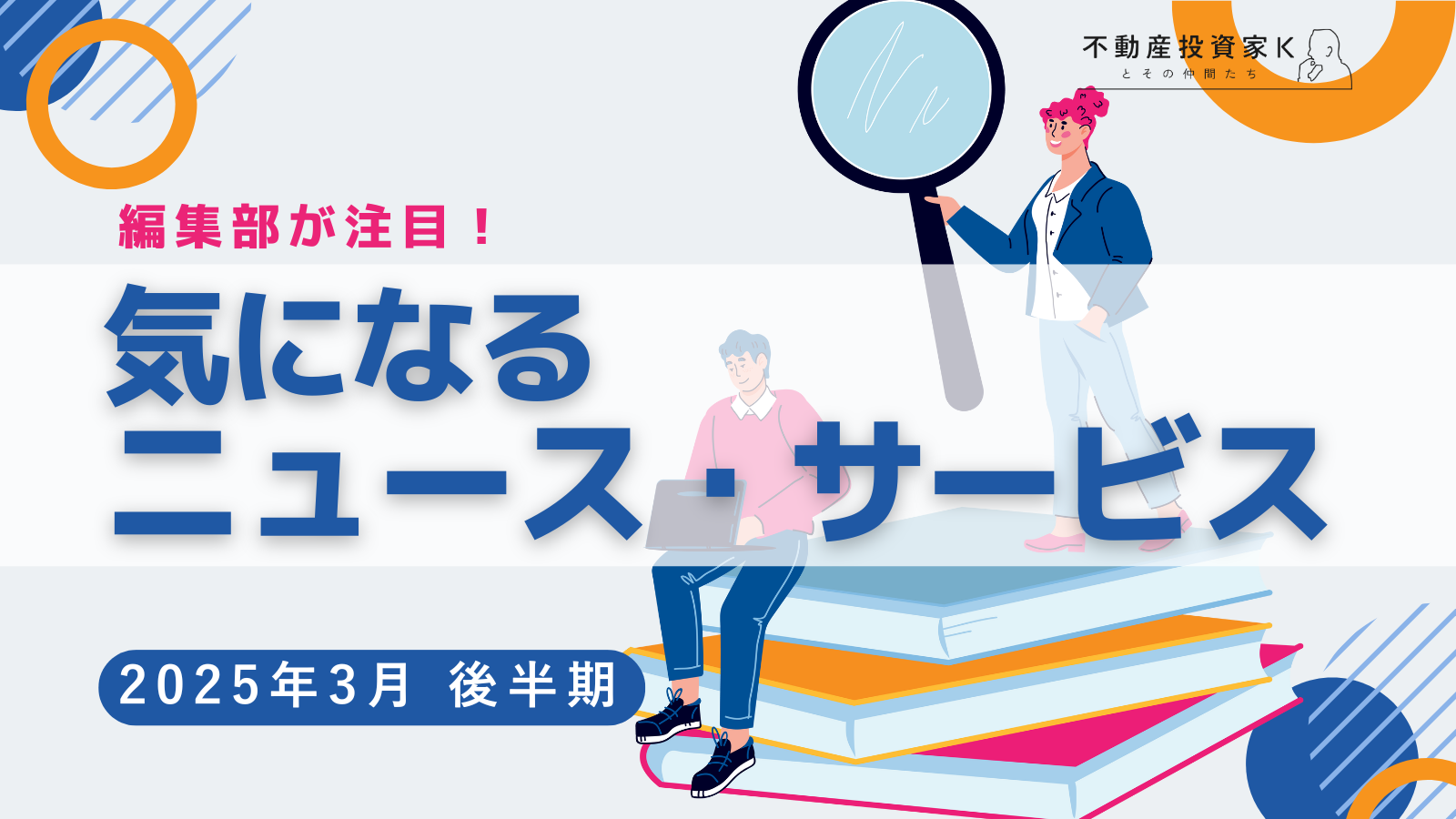不動産鑑定士・公認会計士・税理士の冨田建氏によるコラムがスタート。今回は、東京23区の東部に位置する江戸川区の地価動向について解説します。
ポイント
- 住宅地は、規模の大きい土地では、周辺よりも高額な水準での取引となる傾向
- 江戸川区内の投資収益物件の表面利回りは、小さいもので4%台後半、大きいもので8%台程度が目安
はじめに 江戸川区の概要

はじめまして。不動産鑑定士(公認会計士・税理士)の冨田と申します。縁あって、こちらのコラムを執筆させて頂くことになりましたので、読者の皆様にも何かのプラスの情報を得て頂ければ幸いです。
で、このコラムでは、色々な地域の地価動向を分析していきたいと思いますが、初回は江戸川区から。
江戸川区は、東京23区の東側かつ海側に接する区で、東隣は千葉県です。
区内には北側にJR総武線や京成電鉄本線が走り、南に行くにつれて地下鉄の都営新宿線や東西線、さらにはJR京葉線が通っています。いずれも東京23区中心部から千葉県に向けて東西に放射する形態で、区内を南北に突き抜ける鉄道路線はありません。
また、道路に目を向けると、東京と千葉を結ぶ国道14号線が東西を横断し、南北には都道318号線、いわゆる環状七号線が突き抜けています。
江戸川区の人口は令和6年12月時点で約693千人で前年同月と比較して約0.6%の微増傾向です。
では、江戸川区の地価はどのような傾向なのでしょうか。公示価格や都道府県地価調査基準地価格の動向や国土交通省の公表する不動産取引価格情報にも着目しながら考察してみたいと思います。
商業地の動向はどうか

江戸川区の令和6年の公示地の最高価格地点は西葛西駅の駅前に位置する「江戸川5-3」の地点です。
その価格水準は1,850,000円/㎡ですが、駅前広場に面した、区内屈指の繁華性の高い地点ですので、この地点の価格水準は、同様に小岩駅前の繁華性の高い地点の「江戸川5-1(1,610,000円/㎡)」と同様に区内でも少々例外的な価格水準と見てよいでしょう。
ただし、不動産にある程度、精通している人にはよく知られていることですが、東京23区では、実勢の土地価格は、公示価格よりある程度は高いことが通常です。
特に商業地の場合は、その土地を賃貸等をしたらどの程度の稼ぎが得られるかに左右される部分が強いため、一概には言えない部分はありますが、筆者の個人的感覚では公示価格ベースより1.5倍程度であっても「おかしくははない」と感じています。
一方で、国土交通省が発表している不動産取引価格情報もあります。
こちらで、「商業地」の「土地」を「令和4年以降」の「今後の利用目的が住宅以外」の取引との条件で令和7年1月に検索すると19件の取引事例がヒットし、240,000円/㎡~1,400,000円/㎡(うち1,000,000円/㎡以上は2件、900,000円/㎡台が3件の一方で、400,000円/㎡以下が9件)でした。ただし、これは国土交通省が把握している限りの情報ですので、実際にはより多くの件数の取引があることが推察されます。しかし、それは関係者限りのクローズドな情報であることも多いので、ここでは知り得る情報から分析をしたいと思います。
当然ながら、低い価格の地域は駅から遠い等、不便な地域が目立つ印象でした。
特に商業地の売買に際しては、23区外周の区の全般に言えることですが、利便性・繁華性に注意して意思決定する必要がありそうです。
参考:国土交通省 不動産情報ライブラリ
住宅地の動向はどうか

住宅地の場合は、令和6年公示価格ベースで300,000円/㎡台~500,000円/㎡台に概ね収束しています。なお、近年の動向を勘案するに、執筆時点では江戸川区の令和7年時点の公示価格の内容を筆者は存じ上げませんが、近似の地価動向を勘案するに令和7年は令和6年に比較して上昇傾向と推察されます。
ただし、商業地と同様の理由で、実勢相場は公示価格よりある程度は高いです。 ここで、筆者の個人的見解かつ肌感覚を書くと、江戸川区に限らず東京23区の外周であれば、住宅地の状況にもよりますが、実勢価格は公示価格の1~1.5倍程度が目安と感じています。
さらに個人的見解かつ肌感覚を書くと、江戸川区の場合、JR総武線が最も利用価値が高い路線と言え、京成線も概ねJR総武線に平行しているので、都心への距離にもよりますが、JR総武線側が最も高いと考えています。
次に東西線沿い、その次に都営新宿線沿いで、京葉線沿いはそれほど地価は高くない印象です。
実は、この順番は、これらの鉄道が開通した順番です。
江戸川区に限らず、昔からある鉄道の駅を中心に街並みが形成された経緯がありますので、その街並みとは無関係に、例えば最近50年以内程度に開通した鉄道の駅は「町の核」としての機能は比較的低いと思いますが、いかがでしょうか。
商業地と同様に、令和4年以降の土地の不動産取引価格情報に基づく取引事例も見てみましょう。
江戸川区では住宅地は取引件数がたいへん多いため、概ねの傾向を語るに留めざるを得ませんが、中心価格帯は300,000円/㎡~400,000円/㎡台が目立つ印象ではあります。
ただし、特徴的なこととして指摘できるのは、例えば400㎡以上の土地については、490㎡で1,300,000円/㎡の取引事例や、810㎡で870,000円/㎡の取引事例、さらには340㎡で810,000円/㎡の取引事例等も見られる点です。
いわば、「標準的な戸建住宅としての利用」に適した規模感の土地については、300,000円/㎡~400,000円/㎡台が一つの目線と言えても、おそらくは分譲業者が買主なのでしょうが、規模の大きな土地については単価ベースでの比較では明らかに周辺よりも高額な水準での取引となる傾向との点も認識して損はないでしょう。
一方で、区内でも交通利便性に劣る大杉や本一色、鹿骨などでは200,000円/㎡を下回る取引も見られる状況です。
不動産取引価格情報では、その土地の取引が「更地なのか、それとも底地なのか」が明確ではないので、もしかして価値の低い底地の取引である余地も否定できませんが、とりあえずは、例えば駅から20分以上かかる地域では、地価は相応に安いとの点は認識しておいてもよいのではないでしょうか。
参考:国土交通省 不動産情報ライブラリ
利回りの動向はどうか

この記事をご覧になっている方は、不動産投資を考えておられる方も多いかと思いますが、そのような方に向けて、利回りの動向も考察したいと思います。
その前に、読者の方の中には利回りとは何ぞや…とお考えの方もおられると思いますので、簡単にあらましを説明したいと思います。
そもそも利回りとは
不動産投資をするということは、まず「一定の価格を払って賃貸物件たる元本としての不動産」、即ち、「投資収益物件」を購入して、貴方自身がその賃貸物件にオーナー(賃貸人)になり、賃借人から家賃を得て元本を回収し、うまくいけば元本以上を回収して利潤を得ることになります。
と、いうことは、「元本」たる価格に対して、「家賃に基づく儲け(純収益と言います) 」の割合が高ければ高いほど、賃貸経営的には有利ということになります。
ここで、一点、注意したいのは、「家賃」と、「家賃に基づく儲け」は違う点です。なぜなら、賃貸人は回収した家賃から、賃貸物件の固定資産税・都市計画税や修繕費、賃貸管理業者に対する報酬等の「その賃貸物件に関する経費等」を支払う必要があるので、「家賃に基づく儲け」は「家賃」から「その賃貸物件に関する経費等」を差し引いた額になるからです。
そして、「元本」に対する「家賃に基づく儲け」の比率が、「どの程度のペースで回収ができ、儲かるか」の指標となります。
この比率が不動産業界でいうところの「還元利回り」と言われるものになります。なお、細かい話を書くと還元利回りの定義も色々と複雑な面があるのですが、この記事ではマニアックなことを語っても混同をするだけですので割愛します。
また、経費等を差し引く前の単なる「家賃」と「元本」の比率を表面利回りと言います。
表面利回りは、純粋な稼ぎに対する割合ではありませんので、実際には家賃に対する経費が異常に高いために儲からない場合もある等、厳密に言えばこれを不動産投資の指標にすることは問題がないとは言えなくもありません。そして、それゆえに不動産鑑定の世界では、表面利回りを何ら補正をせずに使うことは基本的にはタブーで還元利回りを用いて鑑定評価額を決定します。
しかし、細かい経費等の分析をせずに実際の家賃と元本としての価格の比率を簡単に算出できるため、不動産鑑定を経ない不動産市場の現場では表面利回りが多用されています。
と、いうことは、この表面利回りや還元利回りの動向を見て、その数値が下がっていけば、「家賃」もしくは「家賃に基づく儲け」に対する元本たる価格が上昇していることを示しますから、「投資物件も上昇している」ことの示唆となります。
ですので、表面利回りの動向も考察してみたいと思います。
利回りの動向
筆者が色々と調査をしたところ、令和6年以降の江戸川区の投資収益物件の取引は、例えば都心5区ほど活発ではないものの、それでも昭和末期から平成年代新築の物件で数件の情報が得られる状況でした。ただし、こちらも筆者が調べた限りの情報に過ぎず、実際にはクローズドで他にも取引がなされている旨が指摘できます。とはいえ、大型の不動産投資案件が動く都心程は投資市場は熱くないのでは…と個人的には思います。
もともと、「自分が住むための戸建住宅」とは異なり、不動産投資目的で不動産を買う人は限られるので、投資収益物件の取引は、千代田区のような例外は別として件数がかなり少ないのです。
その結果として、江戸川区内での投資収益物件の表面利回りは小さいもので4%台後半、大きいもので8%台程度が一つの目安と考えられました。
ちなみに、建物が古いほど、リスクが高いので利回りの数値は大きくなり、よって価格は低くなります。
ただし、注意したいのは、表面利回りは、満室想定の賃料を基準に計算している場合も多いのですが、現実には空室があることにより、実際にはもう少し不利になる場合があるとの点です。
ですので、まずは表面利回りの目線を頭に入れて置き、必要に応じて不動産業者や、場合によっては相談料の報酬等が生じますが不動産鑑定士の意見も聞いた上で、適宜、判断されるとよいのではないかと思います。
最後に

江戸川区提供画像
筆者の個人的な感覚ですが、地価が上昇というよりは、「物価高でお金の価値が下がっている」面も手伝って、不動産価格も上昇している面を感じています。 不動産の価値は変動しやすい上に、不動産経営の如何でもその後の稼ぎが変わってきますので、江戸川区で不動産の売買をご検討中の方は先に考察した区内の不動産市場の動向を勘案しつつ、物価高との関係も吟味しながら意思決定されるとよいのでは…と感じています。
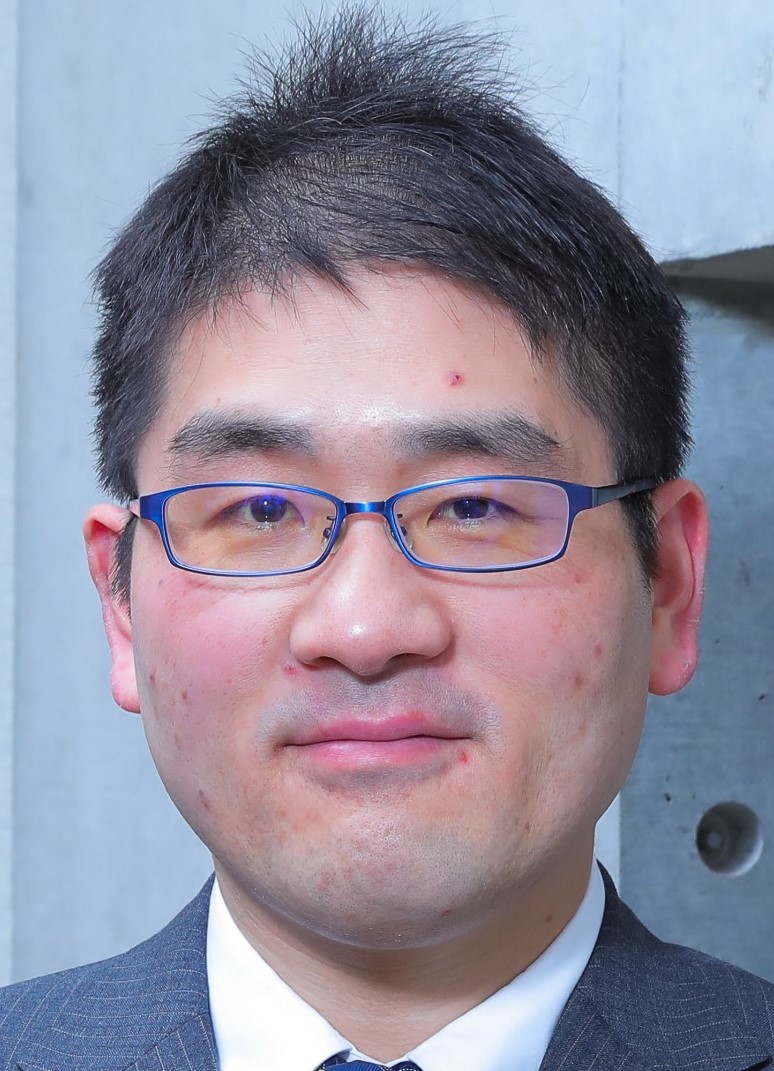
執筆者
不動産鑑定士・公認会計士・税理士
冨田 建
慶應義塾中等部・高校・大学卒業。大学在学中に当時の不動産鑑定士2次試験合格、卒業後に当時の公認会計士2次試験合格。大手監査法人・ 不動産鑑定業者を経て、独立。全国43都道府県で不動産鑑定業務を経験する傍ら、相続税関連や固定資産税還付請求等の不動産関連の税務業務、ネット記事等の寄稿や講演等を行う。特にYahoo!Japan様の個人オーサーとして専門記事や各種ニュースへの専門家コメントを定期的に執筆しており、令和4年1月には鬼怒川温泉の記事で、毎月の個人オーサーの中でも得に優れた記事を表彰する月刊MVAを受賞。令和3年8月には自身二冊目の著書「不動産評価のしくみがわかる本」(同文舘出版)を上梓し、令和4年に増刷。令和5年春、不動産の売却や相続等の税金について解説した「図解でわかる 土地・建物の税金と評価」(日本実業出版社)を上梓。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!