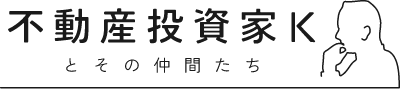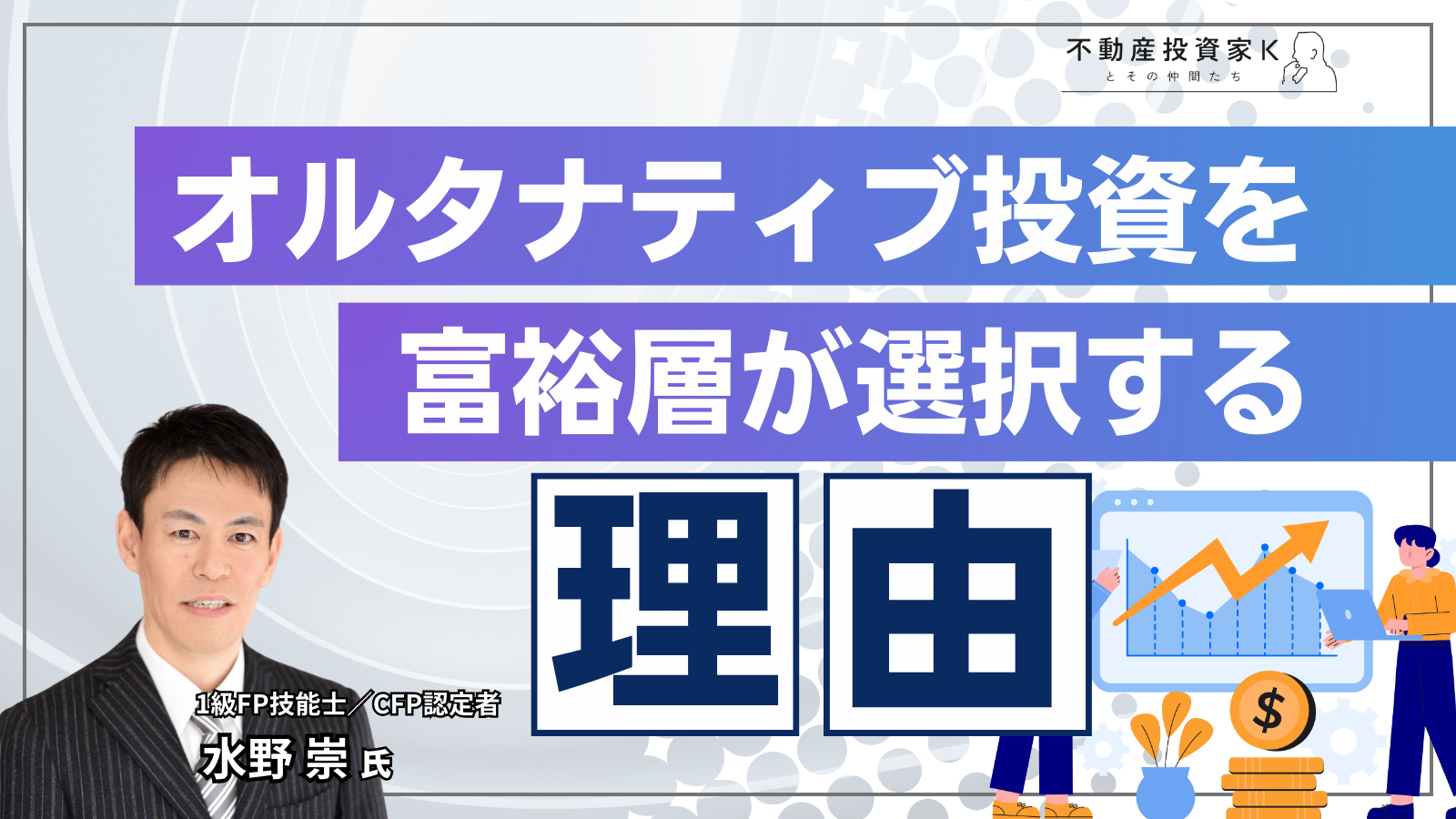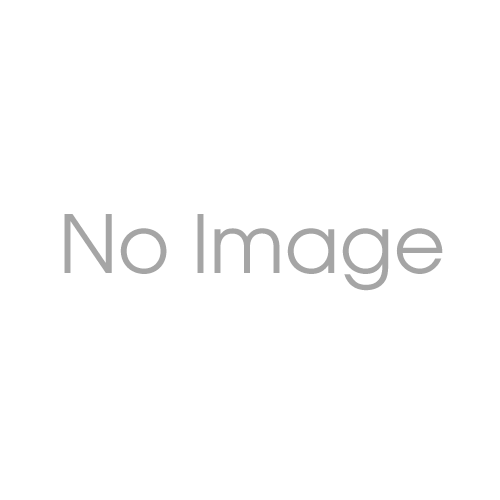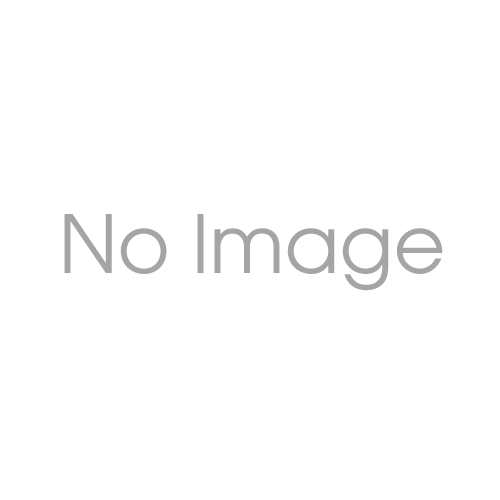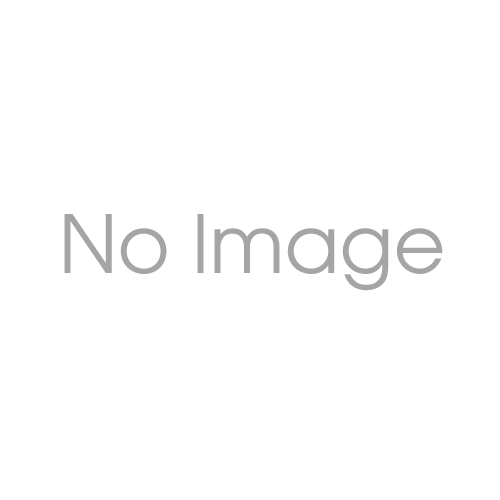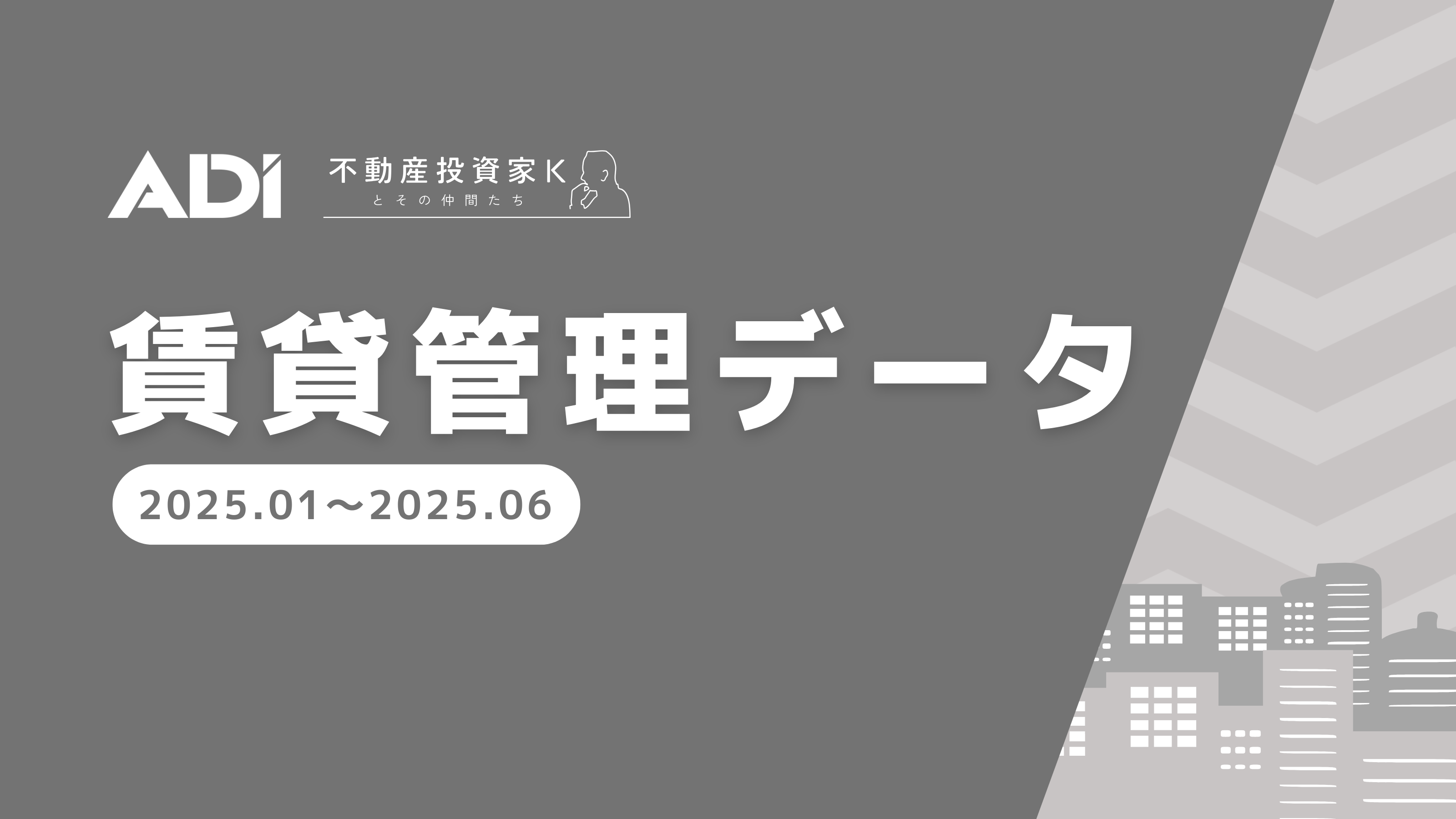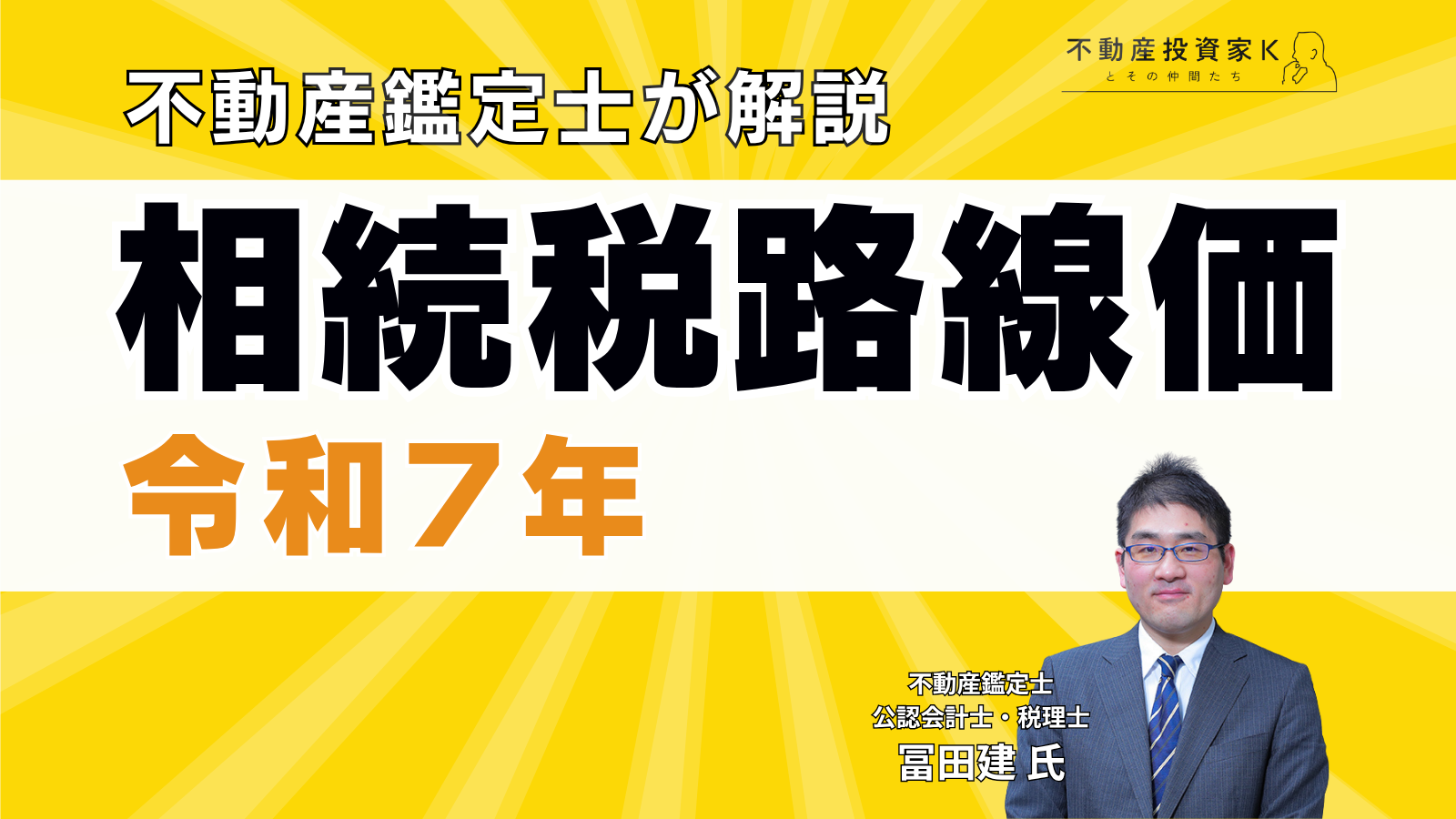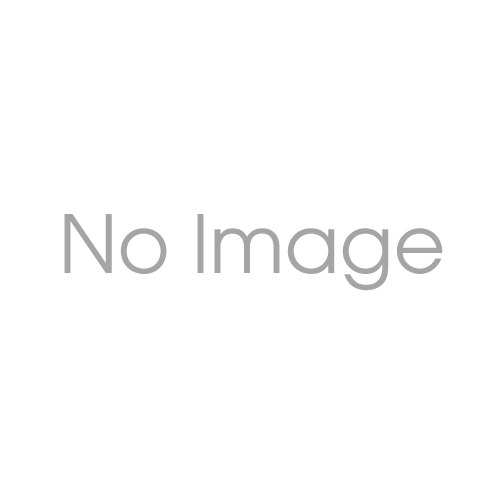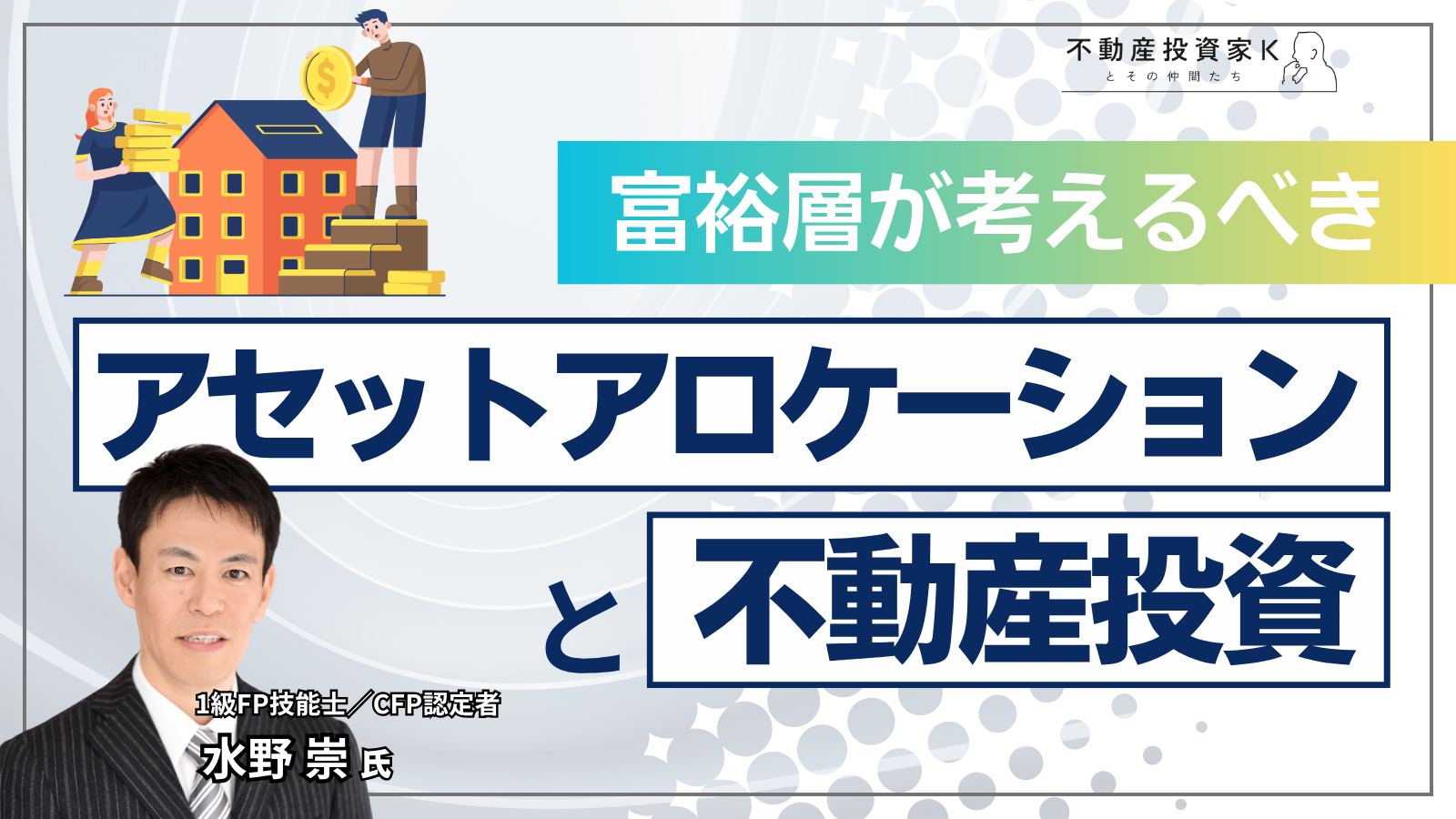
富裕層が考えるべきアセットアロケーションと不動産投資
前回コラムでは、投資で銘柄選びやタイミングよりも大切とされる「アセットアロケーション」について、基本概念を中心とした入門編をお伝えしました。今回は「富裕層が考えるべきアセットアロケーションと不動産投資」と題して、富裕層の資産運用において重要な役割を果たす「不動産投資」を取り上げます。

資産を次世代に継承するためのアセットアロケーション

アセットアロケーションを決める際は、ご自身のリスク許容度を考慮した資産配分が求められます。投資リスクを可能な限り軽減させたいと考えるのは多くの投資家の共通思考ですが、資産額やライフステージが変われば個々人のリスク許容度も変化します。
一般的なアセットアロケーションでは、株式・債券といった伝統的な資産クラスが大部分を占めます。とはいえ、足元で米国を中心に株式市場が毎年好調な推移を続けていることから、歴史的高値圏に位置する株式に対して、新たな資金を投じることに不安を感じる方は少なくありません。この傾向は投資未経験者や投資歴が浅い方ほど顕著であり、株式や債券と異なるリスク・リターン特性を有した投資先も候補になります。
一方、富裕層にとってもリスク管理は重要なテーマです。富裕層の運用目的の一つは資産を「守る」ことであり、資産規模の大きさに見合った効果的な運用を行う必要があります。それと同時に、マーケットがどのような局面を迎えても大幅な資産目減りを回避し、資産価値を維持したまま次世代への継承をできるだけ円滑に進めたいと考えています。そのためには、伝統的資産である株式・債券に加え、ポートフォリオ全体の変動幅(ボラティリティ)を緩和できる資産を投資対象に組み入れ、リスクを意識した分散投資が欠かせません。
そこで検討すべきは、「不動産」への投資でしょう。不動産は株式・債券など伝統的資産との相関性が低いことで知られ、物価上昇に対するヘッジ目的さらには資産保全の観点からもメリットが大きい資産クラスです。保有資産が増えるほど、金融資産に加えて不動産投資を検討する投資家が増加傾向にあります。不動産投資は、高い収益性と節税効果を期待できるという特徴を持ち、生前贈与・相続税対策といった点で他の金融資産よりも有利です。
不動産を組み込んだアセットアロケーションの効果

アセットアロケーションの目的は、期待リターンの最大化と下振れリスクの最小化を同時に達成することです。株式・債券といった伝統的資産は市場サイクルに左右されやすく、資産が巨額であるほど運用中のボラティリティに与える影響は大きくなります。市場の一時的な急落局面でも「売らされない」ポジションを維持するのがアセットアロケーションの鉄則であり、伝統的資産に不動産を加えることで多層化されたリスク分散のもと、ポートフォリオの安定性が向上します。
また、不動産は借入金を利用して投資するのが一般的ですが、適正な範囲内の借入金でレバレッジ効果を高めながら、長期的に資産を保有することができます。さらには、不動産は「一物四価」といわれ複数の価格が存在することで、不動産の評価額を圧縮する手段がいくつかあり、実物資産の中でも評価額を大幅に引き下げできる数少ない資産です。相続税を計算する際は時価よりも低い金額で評価されることから、贈与・相続時において重要な役割を果たす存在として知られています。
このように、不動産を組み込んだアセットアロケーションは、「相関低減によるボラティリティ抑制」「レバレッジによる資金効率向上」「税務・承継メリット」という三重の効果をもたらします。投資家自身のキャッシュフロー計画とリスク許容度の変化に応じて配分を調整することで、保有資産の長期の安定成長と次世代への円滑な資産承継の両方が実現できます。
富裕層が重視する不動産投資の優位性とは

不動産投資は安定した収益を得られるほか、節税・相続対策としても有効に活用できることをお伝えしました。実際、不動産への資産移転は多くの富裕層にも支持されています。ここでは、富裕層における不動産投資の主なメリットを確認してみましょう。
1.インフレヘッジと安定キャッシュフロー
不動産の地価や賃料は長期的に物価と連動しやすく、不動産はインフレ局面において実質価値を維持・上昇させやすい資産といわれます。消費者物価指数が上昇している近年では、都市部を中心に不動産価格の高騰や家賃の値上げのニュースを目にする機会が増えています。
オーナーの立場からすると、株式配当のように企業業績に左右されない賃料収入は、景気変動をならすクッション用の役割を果たしているのでしょう。安定的に確保できる毎月のキャッシュフローによってインカムゲインを担保しつつ、市況動向や立地を見極めて投資を行うことで、キャピタルゲインを期待できる場合もあります。
2.レバレッジ効果による資金効率の向上
不動産投資のメリットには、自己資金以上の投資を可能にする「レバレッジ効果」もあげられます。
購入時に融資を受けることで、大きな物件に投資しやすくなるのです。不動産投資の健全性を判断する指標の一つにLTV(Loan to Value)がありますが、LTVは購入価格や評価額に対する借入金の割合を示しており、全額借入金(自己資金0円)で購入した場合のLTVは100%です。そのため、LTVが低いほど安全性が高いといわれますが、自己資金をなるべく多く手元に残し低い金利の借り入れで不動産投資を行うことで、資金効率が大幅に向上します。
信用力の高い富裕層であれば、比較的低金利のローン調達も可能となるケースが多いため、レバレッジ効果も最大限に活かせます。
3.税務メリットと資産承継の合理化
建物部分の減価償却費は経費として計上できます。実際の現金支出を伴わない経費である減価償却費には節税効果があり、課税所得の圧縮によって税負担を軽減できるため、キャッシュフローが増加します。
資産承継においては、相続時の不動産評価額は相続税路線価や固定資産税評価額が基準となることで、時価よりも低い額で評価されるのが一般的であり、不動産は相続対策としてさまざまな形で有効活用されています。加えて、法人化による所得分散、信託設定、事業承継税制、ファミリーオフィスなどを併用すれば、次世代への資産引き継ぎを円滑に行いつつガバナンスも強化できます。
「まとめ」と次回コラムの案内
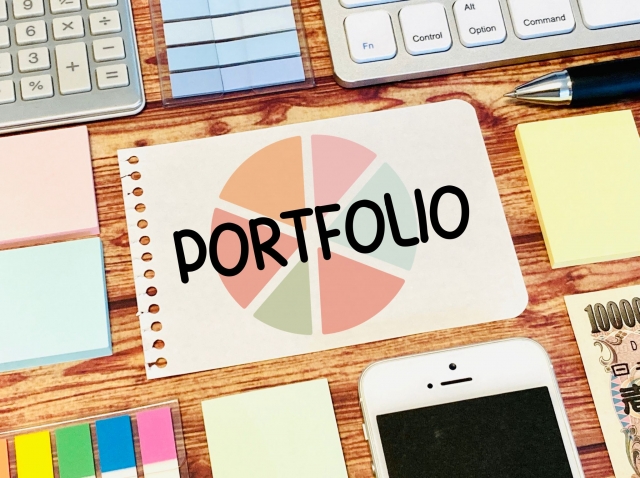
不動産は「守り」と「攻め」を兼ね備えた稀有な資産クラスに位置付けられることから、長期的な視野でアセットアロケーションを構築したい投資家にとって、単なる投資対象ではなく資産戦略全体の中核を担います。不動産は流動性の面で他の資産クラスよりも不利ですが、「守り」の投資比重を高めたいと考える多くの富裕層が、金融資産と並行して不動産への投資を重視しています。
投資では、「利回り」や「値上がり益」といった目の前の運用パフォーマンスにどうしても目を向けがちです。その点、不動産には安定的なキャッシュフローを得られる以外にも、アセットアロケーションにおける相関性の低減とともに「インフレヘッジ」「資産保全」「節税」など複合的な効用が期待できます。保有するすべての資産のバランサーの役割も果たします。
最後にお伝えしたいのは「時間を味方につける」という視点です。値動きやリスク特性が異なる複数の資産クラスへの分散効果は、長期的な保有によってこそ「複利」の威力を発揮し、リスクを分散しながらリターンの底上げにつながります。アセットアロケーションの定期的なリバランスを通じて、資産配分を最適化していくのも大切なポイントでしょう。
「不動産」という実物資産は、富裕層の資産運用・資産保全において、今も昔も極めて重要な役割を果たしています。 次回は、不動産投資と株式投資について、それぞれのメリット・デメリットなどを詳しくお伝えします。

執筆者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士
水野 崇
水野総合FP事務所代表。東京理科大学理学部卒業。相談、執筆・監修、講演・講師、取材協力、メディア出演など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。テレビ朝日「グッド!モーニング」、BSテレ東「マネーのまなび」などに出演。NHK土曜ドラマ「3000万」の家計監修を担当。学校法人専門学校東京ビジネス・アカデミー非常勤講師。一般社団法人相続・事業承継コンサルティング協会会員。
<保有資格>1級ファイナンシャル・プランニング技能士|CFP認定者|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 ほか
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!