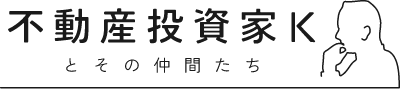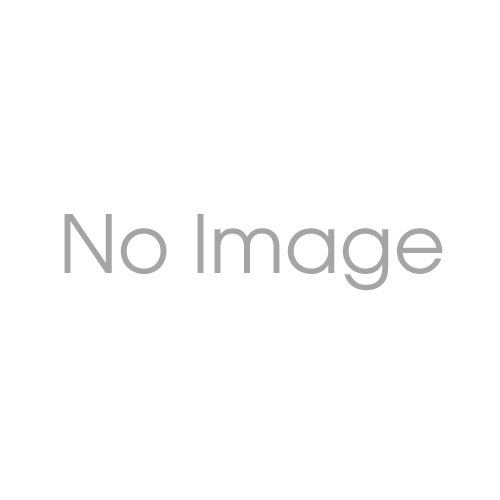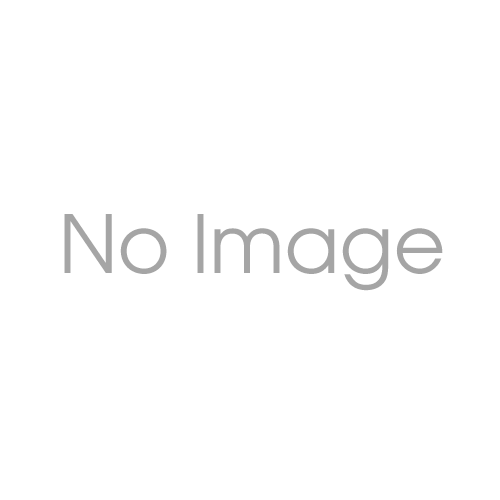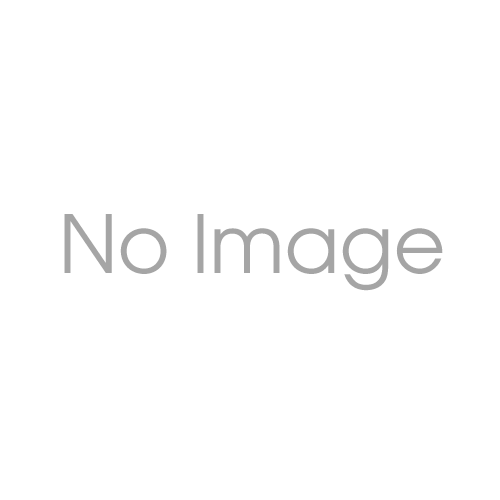
土地や建物などの不動産を所有すると、所有者には「固定資産税」が課税されます。所有している不動産によっては、固定資産税が高額になる場合があります。
本記事では、固定資産税が高くなる仕組みや、節税方法などを解説します。固定資産税は不動産を所有しているだけで課される税金です。これから購入や相続などで不動産を取得する予定の方は、ぜひ参考にしてください。
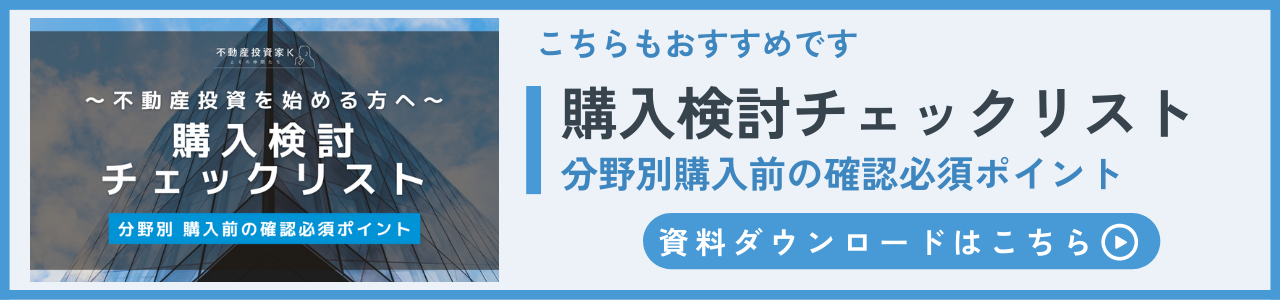
ポイント
- 地価が高く、評価額の高い不動産物件は固定資産税が高い
- 固定資産税は物件の状況によって計算方法が異なる
- 更地の固定資産税を抑えるには賃貸物件の建築が有効
固定資産税が高い理由

活用していない不動産であっても固定資産税は課税され続けるだけに、課税金額が高いと感じる人もいるかもしれません。ここでは、固定資産税が高くなる理由を、土地と建物とのケース別に紹介します。
土地の評価額が高い場合
土地に課税される固定資産税は、土地の評価額に比例する傾向があります。そのため、評価額が高い土地を所有している人は、土地の固定資産税も比較的高くなることを覚悟しなければなりません。
ここでは固定資産税が高額となる、土地の評価額が高い2つのケースを紹介します。
地価が高いエリア
地価が高いエリアに土地を所有すると、必然的に固定資産税も高額になります。地価は地方よりも都市部が高く、さらに都市部でも大都市圏の方が高いのが一般的です。
特に人口が多い東京都市圏は他の道府県の都市圏よりも地価が高いことから、東京都市部の土地は、固定資産税が高額の場合が多いと考えられます。
あわせて読みたい
宅地や整形地
土地には農業用の「農地」、林業用の「林地」、住宅用の土地である「宅地」など、使用目的に応じて複数の形態があります。農地や林地に比べて宅地の地価は高くなります。
また土地は、土地の形状が四角形できれいに整えられた「整地」と、逆に土地の形状が変形している「不整地」に区分されます。整地は利用価値が高いことで課税減額要素が少ない土地とみなされるため、固定資産税が高くなりがちです。
あわせて読みたい
高層階のマンション
分譲マンションは、分譲時の取引価格に準拠して評価額が算定されます。必然的に購入価格が高い都市部のタワーマンションは評価額も高くなります。また、分譲マンションは部屋の階が高くなるにつれて評価額も高くなることから、高層階のマンションの固定資産税は低層階よりも高くなります。
平屋や鉄筋コンクリート造
建物の固定資産税を算出する基準には、建物が建つ土地の面積と建築単価を参考にするのが一般的です。建築単価が高く、土地面積が広くなると、固定資産税も高い傾向があります。
同じ床面積の建物であれば、平家は2階建てよりも基礎や屋根部分の面積が広くなり、より多くの土地面積を必要とします。2階建てよりも広い土地に建てられた平屋の方が資産価値も高くなり、固定資産税は高く評価されます。
また、鉄筋コンクリート造の家屋は、木造に比べて建築単価が高く耐用年数が長いことから、資産価値が下がりにくく、固定資産税も高く評価されるのが一般的です。
そもそも固定資産税とは

固定資産税は1月1日の時点で所有している土地や建物などの不動産に課税される税金で、不動産の所有を続けている限り課税される仕組みとなっています。
ここでは、固定資産税の仕組みや計算方法、支払い方法、納付期限などを紹介します。
固定資産税の基本的な仕組み
固定資産税は土地や建物など不動産物件の所有者に課税される税金です。所有する不動産を売却や譲渡すれば、当然ながら固定資産税は課税されなくなります。
固定資産税は毎年1月1日時点での不動産所有者に課税される仕組みになっており、年末に不動産の売却を進めている人は、年内に売却の取引を完了させれば翌年の固定資産税が課されることはありません。ただし、実際の運用上では、売却時に売主と買主とで固定資産税を日割りで分担することが一般的です。
地方自治体による、固定資産税が決定するまでの流れは以下のとおりです。
- 1.
- 物件の調査:「固定資産税評価基準」に基づいて、地方自治体の評価員が土地・家屋などの物件調査を実施する(新築や土地売買など不動産物件の取得後、約1~3カ月以内に、事前に所有者へ通知の上で実施)。
- 2.
- 固定資産税の決定:評価員の評価による「固定資産税評価額(実勢価格の約7割)」を基に、調査した物件の固定資産税が決定される。
なお、固定資産税評価額の評価替えは3年に1回実施されています。地価の変動による不公平を回避するために、評価額は低めに設定されているのが通例です。
あわせて読みたい
固定資産税の計算方法
固定資産税は、所有する不動産の固定資産税評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%をかけて算出されます。固定資産税を求める計算式は以下のとおりです。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率1.4%
固定資産税評価額が1,000万円の場合の固定資産税は、1,000万円×0.014=14万円です。
参考:国土交通省 「土地の保有に係る税制」
固定資産税の支払い方法
土地や家屋など不動産物件の所有者には、居住地の自治体から毎年5~6月頃にその年1年分の固定資産税納付書が郵送されます。1年間を「6月・9月・12月・2月」などに4分割された納付書になっており、納付書に記載された1年分の固定資産税の金額を各回の納付期限日までに、4回に分けて支払います。
固定資産税の納付方法は、以下のとおりです。
【窓口払い】
納付書を持参の上、市町村役場、金融機関の担当窓口で支払います。またはコンビニでの支払いも可能です。
【口座振替】
各地方自治体で事前に手続きをしておけば、各金融機関での口座振替での支払いが可能です。残高不足で振替不能となった場合は、後日自治体から納付書が郵送されてきますので、その納付書にて支払う必要があります。
【カード払い】
ほとんどの地方自治体では、クレジットカードでの支払いが可能です。クレジットカード払いにすれば、曜日や時間帯も選ばずに、手持ちの現金がなくても24時間いつでも送金ができて便利です。
また、ポイント付与があるクレジットカードなら、納税のたびにポイントが貯まるメリットもあります。ただし、手数料がかかります。
固定資産税の納付期限
固定資産税は4回に分けて納付し、各期の期限までの納付が義務付けられています。納付月は自治体によって異なり、いずれも規定された月の末日が納付期限日となります。
たとえば各期が6月・9月・12月・2月の場合、第1期:6月末日、第2期:9月末日、第3期:12月末日、第4期:2月末日となります。
不動産の所有者は、自治体が定める年4回の納付期限日を確認しておきましょう。
固定資産税軽減措置の活用
固定資産税軽減措置は、住宅取得者の費用負担を軽減することで、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図る目的で制定されました。
固定資産税軽減措置が活用できる特例を以下に紹介します。
新築住宅の特例
固定資産税軽減措置により、新築住宅にかかる固定資産税は3年間(マンションなどの場合は5年間)にわたり半額に減額されます。もともと令和5年度までの措置でしたが、令和6年度税制改正の大綱により、令和8年度まで継続されることが決定しました。
新築住宅は、下記にあげた要件を満たすと、固定資産税の減税措置が適用されます。
- 2026年3月31日までに新築された住宅が対象
- 住宅として使用する床面積が全体の2分の1以上120㎡まで
- 居住部分の床面積が50㎡~280㎡まで
固定資産税評価額が1,500万円・居住面積60m2の一般住宅に課税される固定資産税は以下のとおりです。
新築住宅の特例が適用された固定資産税
1~3年目の固定資産税
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%×50%
=1,500万円×1.4%×50%
=10万5,000円
4年目以降の固定資産税
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%
=1,500万円×1.4%×50%
=21万円
参考:国土交通省 新築住宅に係る税額の減額措置財務省 令和年6度税制改正の大綱
小規模住宅用地の特例
200㎡以下の住宅用地には「小規模住宅用地の特例」が適用され、課税標準額が6分の1に減額されます。200㎡を超える部分は一般住宅用地となり、課税標準額が3分の1になります。一般住宅用地については次の章で説明します。
たとえば固定資産税評価額(課税標準額)3,300万円・150㎡の宅地の固定資産税は以下のとおりです。
小規模住宅用地の特例が適用された固定資産税
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1/6×1.4%
=3,300万円×1/6×1.4%
=550万円×1.4% =7万7,000円
一般住宅用地の特例
小規模住宅用地を除く住宅用地が「一般住宅用地」です。一般住宅用地では、200㎡を超える部分の住宅用地に課税特例が適用され、課税標準額が固定資産税評価額の3分の1として計算されます。
したがって、200㎡を超える住宅用地の場合、200㎡までが小規模宅地特例の対象、それを超える部分が一般宅用地の特例の対象となります。
一般住宅用地の課税標準額の求め方は以下のとおりです。
一般住宅用地の課税標準額 = 固定資産税評価額 ×(200㎡超の部分÷全体面積)× 1/3
固定資産税評価額が3,600万円の300㎡の住宅用地を想定して、固定資産税額を実際に計算してみましょう。
一般住宅用地の特例が適用された固定資産税
固定資産税=一般住宅用地の課税標準額×1.4%
=(固定資産税評価額 ×(200㎡超の部分÷全体面積)× 1/3)×1.4%
=(3,600万円×(100m2÷300m2)×1/3)×1.4%
=400万円×1.4%
=5万6,000円
小規模住宅用地の特例が適用された固定資産税
固定資産税=小規模住宅用地の課税標準額×1.4%
=(固定資産税評価額 ×(200㎡の部分÷全体面積)× 1/6)×1.4%
=(3,600万円×(200m2÷300m2)×1/6)×1.4%
=400万円×1.4%
=5万6,000円
固定資産税評価額が3,600万円の300㎡の住宅用地の固定資産税
固定資産税=一般住宅用地の固定資産税+小規模住宅用地の固定資産税
=5万6,000円+5万6,000円
=11万2,000円
認定長期優良住宅
2026年3月31日までに建築された新築住宅の中で「構造や設備が長期にわたって良好な状態で保たれる」と認定された住宅は、「認定長期優良住宅」として固定資産税が半額に減額されます。
認定長期優良住宅の減額対象部分は住宅用床面積のうち120㎡までです。減額期間は5年間で、地上3階以上の中高層耐火建築物は7年間となっています。
通常の固定資産税評価額が1,600万円かつ建物の面積が100㎡の新築木造住宅が認定長期優良住宅となったケースでの固定資産税の計算式は以下のとおりです。(※地上3階以上の中高層耐火建築物ではない物件の例)
認定長期優良住宅対象物件の固定資産税
1~5年目の固定資産税
固定資産税=(固定資産税評価額 ×1.4%) ×50%
=(1,600万円×1.4%)×50%
=22万4,000円×50%
=11万2,000円
6年目以降の固定資産税
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
=1,600万円 ××1.4%
=22万4,000円
リフォーム促進税制
リフォームを行うことで、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。固定資産税の減額措置が受けられる可能性があるリフォームには以下の4つです。いずれも、減税が受けられるための詳細な要件がありますので、国土交通省のホームページから条件を満たしているか確認してみてください。
| 耐震リフォーム | ・昭和57年1月1日以前から所在している住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震リフォームを行った場合 |
| バリアフリーリフォーム | ・特定の条件に該当する個人が、居住している築10年以上の住宅に対して一定のバリアフリーリフォームを行った場合 |
| 省エネリフォーム | ・個人が平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合 |
| 長期優良住宅化リフォーム | 個人が住宅に対して一定の耐震リフォームまたは省エネリフォームを行い、増改築認定を取得した場合 |
参考:国土交通省 住宅リフォームにおける減税制度について
更地の固定資産税を抑えるために
住宅などの建築物がなく、借地権などの制約もない空き地が「更地」です。更地は、住宅が建っている土地よりも3~6倍も高い固定資産税が課税されます。何も活用されていない更地に高額の固定資産税がかかるのは、土地所有者にとって大きな負担です。
更地に住宅を建てることで、固定資産税は特例により1/6~1/3にまで抑えられます。すでに自宅は別に所有している場合、賃貸物件を建てて更地を活用するのも固定資産税を抑える有効な方法です。多額の費用を必要としますが、賃貸物件に適した土地であれば、数年以内での初期費用の回収は可能です。
賃貸物件には「アパート」「マンション」「戸建て住宅」「シェアハウス」など数種類あります。それぞれ一長一短があり、どのような形態の賃貸物件が最適か、周辺環境をじっくりと検証する必要があるでしょう。
地域性に合致した賃貸物件を建てることで、固定資産税の節約と同時に家賃収入という安定した収入の確保にもつながります。
あわせて読みたい
固定資産税が間違っていることがある?
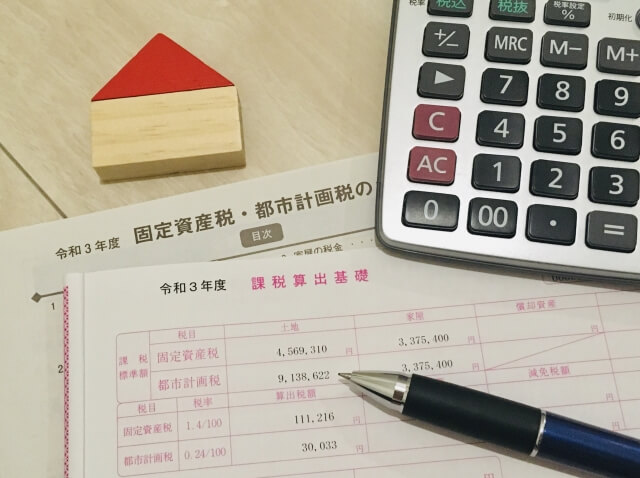
本来支払うべき固定資産税の金額よりも多く請求されており、払い過ぎてしまったという場合があります。原因は、ここまで紹介した住宅用地の特例が適用されていない場合が考えられます。
住宅用地の特例が適用されていない場合がある
よくある原因は、住宅用地の特例が適用されていない場合です。
自治体から送付された固定資産税の納付通知書に記載されている「現況地積」の内訳の欄にある「非住宅地積」の項目を確認しましょう。この項目に数字が記入されている場合は、住宅用地の特例が適用されていないことを意味します。
住宅用への変更が適用されていない
たとえば、これまで店舗として使用していた建物を廃業により住宅用に変更すると「住宅用の特例」対象物件となります。ところが、この事実を自治体が把握していないケースもあります。
こうしたケースを避けるには、自営業の廃業届を税務署に提出後、「住宅用地等申告書」を自治体に提出することが大切です。
過払い金を還付請求する方法
固定資産税を支払ってしまったあとに、過払いが発覚するケースもあります。この場合は、払い過ぎた金額分を速やかに払い戻してもらわねばなりません。
誤請求となった原因が証明できる書類を自治体の担当窓口に持参することで、過払金の還付請求ができます。建物を住宅用にリフォームした改装工事の契約書や、大型家具を購入した際の領収書などが添付書類として有効です。
税金があがる可能性があることに注意
固定資産税の過払い金の返還手続き自体は、払い過ぎた税金を取り戻す正当な行為です。ところが、固定資産税の還付請求をすることで思わぬ出費を強いられるケースが起きることもあり、充分に注意が必要です。
たとえば、自治体が申告者の課税金額を調べ直した際に、減額特例の不正利用や未納分の税金が発覚することもあります。このようなケースでは過払い金よりも多額な税金が請求されることになりかねません。
想定外の金銭的な負担を回避するためにも、固定資産税に関する特例の申請が適法かどうか、あるいは税金の未納分がないかなどを事前に確認しておきましょう。
まとめ

不動産物件に課税される固定資産税は、物件の内容や状況次第で課税金額が大幅に変動します。計算式もそれぞれの物件内容で異なり複雑化しているのが現状です。
気付かないうちに不要な税金を払い過ぎないように、固定資産税の仕組みや節税方法をよく理解しておきましょう。自身や家族が所有する不動産物件の固定資産税に関して不明な点が解決できない場合は、専門業者に相談してみるのもよい方法です。

監修者
宅地建物取引士
伊藤 公貴
アパートの建築請負営業に18年従事。自身も賃貸物件を所有しており、「顧客目線での営業」を念頭に業務に携わっている。
不動産投資家Kでは無料相談を承っております!
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!