高齢者の賃貸入居で起こりやすいリスクとは?オーナーが直面する課題と対策
高齢者向けの賃貸需要は増加傾向にあるものの、特有のリスクがあります。家賃滞納や孤独死、体調変化による事故、認知症に伴う近隣トラブルなど、一般の入居者とは異なる課題に直面する可能性があり、適切な対策が必要です。 本記事では、高齢者入居に伴うリスクの具体例と、賃貸住宅に高齢者を受け入れるメリット、高齢者入居の際にオーナーが実践できる対策について解説します。 ポイント 高齢化社会や住宅ニーズの多様化によ...
不動産投資家K
アパートが古くなると、利回りの低下や空室リスクが心配されます。これらを解消する方法の1つが、建て替えです。とはいえ、費用が気になり踏み切れないという方もいるでしょう。
そんな方へ、この記事ではアパート建て替えにかかる費用の相場と安く抑えるコツ、注意点について解説します。
\全29P「建て替えとリフォームの教科書」配布中/

アパートの建て替えには、「アパートの解体にかかる費用」「アパートを新しく建てるための費用」「現在の入居者の立ち退きにかかる費用」の主に3種類の費用がかかります
。
更地にアパートを新築するときと比べ、追加費用がかかることは間違いありません。とはいえ、アパートの建て替えは、建物の老朽化による回転率の低下や修繕費の発生など、さまざまな問題を解消または改善できる有効な手段でもあります。
まず重要なのは、これらの費用を正しく理解することです。ここでは、アパートを建て替えるときにかかる費用の概要とそれぞれの相場について解説します。
アパートの解体には、大きく分けて「建物自体を解体するための費用」「解体後の廃材の運搬・処分にかかる費用」「駐車場など土間コンクリートを解体するための費用」「屋根付きガレージなど建物付属の建築物の解体にかかる費用」の4種類の費用があります。
これらの中で高い比率を占めているのが建物自体の解体費用ですが、これは建物の構造によって相場が異なります。
| 建物の構造 | 解体費用の相場(坪単価) |
|---|---|
| 木造 | 4万~5万 |
| 鉄骨造 | 6万~7万 |
| 鉄筋コンクリート造 | 7万~8万 |
鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合、木造と比べて必要な重機の種類や大きさ、廃材の処分方法、手間がかかります。なお、これはあくまでも建物の構造による相場の違いです。実際にかかる費用は、アパートが建っている場所や規模、周辺の環境によって変化します。
また、一部の自治体では、解体を含めて建て替えについて補助金制度を設けている場合もあります。要件に合致すればかかる費用を抑える効果が期待できるので、事前に調べたり、問い合わせたりしておくとよいでしょう。
アパートの新築時には、アパート本体の建設だけでも、基礎工事から木工事、屋根・外装工事、内外装工事や電気工事、給排水衛生工事まで、実に多岐にわたる費用がかかります。また、実際にこれらの費用は個別ではなく、総額で表されます。
総額は、「坪単価」に「延べ床面積(坪数)」をかけて求めるのが一般的です。この場合、建物の構造によって坪単価の相場が変わります。
建物の構造による新築費用相場の違いがわかる具体的な例として、「2階建、1戸9坪X10戸(90坪)」の新築費用の概算を比較したのが次の表です。これは、国土交通省「建築着工統計調査」2021年度の共同住宅(貸家)工事費予定額の全国平均から計算した結果ですので、建てる場所によって金額は変わってきます。
| 建物の構造 |
新築費用の坪単価 |
建物のみの概算の新築費用 (90坪の場合) |
|---|---|---|
| 木造 | 56.2万円 (17万円) |
5,058万円 |
| 鉄骨造 | 82.3万円 (24.9万円) |
7,407万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 84.0万円 (25.4万円) |
7,560万円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 94.9万円 (28.7万円) |
8,541万円 |
参考:国土交通省 建築着工統計調査(2021年度)第34表
建物の構造は建築費用だけでなく、その後の家賃設定にも大きく影響します。どの構造で建て替えるかは、賃貸を再開したときの家賃相場も考慮して決めるとよいでしょう。
また新築の場合、外構工事費や地盤改良工事費などの「付帯工事費」や、火災保険料や不動産取得税といった「諸経費」も考慮しなくてはなりません。アパートの建て替えを検討するときは、これらの費用もすべて細かく考慮する必要があります。
建て替えの場合、解体するには、入居者が退居しなくてはならないという、新築との大きな違いがあります。アパート経営において大きな決断ですが、これはあくまでもオーナー側の事情です。
入居者にとって退居は、まさに生活の基盤を失うことであり、大変な負担を強いられる一大事に違いありません。
そのため、借地借家法は入居者に対し「正当な理由がなければ、入居者は解約に応じなくてもよい」と定めると同時に、オーナーに対しては「賃貸借の解約の申し入れは、6カ月前までに行わなければならない」と定めています。借地借家法では、正当な理由について以下のように定められています。
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(1)建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用状況、(4)建物の現況、(5)建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出、これら5つを総合的に考慮して判断されます。
通常、アパートの建て替えだけでは、入居者の居住権に対して「正当な理由」にはあたらないとされます。入居者にスムーズに退居してもらうために、多くの場合オーナーは立ち退き料を支払います。
立ち退き料の相場は一般的には賃料の6カ月分とされていますが、地域や状況によってさまざまです。なかなか合意に至らない場合には、引越し費用などを加えることもあるようです。

アパート建て替えと一口に言っても、かかる費用はつくりや規模によって大きく異なります。将来の収益を計画する上で限られた延べ床面積にどのようなつくり、規模のアパートにどの程度の費用がかかるかはしっかり把握しておくことが大切です。
ここでは木造・鉄骨造それぞれの、特定の建坪のアパートに建て替える場合の費用をシミュレーションします。計算に必要な要素や計算方法を、実際のパターンに照らし合わせてみましょう。
ここでシミュレーションするのは、次のような木造アパートの建て替えにかかる費用です。
このアパートを同じ木造2階建てアパートに建て替えるときかかる費用の相場は次の通りです。
このシミュレーションで重要なのは、それぞれの「坪あたり費用」です。坪あたり費用は依頼する建築会社によっても、建てる土地やアパートのグレードによっても大きく違ってきます。計算方法を参考に大まかに計算し、正確な金額は複数の見積もりを参考に相場を把握しましょう。
次のような鉄骨造アパートの建て替え費用をシミュレーションしてみましょう。
こちらの建て替えには次のような相場の費用が必要です。
鉄骨造は木造より坪あたり費用は高めになりやすいため、事前の見積もりや比較検討はより重要といえるでしょう。

アパートの建て替えには新築以上の費用がかかりますが、それを差し引いてもメリットがあることも事実です。ただし、それはあくまでも建て替え前と比べた場合という意味です。建て替え前の状況と、建て替え後の綿密な比較と計画との比較があって初めて現実的に検討を始めることができます。
ここでは、建て替え前と建て替え後の変化と合わせて建て替えのメリットについて解説します。
建て替えの大きな理由の1つは、家賃収入の改善でしょう。たとえ立地条件が良かったとしても、建物が老朽化すれば賃貸物件としての魅力は下がり、だんだんと空室期間が長くなってくるものです。
空室対策のため、家賃を下げざるを得なくなるかもしれません。さらに老朽化が進めば、よほどのことがない限り、再び家賃を上げることは難しいでしょう。
そのような場合にアパートを建て替え、新築に変われば、これまでより家賃も高く設定できる可能性があります。Wi-Fiを完備したり防犯設備を追加したりすれば、追加費用はかかるでしょうが、それ以上のリターンが得られるかもしれません。
建物は老朽化するほど、雨どいが割れたり壁にひび割れが入ったり、さまざまなほころびが目立つようになります。大きな問題でなければまだよいのですが、雨もりのように入居者の生活に悪影響を与える時は早急な対応が必要です。
しかし、建て替えれて新築に変われば、当分の間老朽化による修繕は必要なくなります。エアコンや給湯システムなどの設備には保証期間があり、新調すれば一定期間は余計な出費はありません。オーナーにとっても、急な出費に対する不安の軽減につながるでしょう。
アパート経営における重要な費用項目の1つに、減価償却費があります。減価償却費は、収入を得るために必要な固定資産について、経年劣化する分として毎年計上できる費用です。
アパートの建物は、不動産収入を得るために必要な固定資産にあたるため、一定期間、減価償却費を計上できます。逆にいえば、期間を過ぎると費用計上できなくなるということでもあります。費用計上できなくなれば、その分所得が増えることになり、より高額な所得税を納めなくてはならなくなります。
減価償却できる期間は建物の構造により異なります。アパートの場合、木造で22年、鉄骨造で19〜34年、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で47年と定められています。現在それぞれの期間を超えているアパートは、建て替えれによって減価償却費を計上して所得税を抑えられる、つまり節税が可能になります。
また建て替えは、相続税対策にもなり得ます。アパートを建て替えたとき、オーナー名義のローンを利用していれば、相続時、資産総額からローン残高が差し引かれ相続税を抑えることができるからです。相続する子どもや孫にとっても、築古のアパートより、資産価値が高く、節税にもなる新築アパートの方が良いでしょう。
アパートの建て替えは目先の数年だけでなく、5年・10年先のメリットまで見越して計画・実行したいものです。
参考:東京都主税局 償却資産の評価に用いる耐用年数
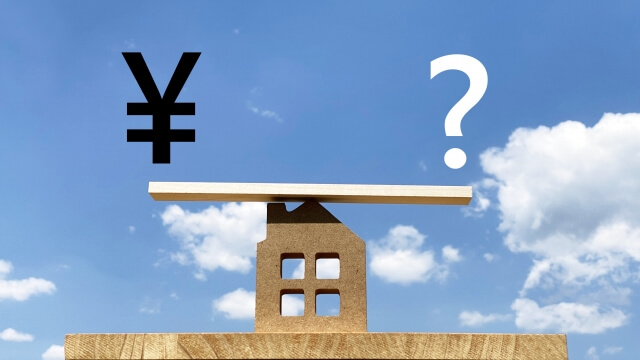
アパートの建て替えにはメリットがありますが、まとまった費用がかかることでもあります。経営を考えれば、収入はできるだけ高く、支出はできるだけ抑えたいもの。ここでは費用を抑えるコツについて解説します。
解体費用と新築費用、退去費用、その他の支出を抑えるコツを、1つずつ見ていきましょう。
解体費用を上手に抑えるには、「複数の解体工事会社から見積もりをとって比較する」「建物の周辺や近隣住民には十分に配慮する」「固定資産税の課税のタイミングを避けて解体する」の3つに留意することです。
解体費用には相場がありますが、建っているエリアや周囲の状況など、さまざまな理由によって実際にかかる費用は異なります。そのため解体費用の見積もりを、1社だけでなく2〜3社からとって比較し、金額と内容を詳しく検討することをおすすめします。
また解体から新築まで、まとめて依頼できれば、それぞれ別の会社に依頼するよりずっと手間が少なく済むだけでなく、解体から新築までスムーズに移行できるというメリットもあります。
ただし、そのためには解体前の時点で、建て替えと資金に関する綿密な計画が必要です。ある程度の時間の余裕をもって計画しましょう。
また解体や新築では騒音や振動などによって近隣住人とトラブルになることも少なくありません。対処を誤るとその後の関係が悪くなったり、余計な工事費が発生したりする可能性があります。
工事前には丁寧に、ご近所へ挨拶に回り、連絡先を記したチラシも忘れずに配布しておきましょう。
固定資産税の課税価格は、毎年1月1日時点における土地の状況・要件によって決まります。通常、アパートが建っている土地は、アパートが建っていることを条件にもとの課税価格の約4分の1程度に軽減されています。しかし、1月1日に解体を終えていると、土地の固定資産税は4倍になってしまいます。
できるだけ、建物が建っている状態で1月1日を迎えられるよう計画すると良いでしょう。
新築費用も解体費用と同様、複数の業者の見積もりを比較することが重要です。加えて新築の場合、どのようなアパートにするかというプランも比較する必要があります。
特に大手ハウスメーカーであれば、自社で製造した建築部材を使用していたり、中堅メーカーでも独自の工業加工法で高品質ながら価格を抑えていたりと、各社さまざまな特色があります。相見積もりをとることで、オーナーはより理想に近いプランを選ぶことができるでしょう。
また、もし計画時点で土地が余る場合は、その土地を売却または活用して新築費用に充当すると、結果として新築費用を抑えることができます。なお、土地の一部を売却する場合は、土地の境界を確定し、文筆しなくてはならない点は注意が必要です。
退居費用を抑えるには、まず入居者と丁寧に対面交渉する必要があります。最低でも退居の6カ月前までに通知しなくてはなりませんが、それ以上前から協力を仰ぎ、立退料を含めスムーズに退去してもらえるよう、立ち退き料も含めて交渉していきましょう。
もし建て替えまでに期間があるようなら、自然退居の後、新しい入居者を入れない、または賃貸契約を定期賃借契約に切り替えて短期間入居を募集するなどして、全体の入居戸数が減るタイミングで建て替えられるよう調整するこおとも1つの方法です。
費用が高額で工面できなかったり物件が再建築不可だった場合など、建て替えが難しい場合は、建て替え以外の方法も検討するとよいでしょう。たとえば間取りや古い設備のために入居率が伸び悩んでいるだけなら、リフォームで十分対応できるかもしれません。
リフォームの良い点は、1戸単位から可能なことです。自然退居した後にリフォームを行えば、ニーズの多い間取りで設備の備わった物件として、家賃を高めに設定することもできます。そうすれば解体費用はもちろん、退居費用も発生させずに物件の価値を上げることも可能です。
建て替えだけが、収支改善の手段ではありません。今抱える問題は何か、原因を正しく分析し、それに対する最適な解決方法を模索することが重要なのです。
こちらの記事もおすすめです

アパートの建て替えには新築費用をはじめ多額の資金が必要なため、計画を具体的に進めるにはなんとかして資金を捻出しなければなりません。
ここではアパートオーナーが建て替えに利用できる資金の捻出方法を解説します。それぞれの特徴や要件をきちんと把握しておきましょう。
アパートローンは不動産投資用にアパートを購入したり、建築したりする際に利用できるローンです。アパートローンは、契約者本人または家族が居住する建物に必要な資金確保の手段「住宅ローン」とは異なります。
自己資金や経営実績、返済計画などを含め、住宅ローンよりも厳しく審査されます。これはアパートが不特定多数へ提供する居住施設であり、空室や災害などのリスクなどから得られる収益が不確実とされるためです。
アパートローンの審査には、過去のアパート経営やローン返済の実績が影響する場合があります。これまでの経営状況が良好であれば、金融機関から評価され、審査にも有利に働きやすいでしょう。
アパートの建て替え資金を、日本政策金融公庫からの融資でまかなう方法もあります。
日本政策金融公庫は政府系の金融機関であり、主に中小企業を支援することを目的としています。企業だけでなく個人でも利用でき、経営するアパートの建て替え準備金についても、比較的低金利での資金調達が可能です。
融資には次の要件を満たしている必要があります。
また借入期間は最大20年とされているため、契約者の年齢や借入予定金額、さらに建て替え後の建物の仕様なども慎重に検討する必要があるでしょう。
参考:日本政策金融公庫 一般貸付
アパートの建て替えの際に、国が推進する事業として補助金を受けられる場合もあります。
うまく利用すれば、付加価値の高い建物をより安価で建てることができるでしょう。これからのアパート経営も踏まえ、利用を検討してみましょう。
子育て支援型共同住宅推進事業は、アパートを含む共同住宅の新築に適用可能な、国土交通省主導の事業です。アパートの新築ではこのうち「子育て建設型」に該当します。
アパートやマンション、長屋タイプの戸建て賃貸住宅が対象で、事故防止や防犯など子育て支援として子どもが安全かつ安心して暮らせる共同住宅の建築について、補助金が支給されます。
子育て建設型が適用されるための主な要件は次のとおりです。
補助金の限度額は1戸あたり100万円ですが、別途居住者の交流を促すための施設への補助は500万円が限度です。
参考:国土交通省 子育て支援型共同住宅推進事業について
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、住宅の新築や既存住宅の省エネ改修に対して支援を行う事業です。
補助金は対象の住宅ごとに次のとおりとされています。
この補助金の対象となるには、まず新築するアパートの住戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下でなければなりません。</p
また、長期優良住宅・ZEH水準住宅は、「18歳未満の子を有する子育て世帯」または「夫婦のいずれかが39歳以下の若者夫婦世帯の居住が条件となります。
参考:国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業について

アパートの建て替えには多額の資金と一定の期間が必要です。資金と時間はどちらも経営に大きな影響を与える要素であるため、アパートの新築工事が無事着工するまでの流れはしっかり把握しておく必要があるでしょう。
ここではアパート建て替えの大まかな流れについて解説します。
まずはアパート建て替えの計画をできるだけ具体的かつ詳細に作成します。現在の収益性や建て替えた後の収支のシミュレーション、新築する建物の仕様、引渡しまでのスケジュール、立ち退き料の予算決定などについて検討しましょう。
新規入居者の募集停止や立ち退き交渉にかかる期間も含めると、建て替え予定の2年または3年前には作成する必要があるでしょう。
あわせて建て替えの目的や必要な理由も明確にすることも重要です。そうすれば新しい建物の仕様がスムーズに決められ、立ち退き交渉の際に納得してもらうための材料の整理もできます。
建て替え計画が決まったら、計画に沿って新規入居者募集を停止します。ただし立ち退きまでに時間があれば、定期借家契約で新規に入居してもらうのは有効です。
定期借家契約なら定めた期日までの入居が明確なため、こちらの希望の期日までにスムーズに退去してもらえるだけでなく、その間の家賃収入も得られます。
また、現在入居している世帯へ立ち退きを通知して退去日や立ち退き料について交渉しましょう。アパートの立ち退きについては、借地借家法第28条によって「正当な理由が必要である」と定められています。
参考:e-Gov 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)
正当事由には「建物が老朽化して建て替えが必要な場合」も含まれていますが、入居者から理解が得られるとは限りません。「旧耐震の建物であるため早急に耐震改修が必要」など具体的な理由を提示し、理解を得る必要があります。
立ち退き交渉を進めつつ、アパートの新築工事請負契約やかかる費用をまかなうためのアパートローン契約も進めます。計画作成の段階でしっかり情報を収集し、手順や審査通過の見込みなども把握しておけば、よりスムーズに進められるでしょう。
建物の構造の変更や大きな設備や機器の導入があれば、必要な資金は高額にのぼることもあります。複数の建設会社に見積もりをとり比較検討するなど、工事に突発的な費用を発生させないよう慎重な準備が必要です。
すべての入居者が立ち退けば、既存アパートの取り壊しができます。通常、アパートの解体工事には2週間から1カ月程度かかりますが、建物の場所や周囲の状況によって解体に必要な期間は変わるため注意が必要です。
また、解体工事では騒音や瓦礫運搬のトラックの出入りなど周辺住民に対して負担をかけることが予想されます。通常、周辺住民への事前連絡は解体業者が行いますが、もしトラブルが発生すれば発注した施主の責任が問われるかもしれません。業者に任せきりではなくきちんと確認することが大切です。
取り壊しが完了すれば、アパート新築工事請負契約にのっとって計画通り新築工事を開始します。解体工事と新築工事を同じ会社に依頼できればよりスムーズな工事も可能です。建築会社の選定では、事前に問い合わせておきましょう。
アパートの新築工事には、アパートの階数+1カ月が目安とされていますが、構造や所在地周辺の状況、外構工事の必要などさまざまな要件によって変わります。木造2階建てなら3カ月程度、状況によっては4〜6カ月程度かかる可能性も含めて計画しておくと突然の変更にも対応可能です。
新築アパートが完成したら、施主検査後に引き渡しを受けます。計画通りの仕様になっているか、傷などの不具合がないかなど細かな部分も入念に確認しましょう。
アパートの建て替えは、費用も高額で時間もかかる一大事業です。スムーズに計画を進め、効果的に収支を改善させるためには注意すべき点がいくつかあります。計画立案の際は、ぜひ注意点を加味して検討してください。
アパート建て替えに必要な費用と、建て替え後に想定できる家賃や利回りを試算してみると、より実現性の高いアパート建築費を算出することができます。そのためには周辺の家賃相場やニーズの傾向といった情報収集が欠かせません。
不動産会社や管理会社、ハウスメーカーなどに相談し、収支計画のための情報を集めましょう。
綿密な収支計画であるほど、将来のトラブルを避けることにつながります。細かい費用やその支払いタイミング、支払い方法に至るまでできる限り細部まで把握することが大切です。
建て替えに欠かせない入居者の退居は、6カ月以上前に通知しなくてはなりませんが、通知したからといって期日までに退居が完了するとは限りません。
建て替えが「やむを得ない事情にあたらない」と判断される以上、オーナーと入居者の双方の合意が必要なため、期間を制限することはできないからです。
通知後スムーズに合意できる場合もありますし、1年たっても合意できない場合もあるでしょう。建て替えたい期限があるのなら、入居者に相応の時期と条件を提示し、丁寧に交渉することが大切です。
解体にしろ新築にしろ、信頼できる会社を選ぶことは重要なポイントです。しかし、費用は安いが仕事が荒くてトラブルが多い業者や、期待以上の仕事をするけれど費用は驚くほど高額、などさまざまな業者が存在します。
アパートの建て替えを前提とする場合、新築の後のメンテナンスや経営について相談できるような不動産のプロフェッショナルへの依頼であれば、ある程度費用がかかってもそれ以上の価値があるかもしれません。
アパート経営には、厄介なトラブルが発生する可能性があります。そのようなときも、信頼できる会社であれば、毎日不安が少なく安心して経営できるでしょう。せっかく建て替えるのであれば、建てた後の経営の相談にも乗ってくれるような、頼れる会社を選びたいものです。

アパートの建て替えに関する費用について、さまざまな視点から解説してきました。建て替えには高額な費用がかかるものの、それに見合うだけのメリットも期待できます。
ただし、そのためには、それぞれの費用の特徴や抑えるためのコツや注意すべき点を正しく把握し、実際に計画に盛り込むことが大切です。
ただ費用を抑えればよいのではなく、建て替え後の想定家賃や収支計画とのバランスを考えて適切に投資する必要があります。アパートを上手に建て替えるためには、十分な情報収集と、時間に余裕をもって始めることが大切です。

監修者
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
現在、不動産会社で建築請負営業と土地・収益物件の仕入れを中心に担当している。これまで約20年間培ってきた、現場に密着した営業経験と建築知識、不動産知識を活かして業務に携わっている。
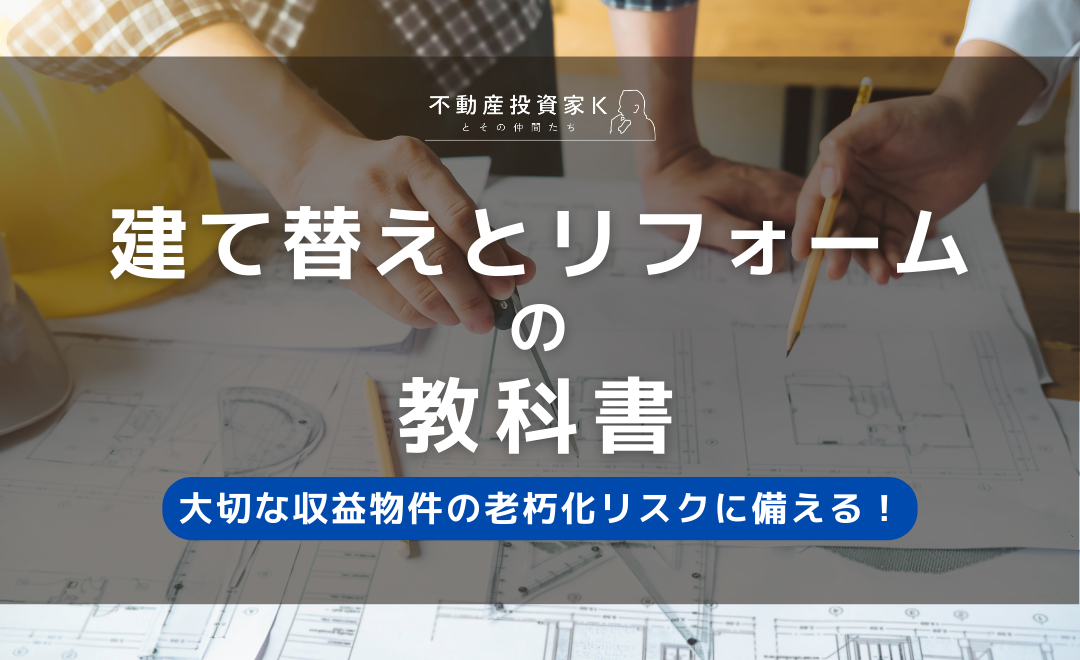
建て替えとリフォーム、どちらの方が物件に適しているのか悩んでいる方へ。アパート建て替えの流れとポイント、リフォームとの違い、費用についても解説。大切な収益物件の老朽化リスクに備えましょう。リフォームローンについても解説しています。
高齢者向けの賃貸需要は増加傾向にあるものの、特有のリスクがあります。家賃滞納や孤独死、体調変化による事故、認知症に伴う近隣トラブルなど、一般の入居者とは異なる課題に直面する可能性があり、適切な対策が必要です。 本記事では、高齢者入居に伴うリスクの具体例と、賃貸住宅に高齢者を受け入れるメリット、高齢者入居の際にオーナーが実践できる対策について解説します。 ポイント 高齢化社会や住宅ニーズの多様化によ...
土地にかかる固定資産税は、住宅が建っている土地に比べて更地の方が高くなります。住宅が建っている土地には住宅用地の軽減措置が適用されるためです。宅地を更地のままにしている人は、不動産投資などで住宅を建築することで固定資産税の節約になる場合があります。 本記事では、土地のみの場合の固定資産税の計算式や計算方法、節税方法を解説します。 ポイント 更地の固定資産税は、住宅用地の特例が適用できないため住宅が...
賃貸経営を成功させるうえで、どんな管理会社に管理を任せるかは非常に重要なポイントです。 一口に「管理会社」といっても、実はその出身や得意分野によって特徴は大きく異なります。この記事では、賃貸管理会社を母体別に5つのタイプに分け、それぞれの特徴や向いているオーナー像を解説します。 ポイント 賃貸経営の成功は、管理会社の選択にも左右される 賃貸物件の管理会社は、その母体によって大きく5つのタイプに分け...
インボイス制度は2023年10月から始まった消費税に関する新しい制度であり、不動産オーナーにも影響を与える場合があります。法人テナントなど課税事業者が借主の場合、不動産オーナーが免税事業者のままでは、仕入税額控除を受けるためのインボイスを発行できません。 本記事では、不動産オーナーの賃貸運営に及ぼすインボイス制度の影響や、登録しない場合のリスク、登録のメリット・デメリットについて解説します。 ポイ...
賃貸アパート・マンションの経営でよくあるのが、ゴミ出しのトラブルです。ゴミ捨て時間を守らない・分別のルールを無視しているなど、さまざまなトラブルが発生することがあります。 本記事では、賃貸アパート・マンションのゴミ出しでよくあるトラブルや原因、放置することのリスク、トラブルへの対処法を紹介します。 ポイント 賃貸アパート・マンションではゴミ出しのトラブルが起こりやすい ゴミ出しのトラブルはルールの...
大家になるために、特別な資格は不要ですが、アパート経営を行う目的や理由を明確にしたり、不動産投資の基本知識を身につけたりする必要はあります。また、どのように資金を調達するかまで考えることも必要です。 この記事では、大家になるにあたってどのような準備が必要なのか、またどのような流れで大家になるかなどについて解説します。将来的に大家になりたい人は、ぜひ最後までご覧ください。 ポイント 大家になるための...
資産承継は、財産を次世代に安全かつ計画的に引き継ぐための手段です。承継対象資産の整理や承継者の明確化を行い、遺言書や信託を活用することで、相続時の手続きや税負担を軽減できます。 本記事では、資産承継のステップや円滑に進めるためのポイントなどを詳しく解説します。 ポイント 資産承継とは、保有する資産を次世代や後継者へ引き継ぐこと 資産承継を円滑に進めるためには、計画と手順に沿った準備が大切 円満に資...
所有している土地を有効活用したいけれど、「多額の初期費用がかかるのではないか」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。実は、まとまった資金なしでも、所有している土地を活用して利益を得られる方法はいくつかあります。ただし、そのリスクや注意点はしっかり確認しておく必要があります。 本記事では、資金なし・少額で土地活用を始める方法や注意点、土地活用が可能な土地の条件について解説します。 ポイント...
東京でのアパート経営は、賃貸需要の高さや家賃水準の高さといったメリットがある一方で、地価や建築費の高さ、利回りの低さといった課題もあります。 本記事では、東京ならではの特性を踏まえ、アパート経営のメリットと注意点をわかりやすく解説します。 ポイント 東京でのアパート経営は安定した賃貸需要と高い家賃収入が見込める 東京でアパート経営する際は、地価の高さや利回りの低さ、税金の高さに注意が必要 東京のア...
海外移住を予定していたり、海外赴任の可能性のある賃貸不動産のオーナーにとって、日本国内の賃貸経営や税務対応は大きな課題となります。入居者対応や家賃管理、家賃収入の確定申告などは現地から直接行うことができないため、管理会社への委託や納税管理人の選任が不可欠です。 本記事では、海外に移住・赴任するオーナーが直面するリスクや対応策を解説し、安心して賃貸経営を続けるためのポイントを紹介します。 ポイント ...