不動産投資はフルローンで組める?フルローンを利用するポイントや注意点などについて解説
フルローンとは、不動産を購入するにあたってかかる費用を、すべて金融機関の融資でまかなうことです。 フルローンを利用すると頭金がない人でも希望の物件を購入できる可能性が広がりますが、キャッシュフローが出にくくなる、金利の上昇の影響を受けやすくなるなどのリスクも存在する点に注意が必要です。また、利用には、一定以上の金融資産を有している、不動産投資ですでに成功していることなどがあげられます。 本記事では...
不動産投資家K
中古物件は少ない初期投資から始められますが、築年数が経っている分、家賃も相場より低めに設定せざるを得ないというデメリットがあります。そのような中古物件を生まれ変わらせるのがリノベーションです。
この記事では、リノベーションの定義やメリット・デメリット、注意すべき点と成功のポイントを解説します。
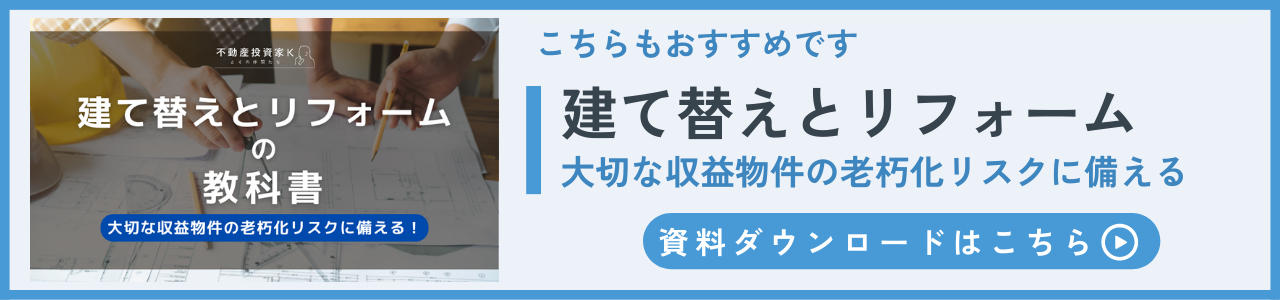
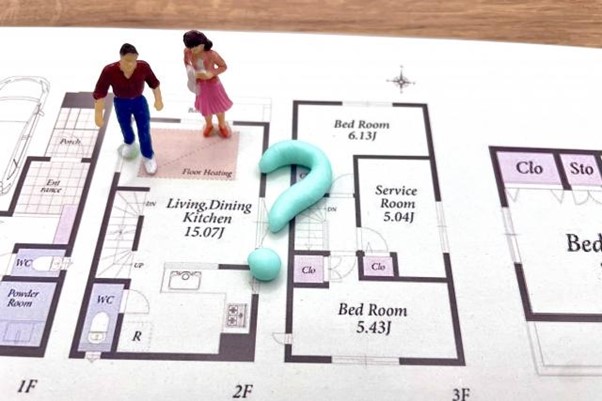
リフォームは、英語のRe(再び)form(形・姿)という言葉どおり、中古物件を以前あった姿や性能に戻すのが主な目的です。経年劣化のために壊れたり汚れたりしたところを修繕し、もとのようなきれいな状態に戻します。新築時点での姿や性能をゼロとすれば、マイナスになったものをゼロまで戻すイメージです。
一方リノベーションとは、英語のRenovationが語源で、日本語でいうと刷新や更新を意味し、「元どおり」というより「新たに別のものに作り直す」に近い用語です。新築時点をゼロとすれば、こちらはゼロ以上、プラスにまで価値を付加することを表しています。
リノベーションによって、物件に新しい価値を付加できれば相場以上の収入が得られる可能性があります。リノベーションとは、中古物件を新しい形でよみがえらせ、収益を改善できる手法といえるでしょう。

リノベーションは元の構造や設備を一新し、別の機能や性能を付加することで物件に新たな価値を生み出す手法です。物件を生まれ変わらせ、収益性を上げることも可能です。ここでは、不動産投資物件をリノベーションするメリットについて紹介します。
古い物件を安く手に入れて、リノベーションすることで、よりニーズの高い物件にすることが可能です。
新築の物件を購入するよりもリノベーションの方が一般的にトータルの費用を安くできます。リノベーションは、不動産投資家にとって実益に直結する「コストを抑える」というメリットがあります。
さらに、リノベーションにかかった費用は全額経費として計上できるため、確定申告での所得を減らすことができ、結果的に所得税を抑える効果も期待できるでしょう。
リノベーションする前提で物件を探すと、より物件やエリアの選択肢の幅が広がります。中でも、新築だと高額になりがちな立地の良いエリアも、築年数が経った物件であれば相場よりも安価で購入出来るでしょう。
つまり、リノベーションを前提にすれば築古物件も扱うことが出来るため、新築物件では予算的に厳しい好条件の物件やエリアでの購入も視野に入れることが出来るのです。
旧式の浴室とトイレを刷新する、リビングと和室の間の壁を取り除いてフローリングのリビングに変えるなどは、築古物件のリノベーションの一例です。ほかにも、ウォークインクローゼットやキッチンカウンターを設置したり、壁にアクセントクロスを取り入れたり、共用スペースを設けて入居者同士のコミュニケーションを打ち出したり、さまざまな方法が考えられるでしょう。デザイン性や希少性を高めることで、より高収益の得られる物件に生まれ変わる可能性があります。
周囲の環境とはマッチしていない物件を、優良物件に生まれ変わらせることができるのもリノベーションの魅力です。
たとえば、独身者向けにワンルームや1DK、1Kの間取りの需要が大きかったエリアが、周辺環境の変化に伴いファミリー層の多い街に変貌した場合、単身向けのアパートのニーズは減少してしまいます。このときワンルーム8部屋のアパートを、4部屋に集約してファミリー向けに間取りや設備を一新すれば、借り手をファミリー層というターゲットに変えられます。
不動産投資家に求められるのは、ターゲットに適した物件かどうかの見極め力です。不動産賃貸では、空室リスクはできる限り低くすることが重要です。そのようなときに、ニーズの変化や想定したターゲットに合わせて物件づくりができるリノベーションは有効であると言えるでしょう。

リノベーションにはメリットがある一方、もちろんデメリットもあります。いずれもリノベーションするなら避けられない要素ではありますが、リスクであることには違いありません。正しく把握して、適切に対処するよう努めましょう。
リノベーションは修繕だけでなく、物件の魅力を上げるための改修を行います。そのためリノベーションは、リフォームよりも高額なコストがかかります。
大切なのはリノベーションによって、コスト以上の収益が得られるかです。計画段階で、できるだけシビアに想定しておく必要があります。
リノベーションを依頼する際には、見積りをしっかりと取り、事業計画と照合して確認を行いましょう。
あわせて読みたい
リノベーションはコストだけでなく工事にかかる日数も考慮しなくてはなりません。工事期間中は賃貸できず家賃収入を得られないからです。
また、リフォームよりもリノベーションの方が工事が長くかかる場合が多いため、十分に想定しておく必要があるでしょう。
リノベーションには、コンセプトや戦略が重要です。コンセプトや戦略を誤ると思うような収益を得ることができず、投資効果が薄くなってしまうリスクがあります。リノベーションには高額な費用がかかるという点や、リノベーションの工事期間中に収入が得られないというデメリットも踏まえると、きめ細やかな計画を立てることでリスクを最小限に抑えてから行いたいところです。
リノベーションにはアイデアやひらめきも重要ですが、なにより的確なニーズの把握と、ニーズを前提としたコンセプトや戦略、高いクオリティの施工が欠かせません。リノベーションを実施する前に、あらゆる方面からの情報を集めて検討することが大切です。

アパート1棟をまるごとリノベーションする場合、工事の範囲にもよりますが工事前の打ち合わせや準備に2〜3カ月程度、工事開始から引き渡しまでの2.5〜3カ月程度かかり、合計すると最低でも4カ月以上が目安です。
また、リノベーションの規模が大きいほど運び込む資材の量が増え、保管場所や作業スペースも限られるため、さらに期間が長くなることも十分に考えられます。

リノベーションしている期間は入居ができないため、できるだけ短期間で完了させられるよう、リノベーションは効率よく進めたいものです。そのためには複数の手順を並行して進める必要もあるでしょう。忙しくなるからこそ、抜けや漏れがないように流れを把握しておくことが大切です。
ここではリノベーションを実施する際の流れを解説します。
まずは周辺環境と物件の現地調査を行いましょう。
周辺の市場調査ができればどのくらいの賃料が設定できるか、リノベーション後にどのくらいの利回りが期待できるかが見えてきます。また、リノベーションの詳細についても、曖昧にせず、オーナーの希望を明確に施工業者に示すことが大切です。
もし調査によって当初想定していたリノベーションが困難とわかったら、適したリノベーションを提案してもらうこともできます。
リノベーションの方向性が定まったら、次は施工プランをいくつか作成してもらい、比較検討します。費用の見積もりはもちろんのこと、完成イメージをCGや手書きのスケッチなどで視覚的に確認することも、検討するうえでは重要なポイントです。
施工プランの内容は、費用が予算内に収まるように材料や設備を見直しながら、理想とコストのバランスを取りながら検討します。リノベーションしたい内容の優先順位づけをしておくと、見積もりがよりスムーズにできるでしょう。
施工プランと費用が決まったら、次は工事契約の締結です。リノベーション費用を借り入れる場合は、金融機関でローンの申し込みを始めましょう。
工事契約では、施工内容や工事の範囲、工期、料金や支払いの条件、アフターフォロー内容などを書面で取り交わします。その際、着手金として費用の半分を支払い、残りを引き渡し後に支払うのが一般的です。
契約締結後、施工業者またはアパートのオーナーが、工事開始前に近隣住民に挨拶し、工期の日程や周囲への影響について説明し、理解を得るようにしましょう。施工中に定期的に進捗を確認することも大切です。必要に応じて施工業者と打ち合わせ、気になる点は随時確認しましょう。
施工が完了したら、オーナーが立ち合いのもと、契約通りのリノベーションになったことを確認し、引き渡しを受けます。引き渡し後は、工事費用の残金や追加で費用が発生した場合は、追加費用を精算すればリノベーション工事は完了です。

不動産投資にとってリノベーションは、収益性を上げるための方法の1つです。自由度が高いからこそ客観的に考え、収益の上がりやすいポイントを押さえる必要があります。ここでは、これらの注意点を1つずつ詳しく解説します。
不動産の需要はエリアによって変わるため、どのエリアの物件を選ぶかは重要です。一般的に次のようなエリアは、長期的な需要が見込めると考えられます。もちろん将来の開発計画にも注意が必要です。
リノベーションにかかる初期投資のコストを回収し、利益を上げるためには長期的な需要が重要であり、物件のエリア選びがポイントとなります。
築年数の古い物件の方が価格は安く、かかるコストを抑えられます。しかし、あまりに古い物件の場合、老朽化による問題が出てくるため注意が必要です。
築年数があまりに古い賃貸物件は、一般的に人気は高くありません。建物自体の古さによる外観はもちろん、中の設備も相応に古いことが考えられるためです。
設備には簡単に交換できるものも多いですが、たとえば建物の下に埋め込まれた水道管は、劣化しても簡単には交換できません。交換する場合、工事は大がかりになり、費用も高額になる可能性があります。
マンションであれば、物件の専有部分だけでなく、エントランスや階段、エレベーター、通路といった共用部分の古さもネガティブな要因になります。専有部分はきれいでも、共用部分が汚れたり破損していれば、それが原因で敬遠される場合もあります。
他に、築年数の古さから金融機関からの融資の返済期間が短く設定されてしまう可能性があることも注意すべき点です。返済期間が短いと毎月の返済額が増え、最終的にキャッシュフローが悪化するため、毎月手元に十分な資金が残らなくなる可能性があります。
あわせて読みたい
どのような物件でも、希望のデザインや間取りでリノベーションできるわけではありません。リノベーションにも限界があり、天井の高さや水回りの位置などは変更できない場合もあります。
また、区分所有のマンションは、専有部分以外のリノベーションはできません。戸建ても建築基準法や条例によって、一定の制限を受けます。必ずしも希望通りとはいかないこともあると思っておく必要があります。
リノベーションするときは事前に、対象物件が希望通りのリノベーションをできるかどうかを確認することが重要です。その際は、リノベーションに強い業者と一緒に、物件を確認するのがおすすめです。プロの目で一般には気付かないようなポイントをチェックしてくれます。
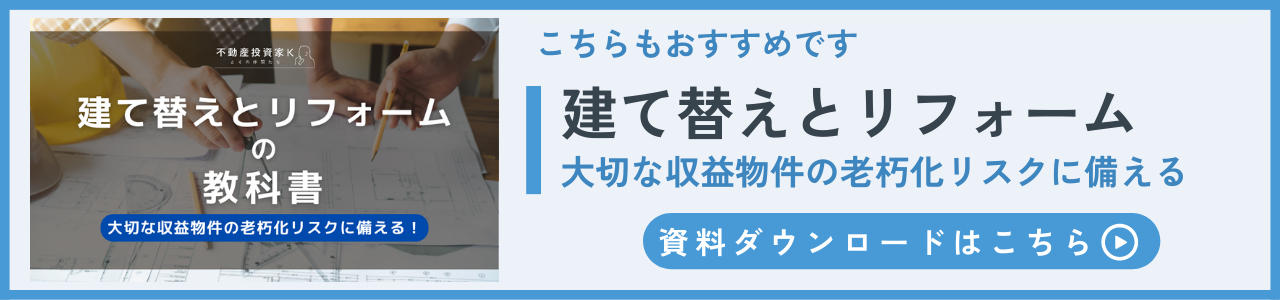
長期的に需要が見込めても、それだけでは十分ではありません。不動産投資には細かな計算や算段が重要で、リノベーションにかかるコストが想定している期間で回収可能かどうか、できるだけ正確に把握することが求められます。
もちろん、投資である限り、計画通りにいかないこともあります。リノベーションを実施する前には、万が一の災害や空室リスクなど、想定できるさまざまなリスクに備えて事業計画を外すことが大切です。

リノベーションにかかる費用は、アパートのどの部分が対象かによって異なります。予算の関係で1棟まるごとのリノベーションが難しい場合は、建物の一部や設備のリノベーションも可能です。
ここではアパートのリノベーションを1棟まるごと行う場合と、箇所別に行う場合の費用の目安を紹介します。
アパートを1棟まるごとリノベーションする場合は、内装だけでも1戸あたり120万円〜400万円程度かかります。仮に10戸のアパートの内装をリノベーションするのであれば、1,200万円〜4,000万円程度かかる計算です。
さらに外壁や建物の耐震補強工事などリノベーション箇所が増えるほど、費用はかさみます。そのため、アパートのリノベーションは、入居者のニーズを考慮しつつ、優先してリノベーションすべき箇所を慎重に検討する必要があるでしょう。
アパートを部分的にリノベーションする場合、場所ごとにかかる費用は異なります。正確な金額は工事部分の状態やリノベーションの程度でも変わりますが、ここでは一般的な費用の目安を紹介します。
アパートのリノベーションとして、構造については耐震補強、外壁については外壁塗装が考えられます。構造は居住の安全性に直結する重要な部分であり、外壁などの見た目は家賃設定にも関わる重要な要素です。
一般的な2階建てにかかる費用は、およそ次のとおりとされています。
居室内装のリノベーションでは、各部屋の内装を改修します。内容別の費用の目安は次のとおりです。
ただし、内装リノベーションの費用は、用いる素材によっても大きく変わることには注意が必要です。耐久性はもちろんデザインや部屋全体の雰囲気と、費用とのバランスを見ながら決める必要があるでしょう。
内見では、毎日使うキッチンやトイレ、浴室といった水回りの設備は特に厳しくチェックされます。リノベーションにあたって水漏れしないのはもちろん、清潔な印象を与えることが重要です。キッチン・水回りの費用の目安は次のとおりです。
なお、洋式便器の温水洗浄便座は20万円以下で設置できます。
その他のリノベーション箇所と費用の目安は次のとおりです。
また、リノベーション期間に得られない家賃収入についても費用として考慮する必要があるでしょう。
「子育てグリーン住宅支援事業」(https://kosodate-green.mlit.go.jp/)は、子育て支援と2050年カーボンニュートラル実現の観点から設けられた制度です。対象のリフォームは以下の1〜3のうち2つ以上を実施することが必須条件で、これを満たした場合のみ、4〜8もいずれかを3つ目として申請できます。
補助金の金額は2種類実施で最大40万円、3種類実施なら最大60万円です。申請受付期間は2025年3月31日から2025年12月31日までですが、予算の上限に達し次第終了します。
工事完了後の申請となるため、補助金の利用を希望するのであれば期間内に間に合うよう調整しましょう。
家庭のエネルギーの多くを占める給湯について、高効率給湯器の導入と普及拡大を目的とするのが「給湯省エネ2025事業」(https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/)です。
対象となるのは2024年11月22日以降に着工する給湯器の交換リフォームで、補助される金額は設置する高効率給湯器によって次のとおり異なります。
ただし、アパートのような共同住宅等において補助の対象となるのは、上記のいずれか1台までです。申請期間は2025年3月31日から遅くとも2025年12月31日までとされ、予算の執行状況によって申請受付は終了する場合があるため注意が必要です。
「先進的窓リノベ2025事業」(https://window-renovation2025.env.go.jp/)とは、住宅の省エネ化を推進するため、断熱性の高い窓に交換するリノベーションを補助する制度です。
対象となるのはガラスの交換、内窓の設置、外窓交換で、窓の改修と同時に施工した場合のみドア交換も対象とされます。給付される補助金は、工事費用の2分の1(最大で200万円まで)です。
申請期間は2025年3月31日から遅くとも2025年12月31日までですが、予算に達し次第締め切られるため、施工完了時期には注意しましょう。
「賃貸集合住宅給湯省エネ2025事業」(https://chintai-shoene2025.meti.go.jp/)は家庭のエネルギー消費のうち給湯分野における省エネ化を推進するため、賃貸集合住宅への小型の省エネ型給湯器の導入を支援することを目的としています。
補助の対象となるのは、2024年11月22日以降に着工するエコジョーズやエコフィールなどの小型の省エネ型給湯器への交換工事です。追い焚き機能の有無によって補助額は異なり、1台あたり5万円〜7万円が支給されます。
申請期間は2025年3月31日から遅くとも2025年12月31日までで、限度額に達すれば締め切られます。
また、複数の給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて「子育てグリーン住宅支援制度」と併用することも可能ですが、1つの機器に対して重複申請することはできないため、注意が必要です。
「次世代省エネ建材の実証支援事業」(https://sii.or.jp/meti_material06/)は、既存の住宅へ高性能断熱材や蓄熱調湿材などの次世代省エネ建材の効果の実証を支援することを目的としています。
補助されるのは該当する次世代省エネ建材を用いたリノベーション費用のうち、補助対象項目の2分の1以内です。それぞれの改修方法ごとに上限額が設けられていることにも注意しましょう。
申請は住宅の所有者または所有予定者が、リノベーション施工前に行います。

リノベーションを成功させるには、新しいアイデアとニーズの両方のバランスをとることが大切です。ここではより効果的なリノベーションのために、まず確認したいポイントを解説します。
ニーズのある設備を導入することは物件の魅了を高める方法の1つです。どんな設備を導入すれば良いかわからない場合は、人気が高い物件にはあって自身の物件にはない設備をリストアップしてみましょう。
たとえばアパートのモニター付きのインターホン、戸建ての最新式のドアキーや目隠しフィルムを施した窓などは防犯面で大きなプラスポイントです。そのほか、宅配ボックス、浴室乾燥機、無料インターネットなど、ニーズのある設備は多くあります。
以下の記事では家賃査定に影響する設備も紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
物件の内見で、強く印象付けるのは見た目です。とくに室内の印象は、壁紙や床材、和室なら畳の状態が大きく影響します。古い壁紙や床材は、経年劣化によるシミや汚れによって印象が悪くなってしまい、入居もつきづらい傾向にあります。逆に言えば、壁紙や床材を新しくするだけで入居ハードルが低くなると言えるでしょう。
壁紙や床材の交換は、リノベーションの中では比較的簡単に行えます。コストを抑えて印象を大きく変えられる手法であるため、リノベーションの第一歩として検討することをおすすめします。
物件を選ぶときの大きな要素の1つが間取りです。例えば、リビングと和室が隣り合っている場合、古い間取りだとふすまで仕切られている場合が多く見受けられます。敷居が天井から低い位置にあるふすまは、リビングも和室もどこか狭い印象を与えがちです。
そのような物件の場合であれば、リノベーションでふすまを敷居ごと取り払い、フラットなフローリングにして広いリビングにリノベーションする方法があります。こうすることで、元の和室よりも広々とした空間へ生まれ変わり、同じ広さの居室であっても受ける印象が大きく変わります。また、入居者目線で見たときにも、現代の過ごし方にあったお部屋作りがしやすくなるでしょう。
1Kや1Rタイプの間取りの場合、3点ユニットをバス・トイレセパレートタイプにすることも、時代のニーズを捉えたリノベーションの1つです。
間取りの変更はリノベーションの中でもかなり大きな工事のため、建物の構造によってはできない場合があります。実現可能かどうかは、必ず業者へ確認しましょう。
ここでは、実際にリノベーションを行うことで家賃がアップした、リノベーション成功事例をご紹介します。

居室内はもちろん、エントランスにオートロックと宅配ボックスを新設、共用部までリノベーションを行った事例です。リノベーションを行いデザイン性を高めることで、立地の良さを最大限に活かした物件に蘇らせました。単純に賃料がアップしただけではなく、このリノベーションによって入居者の決まりやすさにもプラスの影響が出ています。
出典:株式会社アーキテクト・ディベロッパー 「事業紹介 リブランディング事業」
エントランスアプローチには軽やかな色合いのインターロッキングを施し、居室はホワイトを基調としながらヘリンボーン木目調の床材とグレー調の壁というマンハッタンスタイルなリノベーションの事例です。
室内はフレームキッチンやブラックフレーム間仕切りとシェルフによってラグジュアリーな空間を演出し、ワンランク上の大人をターゲットとしています。共有部のエントランスにスマートロックや宅配ボックス、集合ポストを導入し、より快適な暮らしを実現する設備を完備しました。
リノベーションにより、設備や内装をグレードアップした結果、平均家賃11~12万円から45%程度アップしました。
出典:株式会社アーキテクト・ディベロッパー 憧れのマンハッタンスタイルのお部屋が完成 ~ADIのリノベーションマンション「Belleviage Morishita」の一室を公開~

効果的なリノベーションには、ニーズの正確な把握が必須です。ターゲットを明確にし、どのようなデザインや設備が人気なのか、ライバル物件と差別化を図るにはどのような特長を打ち出すのか、戦略をたてましょう。
購入する物件をしっかりと選ぶことも重要です。物件によってはリノベーションの内容に制限があることも念頭に、事前の確認を怠らないようにしておきましょう。
不動産投資家Kとその仲間たちでは、「土地を相続する予定だけど、どうすれば良いか検討している」「管理が大変なので、土地を売却したいと思っている」など、土地・建物のさまざまなご相談を承っております。
あなたやあなたの家族の大切な資産を有効に活用できるよう、お気軽にご相談ください!

監修者
宅地建物取引士、第一種衛生管理者
九州から上京、新卒から今日まで都内を拠点として不動産業界一筋、7年目。バックオフィスからフロントまでさまざまな業務を経験し、現在は既存物件のリニューアル事業に携わっている。
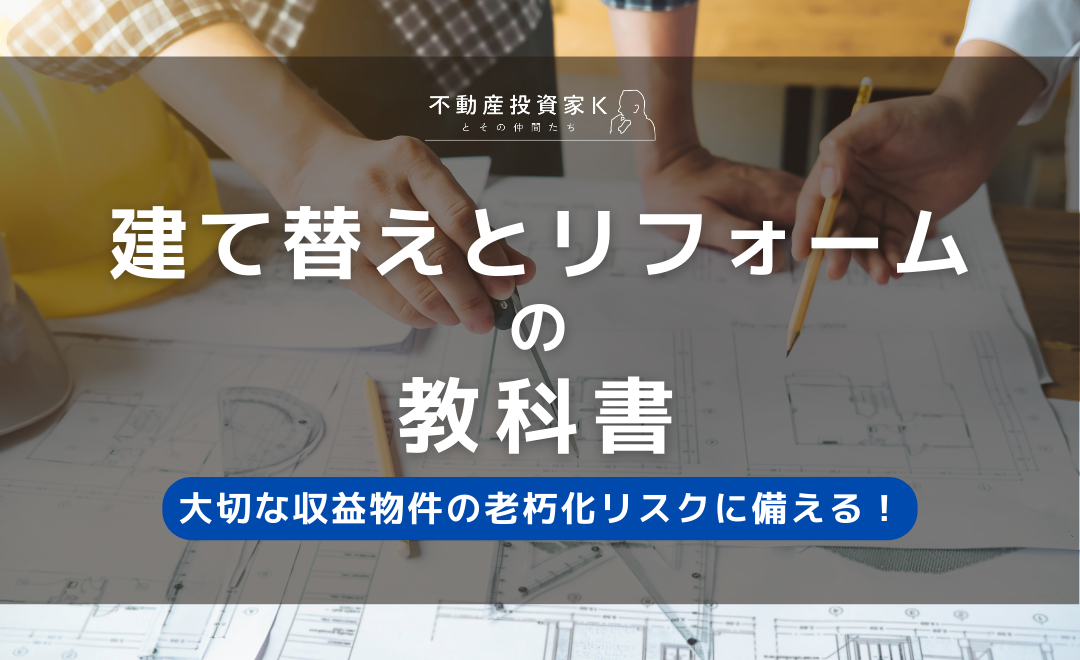
収益物件の老朽化は避けて通れない問題です。中古物件投資を行う方も必見!検討すべきは建て替えかリフォームか、ポイントや費用について解説します。
フルローンとは、不動産を購入するにあたってかかる費用を、すべて金融機関の融資でまかなうことです。 フルローンを利用すると頭金がない人でも希望の物件を購入できる可能性が広がりますが、キャッシュフローが出にくくなる、金利の上昇の影響を受けやすくなるなどのリスクも存在する点に注意が必要です。また、利用には、一定以上の金融資産を有している、不動産投資ですでに成功していることなどがあげられます。 本記事では...
不動産の家族信託とは、信頼する家族に不動産の管理・運用を任せることです。家族信託することで、所有者の判断能力が低下しても不動産を管理・運用でき、将来の相続や承継に備えることができます。 一方で、契約作成や登記手続きには手間や費用がかかり、受託者の負担も生じるなどの注意点を把握しておくことも重要です。 本記事では、不動産を家族信託するメリットや手続きの流れ、おすすめの人などについて、わかりやすく解説...
高齢者向けの賃貸需要は増加傾向にあるものの、特有のリスクがあります。家賃滞納や孤独死、体調変化による事故、認知症に伴う近隣トラブルなど、一般の入居者とは異なる課題に直面する可能性があり、適切な対策が必要です。 本記事では、高齢者入居に伴うリスクの具体例と、賃貸住宅に高齢者を受け入れるメリット、高齢者入居の際にオーナーが実践できる対策について解説します。 ポイント 高齢化社会や住宅ニーズの多様化によ...
土地活用の方法は数多くあり、広さや立地条件、周辺環境などに合った方法を選ぶことで、安定した収入や税制上のメリットを得ることが可能です。 本記事では、27種類の土地活用方法とそれぞれの特徴、メリット・活用する際の注意点を紹介します。 ポイント 土地活用は収益の確保や税金対策のほか、地域貢献につながる場合もある 賃貸経営や駐車場経営のほか、土地の広さや立地などに応じたさまざまな土地活用がある 田舎・郊...
所有している空き家を有効活用する方法として、「自分たちで住む」「賃貸として活用する」「更地にする」などがあります。また、近年は空き家バンクをはじめとする空き家を有効活用するための公的制度も登場しているため、必要に応じて利用するとよいでしょう。 ただし、空き家の活用には「修繕費がかかる」「借り手が見つからない可能性がある」などのリスクがあることも理解しておく必要があります。この記事では、空き家の具体...
不動産投資の種類は数多く、それぞれ特徴や収益を得る仕組みが異なります。また、不動産投資の目的は「収入の増加」「相続税対策」「インフレ対策」「老後のための資産形成」の大きく4つに分けられます。どの目的を重視するかによって最適な投資方法は変わるため、慎重な選択が必要です。 この記事では、14種類の不動産投資の特徴やメリット・デメリットを解説します。 ポイント 不動産投資の主目的は「収入の増加」「相続税...
賃貸経営を成功させるうえで、どんな管理会社に管理を任せるかは非常に重要なポイントです。 一口に「管理会社」といっても、実はその出身や得意分野によって特徴は大きく異なります。この記事では、賃貸管理会社を母体別に5つのタイプに分け、それぞれの特徴や向いているオーナー像を解説します。 ポイント 賃貸経営の成功は、管理会社の選択にも左右される 賃貸物件の管理会社は、その母体によって大きく5つのタイプに分け...
インボイス制度は2023年10月から始まった消費税に関する新しい制度であり、不動産オーナーにも影響を与える場合があります。法人テナントなど課税事業者が借主の場合、不動産オーナーが免税事業者のままでは、仕入税額控除を受けるためのインボイスを発行できません。 本記事では、不動産オーナーの賃貸運営に及ぼすインボイス制度の影響や、登録しない場合のリスク、登録のメリット・デメリットについて解説します。 ポイ...
賃貸アパート・マンションの経営でよくあるのが、ゴミ出しのトラブルです。ゴミ捨て時間を守らない・分別のルールを無視しているなど、さまざまなトラブルが発生することがあります。 本記事では、賃貸アパート・マンションのゴミ出しでよくあるトラブルや原因、放置することのリスク、トラブルへの対処法を紹介します。 ポイント 賃貸アパート・マンションではゴミ出しのトラブルが起こりやすい ゴミ出しのトラブルはルールの...
大家になるために、特別な資格は不要ですが、アパート経営を行う目的や理由を明確にしたり、不動産投資の基本知識を身につけたりする必要はあります。また、どのように資金を調達するかまで考えることも必要です。 この記事では、大家になるにあたってどのような準備が必要なのか、またどのような流れで大家になるかなどについて解説します。将来的に大家になりたい人は、ぜひ最後までご覧ください。 ポイント 大家になるための...